介護現場では、利用者の状態によってインシデントやアクシデントが頻発することがあります。
よくあるのが、利用者の転倒などです。
1人では安定した歩行ができないのに歩こうとして転倒するパターンが多いように感じています。
この場合の対応としては、介護職員の
- 見守り強化
- 付き添い対応
などが挙げられますが、実際の介護現場では人員不足ということもあり、そう単純に解決したり改善できるものではないのが実情です。
1人の利用者に介護職員が24時間付き添うことなど到底不可能なのです。
そもそも、24時間付き添うことなどマンツーマン介護であるはずの在宅介護でも不可能でしょう。
ですから、転倒などのインシデントやアクシデントが頻発する利用者の場合は、他の対応が必要になってきます。
一番重要なのは、「介護職員だけに負担や責任を押し付けるのではなく、事業所全体で検討していく」ということです。
転倒したことがキッカケとなりお亡くなりになった利用者に対して、事業所への損害賠償が成立した判決もありました(下記記事参照)。
こんな(介護職員や介護現場にとって)理不尽な状況が続発すれば、「転倒などのインシデントやアクシデント(事故)が頻発する利用者の対応に苦慮してしまう」ということになります。
かと言って、既に入所してしまっている利用者の状態を理由に退所を促したり受け入れを拒否することもなかなか難しい状況なのが現状です(正当な理由が無ければ受け入れ拒否や退所勧告もできないため)。
では、どうすればいいのかを以下で具体的にご紹介したいと思います。
転倒などのアクシデントが頻発する利用者の対応を事業所全体で検討していく具体例
高齢者でなくとも、人間である以上は転倒する可能性は誰でもあり得ます。
筋力や心身機能が衰えてきている高齢者であれば、尚更転倒のリスクが高いことは必然です。
高齢者の転倒が不可避である理由について、詳しくは下記記事をご参照下さい。
では、この状況に対して「介護現場で事業所全体で検討していく」には、具体的にどうすればいいのでしょうか。
介護職員や介護現場に押し付けない
まず、大前提なのが「介護職員や介護現場にその負担や責任を押しつけない」ということです。
これをしてしまうと、介護職員や介護現場の負担や責任が重くなるだけでなく、
- 追い詰められた介護職員がストレスフルになる
- 介護現場だけでは解決方法に限界があるため結局何も変わらない
- 追い詰められた介護現場の職員の退職が相次ぐ
- 追い詰められた介護職員の退職が相次ぐことで人員不足となり益々転倒などの事故が多発する
という悪循環に陥ってしまいます。
ですから、事業所全体で検討し対応していくことが重要になってくるのです。
まずは、このポイントをおさえておくことが非常に大切です。
入所前(入所時)に家族に説明をして了承を得る
入所前又は入所時に、利用者本人及びキーパーソンとなる家族に入所説明が行われます。
その際に、「転倒は起こり得るもの」「転倒は防ぎきれないもの」という事実をしっかりと説明をし、了承を得ておく必要があります。
何故なら、家族の中には「介護施設に入所させたら完璧な介護をしてくれるのだから転倒などが発生するはずがない」「お金を払っているのだから転倒などの事故が発生すれば責任を取ってくれるはず」と思い込んでいる人がいるからです。
ですから、そういう「淡い期待」や「異常な権利者意識」を現実世界へ引き戻した上で「納得してもらう」必要があります。
その上で、入所してもらうことこそが「事業所全体で検討していく第一歩」なのです。
適宜、家族へ報告し情報のアップデートを行う
入所時はそれほど転倒のリスクがなかった利用者でも、介護施設で生活を続けていく中で、転倒のリスクが高くなっていく場合があります。
また、入所時(又は入所前)に説明した内容を家族が失念したり、「そもそも聞いていない」などと言ってくる場合もあります。
ですから、利用者の状態や転倒のリスクがあることを、入所後も適宜、家族へ連絡したり現状の報告をして情報をアップデートさせていくことも大切です。
つまり、
「今後、転倒する危険がありますよ」
「転倒することは十分考えられますので、知っておいて下さいね」
ということを改めて家族へ報告し理解を得ておくのです。
これをすることで、「聞いていない」ということを防ぐことができます(もちろん、情報のアップデートをしたことを記録にも残します)。
これは、介護職員が行ったり、生活相談員や施設ケアマネが行うなど事業所や状況によって様々でしょうが、これをすることが「事業所全体で検討していくこと」に繋がります。
家族への連絡や報告の頻度やラインを取り決める
転倒などのインシデントやアクシデントが発生すれば、家族への連絡や報告が必須になります。
これが、「毎日のように発生」「1日に何回も発生」ということがあり得ます。
この場合、
- 家族へ連絡や報告をする職員に負担が掛かる
- 連絡や報告をされる家族にも負担が掛かる
ということが往々にしてあり得ます。
この場合、事故の発生頻度や受傷状況や家族の希望などを総合的に判断して、連絡や報告をする頻度やラインを取り決めておくことが大切です。
これにより、家族へ連絡や報告をする職員の負担がグッと減ります(場合によっては家族の負担も減ります)。
但し、施設側や介護職員だけの都合になってしまうと、家族の不信感やクレームに繋がる場合があるので、事前に家族とラインを取り決めておくことが重要です。
中には、些細なことでも連絡や報告が欲しい家族もいるからです。
例えば、
- 病院受診に繋がらない転倒などの事故は報告不要(面会時に生活の様子として報告)
- 病院受診に繋がらない場合は週に1回まとめて連絡や報告をする
などです。
この取り決めは、カンファレンスなどで議題にあげてもいいでしょうし、それなりの人がそれなりのタイミングで家族へ伝えるのもいいでしょう。
つまり、「事業所全体で検討していくこと」が大切なのです。
解決策や改善策も事業所全体で検討
転倒などのインシデントやアクシデントが頻発する場合、多くの場合は第一発見者となる介護職員に負担も責任ものしかかってきます。
リスク報告書の改善策にも、
- 見守り強化
- 可能な限り付き添いを行う
などと書くことになりますが、現実問題、そう簡単にはいきません。
改善策を職員間で共有していたとしても、人員不足の状態では「対応不可能な改善策になるから」です。
対応不可能な改善策を書くことは、「良くないこと」ではありますが、「人員不足のため」「人員不足を解消して転倒を防止する」とは書けないために四面楚歌状態なのが現場の介護職員なのです。
リスク報告書に「人員不足が原因」と書けない理由については、下記記事をチェックしてみて下さい。
では、具体的にどうすればいいのでしょうか。
この場合、「事業所全体で検討していくことが重要」です。
例えば、
- 手の空いている職員(上司や他職種含む)が見守りや付き添いを行う
- 介護職員が見守りや付き添いをできない場合のヘルプを出せるような環境づくりをする
- 状況に応じて総合的に判断して、薬の調整や退所なども検討する
などになります。
介護現場で介護職員だけが負担と責任を被って対応する場合と比べて、大幅に解決や改善する可能性が高くなります。
解決や改善がしやすくなれば、介護職員だけでなく事業所や利用者本人や家族にとっても得策でしょう。
ですから、転倒などのインシデントやアクシデント事故が多い利用者の対応は、事業所全体で検討していくことが非常に重要なのです。
最後に
今回は、転倒などのインシデントやアクシデント事故などが多い利用者の対応は事業所全体で検討していくことが重要であり、その具体例について記事を書きました。
まとめとしては、
- 介護職員や介護現場に押し付けない
- 入所時や入所前に家族に説明をして了承を得る
- 適宜、利用者の状態を家族へ説明し情報のアップデートを行う
- 家族への連絡や報告の頻度やラインを取り決める
- 転倒などの解決策や改善策も事業所全体で検討していく
ということになります。
介護職員や介護現場にばかり負担と責任を押しつけていると何も解決しないどころか、益々悪循環に陥ってしまうことになります。
介護職員や介護現場に何もかも押し付けてしまっているために、転倒などが頻発する利用者の対応に苦慮している介護事業所のご参考になれば幸いです。




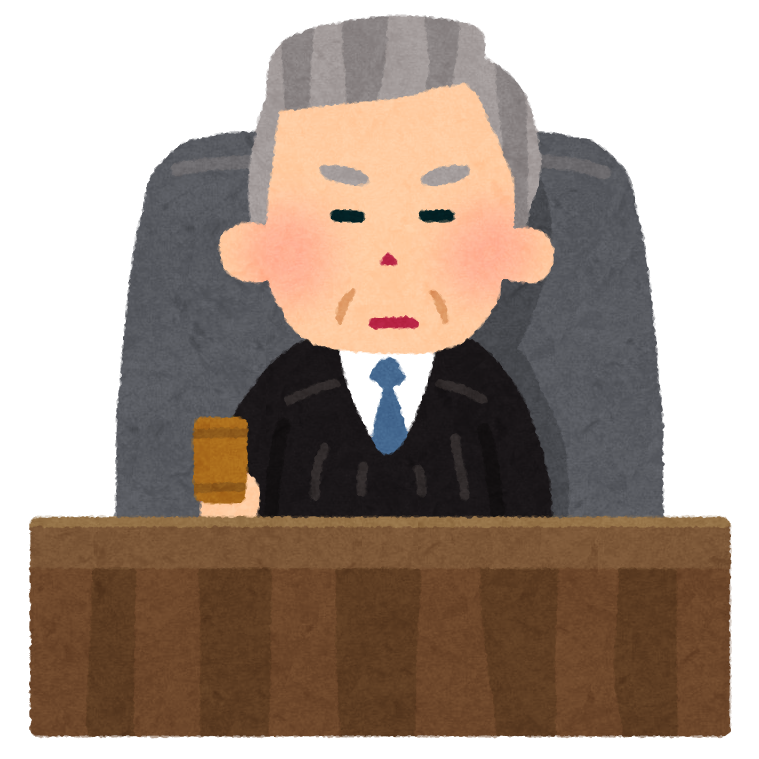










コメント
以前話した笑う介護士は以前デイの施設長をしていた時ウチは事故ゼロですって言ってました。それで転倒事故あった時は事故の大小関わらず職員を怒鳴り散らしたらしいです。施設の面目潰したと、
しかも休みの職員まで呼び出して深夜まで職員を怒りまくったそうです。それでもがまんしていた職員って…。職員を洗脳してたからできたんでしょうけど…。
自伝では昨日まで元気だった利用者がデイの利用後自宅で転倒して亡くなってショックを受けたから今を大事にするような事を理由にしてましたが、異常です。
そういう自分も15年前に今勤めている施設でこんな事ありました。ウチの施設生活エリアがコの字になっており間がスロープになっています。設計ミスで。
そのスロープを車イスの利用者が転げ落ちて頭を強く打って寝たきりになってしまいました。頭血まみれで…。
普段は車イス乗るときコールで職員呼ぶんですがたまに呼ばずに乗ってしまうこともあり皆注意してたんですが…その時は僕以外の職員オムツ交換入っていて僕はお茶配りと整容でかく部屋回っていました。ウチの施設食堂ないので…。
で件の利用者が転げ落ちたのを発見してすぐ看護師よんで対処したのは僕でした。数日後、相談員(今の施設長)にスロープに来るよう呼ばれました。行ったら車椅子に乗せられて突き飛ばされました。すぐ押さえてくれたんですが怖かったです。転倒しそうになりましたから。
その後しれっと言われました。怪我した利用者さんの恐怖がわかったでしょって…。僕がその利用者を怪我させたわけでないのに…。出戻った今でも忘れていません…。なんかずれています。
そういえば施設長先日利用者の食事介助していて薬を無理やり突っ込んで誤嚥させたんですよね、それでその利用者熱出しちゃって…。それについてはどう釈明するんですかねって皆言ってました。
>かずさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
自分や事業所の名誉や名声のために事故ゼロを謳うやり方は賛同できませんね。
仮に達成できたとしても、その裏で泣いている職員がいるのだとすれば、そんな事業所の存在自体が事故です。
高齢者体験ができるキットや職員にオムツをつけさせて排尿を迫るような研修を知っていますが、そういうのは根本的なものがズレていると感じています。
ましてや、責任のない人を車椅子に乗せてわざと突き飛ばすなんて…サイコパスですね…。
笑う介護士は教祖様とも呼ばれてましたから。笑う介護士が施設長していたデイ、またはプロデュースした施設で働いていた職員はある意味カルト宗教の信者みたいになっていて笑う介護士は職員に信奉されて悦になってましたから。実際僕も洗脳されていた時期がありまして笑う介護士がプロデュースしていた施設でセミナーあって参加したんですが参加して違和感感じて
ヤバいと思い洗脳とけました。今は関わりとかないですね。キラキラ職員より危険な介護士ですから。
ウチの施設長介護職員を人として見てないですから。やられた時労基に訴えたら確実に処分されていたと思います。ただ、訴えたら施設が混乱すると思って止めました。
施設長こんな事言って職員怒らせました。職員少ない日休みの人出勤できたら出勤してください『休みでもどうせコロナで外出できないでしょう』って。手当て出ますかって聞いたら手当てだしたら賞与が減りますだって…。皆、誰が出勤するか!って怒ってました。
サイコパス通り越して大バカです。ウチの施設長。
そのうち皆やめてきますね…。
>かずさん
返信ありがとうございます^^
あまり詳しくは知りませんが、教祖様は結局自滅してしまったようですね。
人の気持ちがわからない人が人の上に立っていたり、福祉の仕事をしているのですから闇深い世界ですね。
現在は、徘徊しまくる歩行不安定な認知症高齢者をいきなり介護施設に押し付ける→スタッフが大変な思いをして見守りなどするも現場の消耗ハンパなし→結局見守りしきれず利用者が転倒して骨折し病院に搬送→そのまま拘束され薬漬けにされて肺炎で死亡、ってパターンが多いと思います。
歩行不安定なのに一日中徘徊しまくってる人はいきなり介護施設に押し付けるのではなく、精神科などで薬物療法や行動療法をしてある程度落ち着いてから、介護サービスを利用した方がいいと思いますね。順序が逆なんですよね。
たいていは、医療的な介入はほとんどなく、「見守りで何とかしてください」だの「かかわり方で何とかしてください」だの言われますけど。ww
だって一日中奇声を大音量で上げてる人とか、暴力暴言がすごい人とか、セクハラがすごい人とか、不潔行為がすごい人とか、その状態からより普通に生活できるように近づけるのは医療の役割だと思うし、何もしないんなら精神科医とかただの役立たずだと思う。
薬の種類や量を調整して、毎日服薬してある程度穏やかに生活できるようになったら、病院から生活の場に帰って生活して、毎月モニタリングして、もし異常があれば通院してまた医師に相談しながら調整すればいい。
精神疾患のある高齢者を「認知症」とひとくくりにして、介護サービスにおしつける体質が、すべての元凶だと思われます。
介護施設を「認知症高齢者が事故を起こして病院に運ぶための前段階」とするのではなく、そこで穏やかに暮らしていける生活の場にしていただきたいですよね。
>デイちゃんさん
コメントありがとうございます^^
確かに何でもかんでも介護現場に押しつけすぎですね。
問題行動が軽快したり症状が治まった方が本人にとっても良いでしょうし、介護や福祉以前に治療が必要な案件は往々にしてありますね。
高次脳機能障害で抑制障害の人など、一日中金切り声上げてる人とか、突然怒鳴りだす人とか、いきなりスタッフにグーパンチしたり腕にかみついたりする人いるんだけど、それは適切な服薬が必要不可欠なわけでしょ?本人にとってもまわりにとっても。
なのに家族が「本人の人格が変わるから薬は飲ましたくない」とか言い出して、病院も「じゃあ治療はないです」となって、あとは介護施設に丸投げ。
違うよね~。医師が家族に丁寧に説明して、医療の介入をしなきゃダメでしょ。「ご本人様も一日中大声を出しているのはつらいから。血圧が上がりすぎたりして体にも悪いから。殴ったりしたら自分が骨折とかケガするかもしれないから。服薬は必要なんですよ。薬の種類や量の検討は継続的にしていきますので。」とかなんとか。医師じゃない私でもわかるよ。ww
「高齢者なんてどうせ死ぬだけでしょ?」とか適当に扱わないで、みんな年取って認知症になるかもしれないんだから、もうちょっとちゃんとしてほしいよね。
>デイちゃんさん
返信ありがとうございます^^
そうですね、医療の介入が必要なケースがあっても、そういうパターンになることがありますね。
押し付け合いのようにしか見えませんね。