最近、再び悲しい在宅介護における殺人事件の報道がありました。
兵庫県神戸市で在宅介護をしていた、幼稚園教諭だった孫(22)が同居していた認知症の祖母(当時90)の口にタオルを押し込み窒息死させるという事件です。
詳しくは、下記報道をご参照下さい。
★「限界だった」たった1人の介護の果て なぜ22歳の孫は祖母を手にかけたのか(リンク先:毎日新聞)
この報道を読んでオーバーラップしてしまったのが、約14年前に起こった京都介護殺人事件です。
「在宅介護であること」「介護者である身内が同居の被介護者に手をかけてしまったこと」「手を掛けた介護者は追い詰められた末の行動であったこと」「執行猶予付きの判決となったこと」が共通しています。
詳しくは下記記事をチェックしてみて下さい。
今回の介護事件での裁判では、孫である被告の「責任能力」が争点であったことから、要は「本当に正常な判断ができなくなるほど女性(孫)は追い詰められていたのか?」ということに焦点が当てられていました。
ですから、女性の
- 日々の生活や精神状態
- 過去の生い立ち
- 過去の精神的な病気
などが取り上げられていますが、神戸地裁の裁判長は「適応障害そのものが、犯行に影響を与えていない」としながらも、「介護による睡眠不足や仕事のストレスで心身ともに疲弊し、強く非難できない」と結論づけ、懲役3年執行猶予5年(求刑は懲役4年)を言い渡しています。
これは、過去の生い立ちや病気がどうであれ、また、身内の被介護者のことが大好きであろうとそうでなかろうと、「介護現場では誰にでも起こりうる状況である」ということには留意が必要です。
介護者であった孫がなぜ大好きだった被介護者であった祖母に手をかけてしまったのか、状況を読み取る限り主に以下の点が考えられます。
- HELPの声を上げられなかった
- 親族に介護を押し付けられた
- HELPの声を上げる場所がわからなかった
これは前述した14年前の京都介護殺人事件と類似の原因であると言えるため、乱暴な言い方をすると「在宅介護のフォロー体制は14年前と何ら変わっていない」とも言い換えられます。
以下で詳しく考察していきたいと思います。
【在宅介護殺人事件考察】22歳の孫はなぜ大好きだった祖母に手をかけたのか
冒頭でも触れた約14年前の「京都介護殺人事件」ですが、その判決の中で裁判官は以下のように判示していました。
「裁かれているのは被告だけではない。介護制度や生活保護のあり方も問われている」
つまり、こういった類の介護事件は被告だけの問題ではなく、「介護制度や生活保護などの社会保障のあり方もちゃんとしていかなければ同じようなことが繰り返されるよ」と深読みすることができます。
この事件や裁判を教訓に介護制度や社会保障が大きく変化したかというとそうでもありません。
いや確かに徐々には変わってきているのでしょうが、肝心かなめの点が変わっていないため、「在宅介護事件」が発生してしまっているのではないでしょうか。
もうそこには、「被介護者となる家族が大好き」は関係ないのです。
もっと言えば「大好きな肉親だから自分や家族の手で介護をしなければならないという使命感」こそが、在宅介護事件を発生させる温床とも言えます。
①HELPの声を上げられなかった
22歳の孫は、祖母を介護する必要に迫られた時にHELP(ヘルプ)の声が上げられなかったことが、事件が発生してしまった1つの原因であると考えられます。
とは言え、親族に助けを求めた上であっけなく断られ押し付けられたという経緯がありますので、全く声を上げなかったわけではありません。
しかし、それ以上はHELPの声を上げず自分一人で全てを抱え込んでしまった結果が、このような事件へ発展してしまったのですから、「もっと他にも助けを求めることが必要だった」ということになります。
残念ながら、現在の制度では「助けを求めない人は救わない(救えない)」という仕組みになっていますので、何事でもそうですが、「まずは声を上げる」「助けを求める」ということがとても大切です。
②親族に介護を押し付けられた
22歳の孫は親族に助けを求めましたが、結局は自分一人で全てを抱え込むことになってしまったことが、事件が発生してしまった1つの原因であると考えられます。
親族であっても時と場合によっては非常にシビアであることは肝に銘じておく必要があるでしょう。
もちろん、親族にもそれぞれ生活がありますから一方的に責めることはできません。
しかし、22歳の女性が一人で背負い込むにはあまりにも負担が大きかったのは間違いありませんし、親族からも介護保険制度のアドバイスもなかったとすれば、やはり制度そのもののあり方が問われているのではないでしょうか。
③HELPの声を上げる場所がわからなかった
22歳の孫やその親族、はたまた14年前の京都介護事件も含め、在宅介護を抱え込んでしまった場合にHELPの声を上げる場所がわからない(知らない)ということが、事件が発生してしまう大きな原因であると考えられます。
前述してきたように、まずは親族間で相談したり助けを求めるのでしょうが、「それでもダメだった場合はどうすればいいのか」ということがわからずに介護事件に発展してしまったとすれば、それは介護制度や社会保障制度のあり方にも問題があります。
そもそも、現状で自分が在宅介護をしなければならなくなった場合に、まずはどこに相談すればいいのか知っている人は少ないのではないでしょうか。
過去記事でも触れましたが、もしも自分が在宅介護をすることになった場合、「まずは地域包括支援センターに相談」しましょう。
もしも、今回の事件で22歳の孫が地域包括支援センターに相談をしていれば、このような事件にはならなかったのではないでしょうか。
それは、今までの在宅介護事件然りです。
この、まずはどこに相談すべきかという「周知」が、一昔前と全くと言っていいほど変わっていない(出来ていない)ことが大きな問題なのです。
周知がされていないことで介護制度まで辿り着けず介護事件が発生してしまうという負の連鎖が、大好きだった祖母にさえ手をかけてしまう原因となることはこのケースに限らず誰にでも起こり得ることであることは改めて警鐘を鳴らしておきたいと思います。
最後に
今回は、兵庫県神戸市で発生した在宅介護殺人事件について考察しました。
まとめると、
- 在宅介護に困窮し事件に発展してしまうことは誰にでも起こり得る
- HELPの声を上げないと制度からも見放される
- まずは地域包括支援センターへ相談!
- 一昔前と同じような原因で介護事件が発生している(制度等のあり方が変わっていない)
ということになります。
そして、大好きな祖母であっても母であっても(もちん、祖父や父であっても)介護事件が発生する原因が存在している以上、今後も同じような事件が発生する可能性が危惧されるところです。




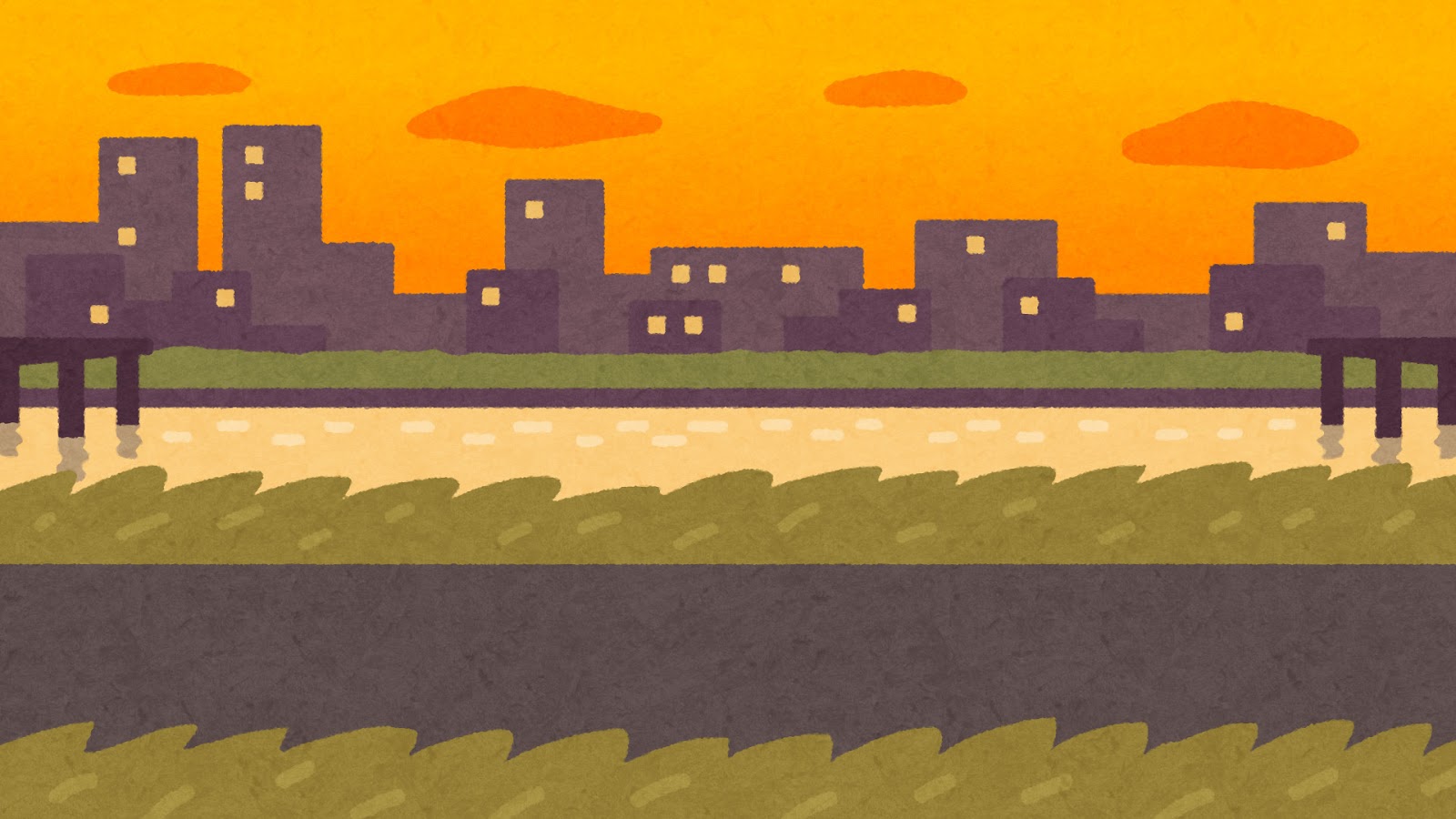


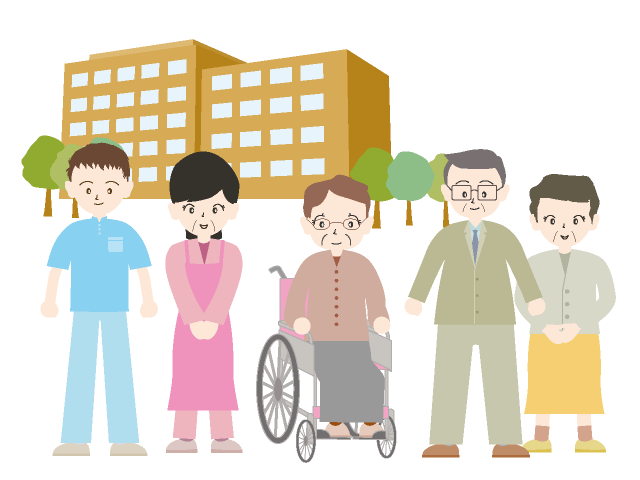

コメント
そう言っていただきありがたいです。
両親に何かあったら自分と妻が動く事になりますが(弟はいますが遠方なので)色々調べて相談して祖母にしてあげれなかったぶん悔いのないようやっていきたいです。ただ、仕事においても家庭においても人を見るというのは大変で綺麗事ではすまない事もありますのでその点は心してやっていこうと思っています。
話変わりますが、とうとうウチの施設退職者続出してきました。新しい施設の面接受けるのに迷いはなくなりました。次の火曜日ですが頑張ります。
>かずさん
そうですよね、介護は綺麗ごとでは済まないことが多々あるでしょうね。
連鎖退職って実際ありますね。
1人が辞めると次々と辞めたり、一斉に複数人が辞めたり…。
面接頑張ってきてください^^
この事件の内情について、各所では(介護から目をそらした)同情が多い印象です。しかし、ゴシップだとは思う記事を見かけました。
蛙の子が蛙なら子を見れが親がわかるみたいな話で、この孫は鷹なのかはわかりませんが、その親たちの性格や態度が非難されているようにその故祖母もまた彼らの親当然に性格や孫の扱いがぞんざいだったとかなんとかと言う話を見かけました。
だから何だそれでも殺人とは話は別だとは私も思いますが、少なくとも日本では法律で殺人が広義で悪いとされているだけですからね。それに勝るものがあれば誰だって犯せるって話なだけで。
介護保険はコロコロ変わるという話なのでまた変わっているかもしれませんが、私が初めて勤めた介護施設に夫婦ともにそのゴシップのような老人が入所していました。時代が時代なのとちょっと特殊な特養だったので認知症はない老夫婦でしたが、まぁそれを好む職員はいなかったと思います。かえって扱いやすいという職員も割といましたが。
私は関わったことはありませんがその夫婦の後見人はその子供とのことでしたが、先輩職員曰く親からは信じられないくらいの良い人らしかったです。しかし、そんな親だから幼いころから入所までの待遇が悪いせいか憎まれていたようで、なるべく関わりたくないと職員や事務所に漏らしていたようです。たしか、亡くなったときもなるべく関わらずに葬儀ができるような段取りでお願いされたらしいです。
ここら辺がよくわからないですが、引き取りには来ないで遺体だけ直送してほしいみたいな話で、これは施設によるサービスの違いなのか、2020現在ではどこもできないのかはわかりませんが。そして、そのように対応したようです。
私が知っている例のように件の孫娘が仮に蛙ではなかったとして、実際にそれでも好きだったのか、マスコミによる脚色なのか。ゴシップが所詮ゴシップで作り話なのか。
もっとも、認知症は全てを壊しますから、元良い人はある意味での極悪人になってしまうし、元最低な人間はそれに輪をかけることの方が基本ですからね。
ホントに安楽死なり尊厳死なりに目を背けるなら、時代ドラマじゃないですが医者と懇ろになってタダシイシボウシンダンショ?を書いてくれる良い医者を作らないとみんな破綻してしまいます。
>めど立てたい人さん
コメントありがとうございます^^
まぁ家庭環境や過去の生い立ちが全くの無関係ではないにしても、誰しも大なり小なり色々あるでしょうからゴシップは後付けでしかないような気がします。
どの施設でもお亡くなりになった後は焼場に行く流れは変わりませんから、そこに家族が関わるか関わらないかは死亡診断書などの書類や直送の手配さえ問題が無ければ可能な話だと思います。
安楽死や尊厳死が可能だとしても、そこに本人の意思や希望がない場合(認知症等により)は判断ができない又は困難でしょうね。
母方の祖母を母がみてました。叔父がみれないので。胸椎を骨折して入院して退院したのですがしばらくは誰かに見てもらわなくてはいけないとの事でした。当時ディの相談員してた僕に母が相談してきました。介護サービスが必要との事で。なので社協でヘルパー上がりの一番いいケアマネさんに祖母をお願いしたら快諾してもらい、色々手配してくれて母もだいぶ助かってました。母方の祖母は認知症はありましたが問題はなく普通でしたので。最後は近所の特養に入所して
老衰で大往生でした。親身になって色々相談に乗ってくれたケアマネさんには今でも感謝してます。ただ、後悔があるとすれば孫の中で一番なついていた僕が祖母が外泊で僕の家に来たときあまり話しなかった事です。怖かったけど優しかった祖母が変わっていくのを見るのが辛くてそっけない態度を取ってしまって…。ホント後悔してます。
なんかすいません。自分の話ばかりになって。ブログの記事みたら急に祖母を思い出してしまい…。
>かずさん
返信ありがとうございます^^
担当ケアマネで対応や判断が変わってくることがありますから良いケアマネさんで良かったですね。
不義理をした(ような気になる)後悔や胸に何かがつっかえたようなモヤモヤ感は誰でも経験することではないかと思います。
それが「故人を偲ぶ」ということにも繋がるのではないでしょうか。
自分の周りにも親族兄弟がやらないから親の介護を自分がしてる人がいます。
一人は職場の同僚で休みはほとんど両親の通院の付き添いで夜勤の入りの日でも両親の通販の付き添いしてから来ることもあります。
知り合いのケアマネは仕事終わってから独り暮らししてる母親の様子見と戸締まりをしに仕事の後実家に寄ってました。いよいよ母親が要介護状態になったので介護申請行い母親の面倒見ながら勤め先を辞め実家の物置小屋を改装して独立して一人でケアマネやっていく予定でしたが直前になりいきなり兄弟から反対され
独立もパーになり自分の中の姉が母親を見ることになりました。「今まで俺に見させておいて今頃なんだよ」と言ってました。その人その後また別の事業所で働いてますがなんか元気がなく心配です。
ホント身内の介護を押し付けられるのって大変です。今回の記事見て改めておもいました。在宅介護殺人に関して『ロスト・ケア』って小説がありますがその小説が現実になりそうな世の中になりそうで怖いです。
>かずさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
身内での押し付け合いは昔からあるのでしょうね。
「身内で介護をするのが当然」「施設から在宅へ」などという思い込みや刷り込みを解放して、「身内に介護が必要になったら躊躇なく施設を利用する」という風潮になればいいと思っています。
もちろん、「本人の意思」や「財源や施設のキャパシティの問題」などもあるでしょうが、高齢者を介護するために現役世代や若者が倒れていく世の中では本末転倒ですよね。
また、在宅介護での虐待や事件が頻発する温床にもなるでしょうし、身内同士の押し付け合いで不仲になったりもしますからね。
そのためにも、介護施設のキャパと介護職員の人材確保、処遇改善が急務ですね。