介護職員として働いていて、「自分は何歳まで介護職員として働き続けることができるのだろう」と考えたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。
私もその一人です。
制度や社内規程などの体制的なことで言えば「自分が働き続ける限り何歳まででも働ける」ということにはなりますが、そうではなくて「自分自身が何歳まで持つのか」という不安の方が大きいのが現実です。
今後、介護職員も高齢化していくでしょうから、働ける環境があるのはありがたいようにも見えますが、本当にそれが手放しで喜べるかと言われればそうでもありません。
今回は、「介護職員として何歳まで働き続けることができるのか」ということについて記事を書きたいと思います。
介護職員として何歳まで働き続けることができるのか
個人個人で寿命も違えば健康状態も違ってくるため、「何歳まで」というライン引きをするのは適切ではないかもしれません。
また、「働けるうちは働き続けたい」という人もいれば「老後の見通しさえ立てば早々にリタイアしたい」という考え方の人もいることでしょう。
そういったことも踏まえながら考えていきたいと思います。
定年後も嘱託職員として働ける
多くの介護事業所では定年があり、その年齢は「60歳~65歳の間のいずれか」となっているのではないでしょうか。
この年齢も「少し前までは60歳で定年だったのに、現在は65歳が定年となっている」という形で段階的に上がってきている事業所もあります。
また、定年となった後も、再雇用という形で「嘱託などの非正規職員」として働き続けることが可能な事業所も多いようです。
そうなると、「自分の体が元気なうちは何歳でも働ける」という体制や環境があることになります。
腰痛の悪化など健康状態が心配
介護職員の代表的な職業病が腰痛ですから、仕事を続ければ続けるほど腰痛の悪化が心配になります。
今のところ軽症だったり致命的ではないにしても、「あと数十年も持つだろうか」という不安は払拭しがたいものがあります。
腰痛だけでなく、自分の精神状態や他の持病などの健康状態が悪化すれば「介護職員を続けたくても続けられない」ということになってしまいます。
ノーリフティングケアもなかなか浸透していきませんし、仮に今後導入されることになってもひとたび悪化してしまった致命的な腰痛は元には戻りません。
周りにいる高齢職員をチェック
今、自分の周りにいる高齢の職員は、ひとつの「自分の将来を映す鏡」と言えます。
自分が高齢になった際のモデルケースとして、自分の将来を重ねて見ることができるからです。
自分の周りを見渡してみると、50代60代の職員は正職員として普通に働いていますし、70代の職員も嘱託などの非正規職員として何名かいます。
但し、70代以上となるとその絶対数は多くありませんし、定年前に辞めていった人も結構います。
つまり、「健康状態が良好で定年後もバリバリ働ける人でなければ続けていくのは難しい」という当たり前の結論になりますが、もっと言えば「致命的な腰痛や持病を持っている高齢職員は辞めていってしまった」ということがわかります。
やはり、介護職員を長く続けていけるかどうかは、「腰痛や健康状態次第で大きく分かれる」ということになります。
しかし、自分の将来がどっちに転ぶかがわからないため不安があるわけです。
どんなに気をつけていても、意図せぬキッカケで発生することもあります。
そうなれば、「定年前にリタイアせざるを得ない」ということも十分に考えられます。
そもそも定年後はゆっくりしたい
「歳を取っても元気なうちは働きたい」という考え方の人が多いのかもしれませんが、個人的には「定年後はゆっくりしたい」という気持ちがあります。
「何歳になっても働ける環境」よりも「定年になったら働かなくても生活ができる環境」の方が何倍もありがたいと感じます。
しかし、年金もアテにならない時代ですし、急速に「自己責任論」の風が強まってきている社会情勢がありますので、そうも言っていられないのが現状です。
今後、どっちに転ぶにしても「腰痛などの健康状態で介護職員としての寿命が左右される」ということになります。
最後に
今回は、介護職員として何歳まで働き続けることができるのかということについて記事を書きました。
環境的には、何歳になっても介護職員を続けていくことが可能ですが、個々人の健康状態によってその年齢は変わってくることになります。
腰痛リスクを抱えながら働く毎日の中では自分の将来の不安も大きくなってしまいます。
介護職員を続けていくにしても、そうではないにしても、腰痛や健康管理には十分注意をしていきたいところです。




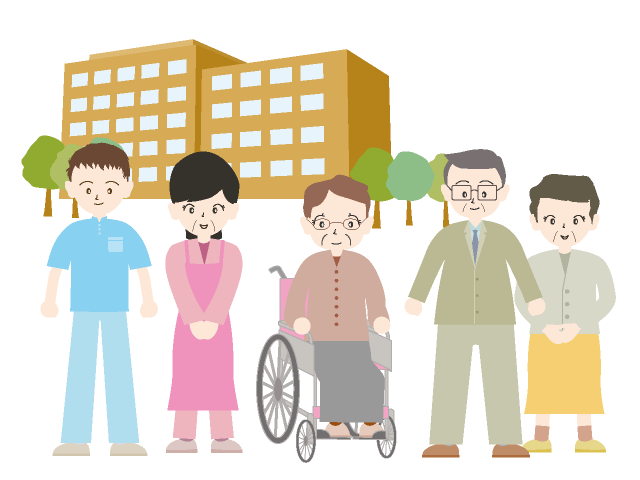


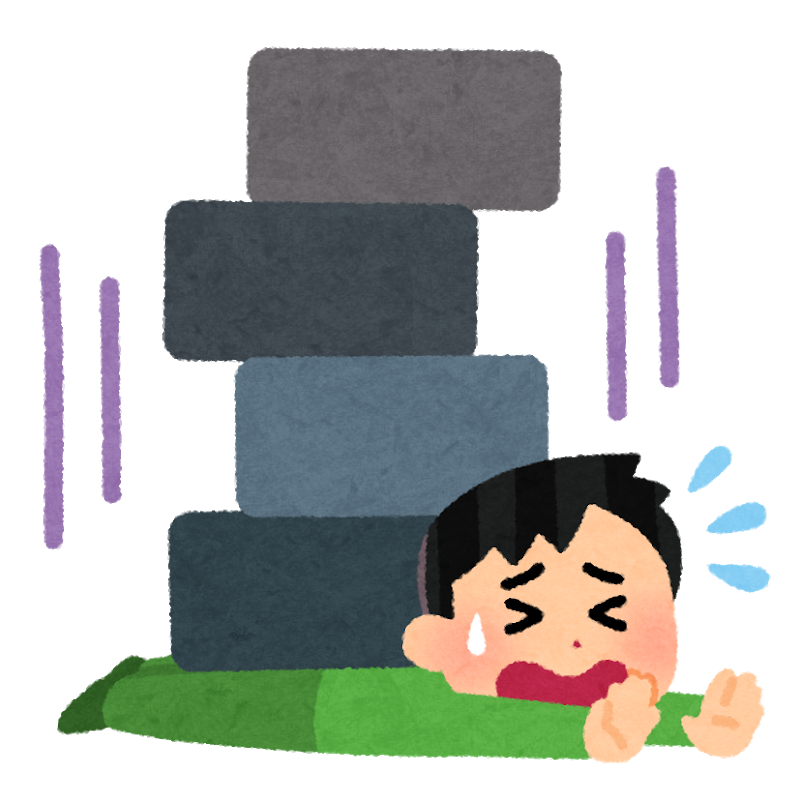

コメント
今の自分の職場の状況でしたら今の職場で長く働くのは無理かなと思っています。職員募集の広告だして来月から1人来るんですが、72歳の男性で経験7年介護福祉士の資格もあるんですが続くかどうか?
旧式のベッドで入所者のほとんどが寝たきりてオムツ交換。旧式なんで高さ調節できなくて皆腰痛めています。機械浴の入浴介助毎日で皆疲れてストレスMAXです。ケアマネも看護師ともめて辞めました。女性の職員間で年末からもめ事も起きています。すべては人手不足が元凶です。施設長は相変わらずとんちんかんですし。今は我慢できる状況ですが…。どうなるかわかりません。
社会福祉協議会に勤めている知り合いからボランティアコーディネーター募集していますがどうですか?と言われてますが給料安くて残業ばかりみたいですし、興味はあるのですが…。待遇よくて今の職場すぐ辞めれる状況なら飛びついてましたが…。身体の事を考えたら…。
>かずさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
そうですよね…。
結局はどこも似たり寄ったりというジレンマ…もありますし、先が見えない不安も大きいですね。
介護の仕事は肉体労働だから、年をとると、体力と健康が問題になりますよね。
若い時みたいな過重労働は無理になってくるし。
でも介護の仕事のせいで、健康を害するのは一番困るから。まだできるかな?と思うあたりで、さっと辞めとく方がいいかもしれませんね。
だけど仕事辞めると、辞めたときはせいせいするんですが、やることがなくてすぐに退屈になるんですよね。
年をとると、きょうようときょういく(今日用がある・今日行くところがある)が大事ですからね。
なので年をとっても、短時間の軽作業などで働けるといいんですけど・・・介護の現場でそれがあるかと言うと・・・ないかも。ww
70歳過ぎて運転手してる人もいますが、もしかしたら運転中に脳梗塞などで事故をおこすかもしれませんし。リスクはつきまといますものね。
>デイちゃんさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
サッと辞めたくても収入が必要であれば無理して続けていかなければならない人もいるのでしょうね。
確かに歳を取るとこちらの健康状態で色々なリスクがありますね。
ワンオペ夜勤中に「今もし自分が何かの病気で気を失ったら早番が来るまで自分も利用者も放置されることになるな…」などと考えたりもします。
そうなんですよ。
昨年67歳の看護師が勤務中に「気分が悪い。右に力が入らない。」と言い出したので、「脳梗塞?」と思ってすぐ管理者に報告して救急車よんだら、救急車来た時には回復したんですけど。
複数人で働いてると、誰か気づいて救急車呼んでくれたりはしますけど。
そういう意味では、ユニット型とか少人数で働いてると、「何かあった時気づいてくれる」っていうよさはないですね・・・。
「年とっても、金がないから、しんどいのに働かなきゃいけない」って不幸ですよね。
前デイにいて人格が悪すぎて追い出された準看のバアサンが、訪看にナースがいなくなったからって呼び戻されたんですよ。バアサンを首にした管理者に。ww
私だったら自分を追い出した職場なんか絶対に戻りませんけど、やっぱり金がないから働かなきゃいけないんだね~って感じで。
そのバアサンは、年とってるし仕事できないし準看だから、他は雇ってくれないから、渡りに船だったのかな~って。
でも今訪看がナースが増えて、すでにその準看のバアサンいらない人になってるので、そろそろ首かも。切ない。wwww
>デイちゃんさん
返信ありがとうございます^^
「歳取ってもお金がないからしんどいのに働かなければならない」という状況の人はこれから増えていくのではないでしょうかね。
そしてそれも全て「自己責任」とされる風潮がありますから私自身も危機感を感じていたりします。
こんにちは!galaxy株式会社の山口と申します。
介護職員A様のこちらのブログをぜひ書籍化のご提案させていたたく思いご連絡させていただきました。
問い合わせサイトには2通メール(内容別)をお送りいたしましたが、
念のためこちらにもコメントをお送りしています。
もし先にお送りいたしましたメールをシステム上ご確認が難しいようでしたら、
下記メールアドレスまたはHPよりご連絡ください!
※HPの場合はメールアドレスをいただけますと幸いです!
※お問い合わせの際は、本名でなくても(介護職員A様で)問題ございません。
よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
galaxy株式会社
山口
メール:yamaguchi@galaxyinc.co.jp
HP: http://galaxybooks.jp/
media:https://conetto.net/
TEL:06-4390-4309 FAX:06-4390-4449
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町 1-2-19AXIS西本町セントラルビル 3F
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>galaxy株式会社 山口さま
お問合せ&ご提案ありがとうございます。
ブログの書籍化は今のところ考えておりませんので辞退させて頂きたく思います。
ブログコメントでの返答で失礼しますが、宜しくお取り計らいください。
最近金銭的に働き続けるのは無理かなと感じています。給料上がらないのに、介護保険料の徴収が始まると思うと手取りが今以上に悲惨なことになるのが目に見えているので。
40歳の壁問題ですねぇ…
>アングラーさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
確かに、40歳からの介護保険料の天引き痛いですよね><
誤差とは言えない数千円単位ですからね。
税金の基本は「無いところから取るな、あるところから取れ」だと誰かが言っていましたが、本当に生きづらさや世知辛さを感じますね><