職場の人間関係や労働環境、又は、自分の体調や健康面の理由から「介護職員を辞めたい」「この介護事業所を辞めたい」と思っているものの、「自分が辞めたら残された職員や利用者に迷惑が掛かってしまうかもしれない」という気持ちが強く、なかなか辞意を上司に伝えられないという介護職員も多いのではないでしょうか。
こういう思いを抱いている介護職員は、過去現在でも私の周りにも何人かいましたし、ネット上での書き込みを見ていても何度か見掛けました。
結論から言えば、「あなたであろうと私であろうと、上司であろうと管理者であろうと、1人くらい辞めたところでほぼ無風」です。
ですから、ご自身が辞めたいと思ったのなら、そんなことは心配せずに自分のために安心して辞めればいいのです。
ただ、極度の人員不足の介護事業所であれば、ひょっとしたら1人辞めただけで立ち行かなくなってしまう状況もあるかもしれません。
だからこそ、「辞めにくい」「辞意を言い出しにくい」と思ってしまうこともあるのでしょうが、もし仮にそうだとしても「自分の人生を捧げ、犠牲にしてまで残る必要は全くない」ということにしっかりと目を向けることが大切です。
今回は、「自分が辞めたら残った職員に迷惑が掛かってしまうかもしれない」と思って辞められない介護職員について記事を書きたいと思います。
残された職員が心配で辞められない介護職員の特徴や対処法
残された職員が心配で辞めることができない介護職員は、「自意識過剰」と言って斬って捨てられがちですが、実際は「本気で残された職員や利用者を心配している」という場合が多いように感じています。
どういうことなのか詳しく見ていきたいと思います。
異常に責任感が強い
残された職員などが心配で辞めづらいと思っている介護職員は、「自分が有能だから辞めることで現場が回らなくなるだろうから辞めにくい」ということではなく「自分が辞めたあとのことを考えると心配でいたたまれなくなる」「一緒に働いた仲間を裏切ることになるのではないかという罪悪感」を持っているのが特徴です。
つまり、
- 心配性
- 想像力や感受性が豊か
- 責任感が強い
という性格の人に多い傾向があります。
そういう性格の人は介護職員に向いているのですが、あまりに度が過ぎると逆に自分を苦しめることになりかねません。
何故なら、そういう性格の人は介護現場ではストレスを受けやすくなるからです。
例えば、
- 同僚や上司の理不尽な発言でも真に受けてしまい忘れられない
- 利用者に深く感情移入してしまい自分を見失う
- 責任感が強く自分から自己犠牲を払ってしまう
ということになり、結局は長く続けられないという結果を招くこともあります。
「介護職員に向いている人と続けられる人は全くの別物」と言えるのではないでしょうか。
実は他人の目が異常に気になっている
前述した性格の持ち主は、実は他人の目が異常に気になっている場合もあります。
つまり、
- 自分が他人にどう思われるか(思われているか)がとても気になる
- 周りの人に悪い印象を与えたくない
- 常に良い子でいたい
という気持ちが強いのです。
ですから、上司などに辞意を伝えた時に上司から
「今辞められたら残された職員や利用者に迷惑が掛かる」
などと言われれば、それを真に受けてしまい
「自分のせいで他人に迷惑を掛けたくない」
「自分が悪者になることは避けたい」
という気持ちが強く働き、なかなか言い出せず辞めることができない悪循環に陥っていくのです。
心配で辞めづらい介護職員の結末
経験上、残された職員などが心配で辞めづらいという介護職員が最終的にどうなったかと言うと、
- 極限まで耐えて限界ギリギリで退職
- 有給などの自分の権利を放棄して罪悪感を薄めて退職
- 休職をしながら働き続けている
というパターンになります。
極限まで耐えて限界ギリギリで退職
このパターンは、うつ状態になったり腰痛が悪化するなど、身も心もボロボロになって辞めていった人です。
意を決して辞意を伝えても、そこからまた退職時期を引き延ばされたりするのですから堪りません。
有給などの自分の権利を放棄して罪悪感を薄めて退職
自分の退職と引き換えに、自ら有給消化の放棄をするなどして罪悪感を薄めて何かとか退職まで持っていった介護職員もいます。
しかし、そもそも退職することは悪いことではありませんし、自分の権利を自ら放棄しなければ辞めることができない状態は明らかにおかしいのですが、「苦肉の策という名の闇」と言えます。
休職を繰り返しながら働き続けている
時々、急に長期休暇(休職)をする介護職員が出現します。
休職の理由を聞くと「精神上の問題」というパターンが過去に何度かありました。
1か月くらい休み、また復帰するのですが、その先には結局退職という結末が待っている現実が往々にしてありました。
心配で辞めづらい介護職員はどうすればいいのか
残された職員などが心配で辞めることができない介護職員に、「そんなことは心配しなくてもいいから自分のことを考えて辞めればいい」と言ったところで「でも…」「そうは言っても…」となってしまい、結局は何も変わらないことになってしまいます。
ですから、忘れてはいけないことを3つご紹介しておきますが、「最終的にどうするかは自分が判断するしかない」という結論になります。
- 人員不足は介護職員の責任ではない
- 他人軸を自分に置き換える
- 自分一人で抱え込まない
1.人員不足は介護職員の責任ではない
これは大前提なのですが、介護業界や職場の人員不足は介護職員の責任ではありません。
人員不足を解消したり対策をしていかなければならないのは、
- 国
- 介護業界
- 職能団体
- 経営者
- 管理者
などの人達です。
それさえも棚に上げられて、人員不足さえも介護職員の責任であるかのような考え方や発言は明らかにおかしいと言えます。
「辞めたら益々人員不足になる」「辞められたら迷惑」ということを言うのではなく、「どうしたら介護職員が辞めていかないような制度や環境をつくれるか」ということが先決です。
人員不足を解消するという責任が果たせていない人が、介護職員に責任を押し付けたり問うたりするから、益々人員不足に拍車が掛かる悪循環に陥っているのです。
つまり「身から出た錆」「お門違い」「責任転嫁」なのです。
そもそも、人員不足さえ解消できていれば「辞めたい」という気持ちにもならなかった可能性だってあり得ます。
人員不足は介護職員の責任ではないのですから、「残された職員などの心配をしたり責任を感じる必要はない」ということは覚えておきましょう。
2.他人軸を自分に置き換える
「残された職員などが心配で辞めれない」「人の目が気になる」という介護職員は、完全に他人軸になってしまっています。
「自分軸が最高で他人軸はダメ」という極端なものではなく、全力で他人に軸を置いてしまっている一部分を自分に置き換えて考えてみましょう。
例えば、
- 自分の人生は誰のためのものなのか
- 自分は誰のために働いているのか
- 自分は何を(どこを)目指しているのか
ということを見つめ直してみる良い機会です。
忙殺されて見失ってしまいがちな「自分は何者なのか」ということを自己覚知してみると自ずと答えが出てくるのではないでしょうか。
3.自分一人で抱え込まない
自分一人で考えると思い詰めてしまいますし、画一的な考え方になってしまいがちです。
誰かに聞いてもらうだけでスッキリする場合もありますし、違う角度の良いアンサーが見つかる可能性もあります。
但し、相談する人は選びましょう。
本当に自分のことを思って考えてくれる人を選定することが大切です。
また、相談相手は個人だけでなく官公庁や公的機関なども多数ありますので視野に入れておきましょう。
例えば、
- 労働基準監督署
- ハローワーク
- 法テラス
などです。
自分一人で抱え込まず、誰かに相談すれば最適な方法が見つかる可能性があるということも覚えておきましょう。
最後に
今回は、「自分が辞めたら残った職員に迷惑が掛かってしまうかもしれない」と思って辞められない介護職員について記事を書きました。
結論は、「そんな心配などせずに自分のために辞めましょう」ということになりますが、そう簡単にいかないから悩まれている人もいらっしゃることでしょう。
この記事の内容が少しでもご参考になれば幸いです。







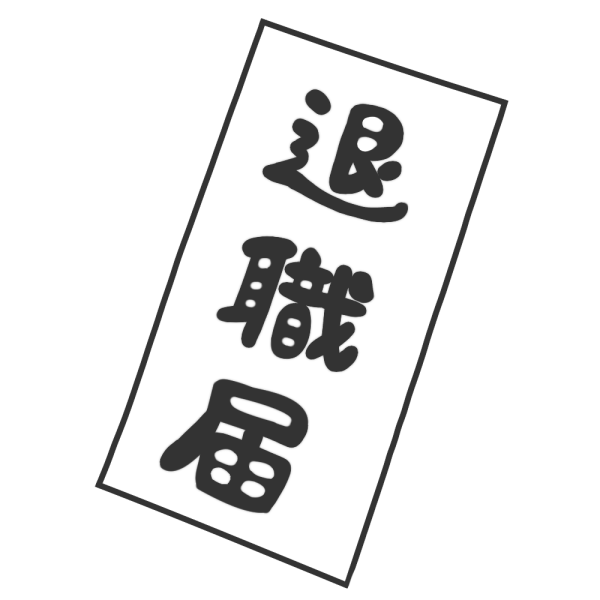









コメント
「あとのことを考えるとやめられないんですよね~」って言う奴って、「そんなに自分の存在大きいと思ってるの?そんなに自分の存在を知らしめたいの?」って感じですよね。
「あんたなんかちっぽけだよ」「あんたなんかいなくなっても、誰も気にもしないよ」って言ってあげたいですね。ww
「もうやめますけど、自分がいなくなったら仕事が回らなくなるっていうなら、もう少しいますけど」って言った、何にも仕事ができないどう考えても何らかの障害をお持ちのスタッフが昔いました。
その人にはソッコーでやめてもらったみたいですけど。ww
あと「利用者さんのことを考えるとやめられないんですよね~」っていうのも、よく聞くセリフ。
「いやいや、利用者さんみんな認知症なんで、あんたのことなんてすぐ忘れると思うから、やめても大丈夫よ?」「どうせもともと赤の他人でしょ?やめたら全くの無関係になるだけよ」って言ってあげますけど。ww
スタッフが辞めるって言っても、経営者的には「〇〇さん?そんな人いた?」「まあいなくなったら人件費がうくな~」くらいしか思ってないですよ。それで回らなくなっても、「別になんとかなるでしょ」って感じだし。
で、スタッフが少なくなりすぎると、配置基準が満たせないから、利用者も減らさないといけなくなるでしょ。
なので別にスタッフ減ってもいっかな~って思ってます。仕事は楽になるし。
まああこぎにスタッフ減っても利用者減らさないとこもあるけど、悪事は必ずあばかれるしね~。
結局落ち着くところに落ち着くんですよね。ww
>デイちゃんさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
いますね、そういう「辞めるつもりはないのに辞められないアピールが強い人」。
辞める辞める詐欺の亜種ですかね。
悪事はどんどん暴かれて欲しいですね。
やめられないってどういうことなんですか?好きな時にやめるのは労働者の権利ですよね。
「え?いつでもやめられるよ?結局やめたくないんでしょ?誰かにひきとめてもらいたいんでしょ?」とか言ってやりたい。ww
ちなみに私のデイは、「やめようと思うけどやめられない」なんて言うスタッフは一人もいません。
なぜなら、仕事もしないでサボりまくってるカスタッフばかりだから。
あんだけサボってたら、さぞかし楽だろうね~。サボってて給料もらえて極楽。やめる理由なし。むしろ「お願いだからやめて?」って言われる可能性大。ww
そうそう、一日中座ってサボってた常勤妊婦、訪問のS責になるそうです。訪問は個人商店なので、もうこれでサボれないね~。
何年間もサボり続けたけど、とうとう年貢の納め時がきたようです。アッハッハ。
>デイちゃんさん
返信ありがとうございます^^
本気で辞めようと思えば辞めれると思いますね。
ただ、実際に辞めたいのに辞められないという介護職員が存在するのは確かですね~
上司も人を見て対応を変えますからね><
色々闇深い部分です。
今訪問が無軌道な拠点分割してて、新拠点にS責が必ず必要なので、無理やりS責にしてるんですよね。
S責は資格が必要だから、介護福祉士の常勤が施設にいたらソッコー異動させて訪問のS責に。
常勤妊婦はなぜか介護福祉士。すかさず召集令状が来ました~。www
でもS責の仕事なんてできるわけないから、たぶん1か月で終了だと思う。
その次は、デイのサボり相談員が介護福祉士だから、異動することになると思います。www
施設などだと、どんなに業務分担しようとサボりまくる奴がいますが、ケアマネや訪問、福祉用具などは、基本個人商店なので、自分の仕事は自分でするしかないんですよね。で、できないと終了。
サボりまくってる奴らを一掃できそうです。
こいつは春から縁起がいいや。www
>デイちゃんさん
こんばんは~
返信ありがとうございます^^
そうですね~個人商店的な業務は進捗状況や仕事ぶりが明確に出てきますものね~。
意外とちゃんと仕事をするようになるかもですよ(笑)