これは介護職員や介護現場に限らずですが、「指導と注意」「指摘と非難」の違いがわからない人を時々見掛けます。
職場にもいますしTwitterなどのネット上でも「指摘を非難だと捉えてしまっている人」がいます。
共通しているのは「全てをネガティブに受け止めてしまう」ということになりますが、それぞれ意味合いが違うために正しく理解しておかないと、
「パワハラだー!」
「誹謗中傷だー!」
と騒ぎ立てたり自分を正当化する手段として悪用することで「逆パワハラ」にもなりかねません。
今回は、「指導と注意」「指摘と非難」の違いがわからないと全てがパワハラに見えてしまう危険性について記事を書きたいと思います。
「指導と注意」「指摘と非難」の違い
まずは、「指導と注意」「指摘と非難」の違いについて確認していきたいと思います。
これらを混同してしまい、全てごちゃまぜにしてしまっている人もいらっしゃるのではないでしょうか。
自分も含め、正しく理解しておきたいところです。
指導と注意の違い
まずは、指導と注意の違いを確認していきます。
指導とは
指導とは、相手の間違っている所やダメなところを指摘した上で正しい方向へ教え導くことです。
職場であれば、上司が部下へ指導することもあるでしょう。
例えば、
「ここは間違っているから、こういう具合に直してね」
「そのやり方よりも、こっちのやり方をすると上手くいくよ」
などというやりとりが指導になります。
注意とは
注意とは、相手の間違っている所やダメな所を指摘することです。
指導との違いは、「指摘するだけで正しい方向への導きはない」ことです。
例えば、
「ここは間違っているよ」
「それはダメだよ」
などというやりとりが注意になります。
指導よりも不親切な印象ですが、それは決して「怒っている」「非難している」というわけではないのです。
但し、言い方によっては「パワハラ」になってしまう場合があるので配慮が必要でしょう。
指摘と非難の違い
次に、指摘と非難の違いを確認していきたいと思います。
指摘とは
指摘とは、間違いや過失や問題となる箇所などについて具体的に取り上げて指し示すことです。
例えば、
「その内容は実際はこういう現状なので間違っているのではないでしょうか」
などのやりとりが指摘になります。
非常に理に適った建設的なやりとりですが、指摘する側があまりにも高圧的な場合は相手に不快感を与えてしまうこともあるので注意が必要です。
但し、どちらにしても指摘は指摘であり、パワハラや誹謗中傷や非難とは違うのです。
非難とは
非難とは、相手の欠点や間違いや問題となる箇所を責め咎めることです。
責めるのですから、一種の責任追及であり改善を求めることになります。
例えば、
「その考え方は一方的に偏ったものであり、あなたの人格を疑わざるを得ません」
「こんな間違いをするなんて今までどういう教育を受けてきたのですか?」
などのやりとりが非難になります。
非難は非常に攻撃的な内容になりますから、ネガティブな印象を受けたりパワハラだと感じてしまっても致し方がない部分もあります。
違いがわからないと全てがパワハラや誹謗中傷に見えてしまう危険性
「指導と注意」「指摘と非難」の違いについて確認してきましたが、これらの違いを理解しないまま全てをネガティブなものとして受け止めてしまっている人もいるのではないでしょうか。
例えば、職場であればすぐに「パワハラだー」と言う人や、ネット上であれば「アンチガー」「誹謗中傷ガー」と言ってしまう人です。
冷静に言われていることを理解しようとしてみれば、実はそれらは「指導」「指摘」である場合があるのではないでしょうか。
もちろん、言う側も言い方には配慮が必要ですが、言われた側も全てをネガティブなものとして受け止めてしまうことは非常に危険です。
何故、危険なのかを以下で詳しく見ていきたいと思います。
ただの自分勝手
指導も指摘も自分への非難だと受け止めてしまう人は、自己満足だけの世界に生きています。
言い換えれば「自分さえ良ければそれでいい」のです。
もちろん、誰しも自分が一番大切ですが、職場であったりコミュニケーションが必要な場で自分の我ばかりを貫き通してしまうのは社会性や社交性に欠けます。
「自分軸」という名の「自分勝手」になってしまうため危険なのです。
自分を正当化する逆パワハラ
全ての指導や指摘をパワハラや誹謗中傷だと言ってしまうのは、自分を正当化するための笠であり実は逆パワハラでもあります。
何故なら、それを言ってしまえば相手は何も言えなくなってしまうからです。
もちろん、本当の意味でのパワハラや誹謗中傷であれば、逃げたり戦っていくことも必要ですが、指導や指摘さえも相手に言わせないというスタンスは逆パワハラになってしまう危険性があります。
ですから、指導と注意、指摘と非難の違いを理解し、適切な対応をしていかなければ自分も周りも不幸になってしまうため危険なのです。
成長しない
指導も注意も指摘も全て自分への非難であり攻撃に見えてしまう人は成長しません。
何故なら、自分を省みたり間違いを訂正したり過失を認めることを放棄してしまっているからです。
唯一無二の唯我独尊も良いですが、「井の中の蛙」「猿山の大将」状態になってしまいます。
そして、外部からの指導や指摘を排除することで、自分の置かれている状態を冷静に判断することもできず気づくこともないため危険なのです。
最後に
今回は、「指導と注意」「指摘と非難」の違いがわからないと全てがパワハラに見えてしまう危険性について記事を書きました。
自分への戒めも込めて、それぞれの違いや意味をしっかりと理解し冷静に判断していきたいところです。
もちろん、伝える側が言い方にも気をつけなければなりませんが、受け取り手の教養や人間性や柔軟さも非常に大切になってくるのです。
自分が「わからず屋になっていないか」というポイントは意識しておきたいところです。



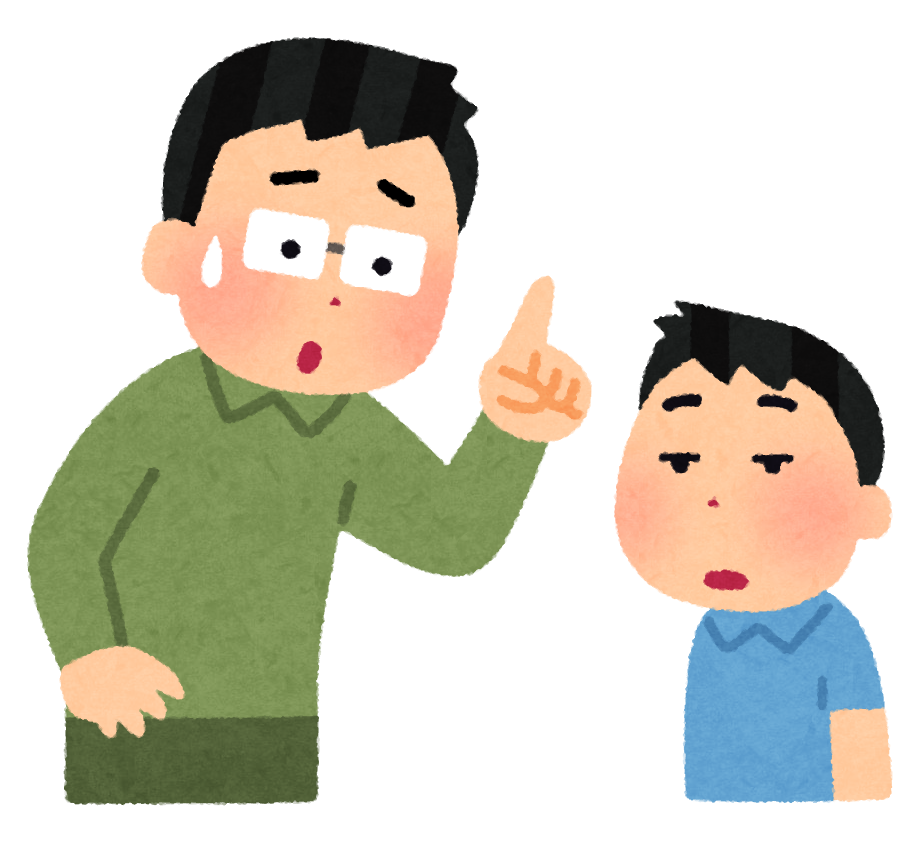






コメント
んで?そんな自分勝手で自分軸で育った人の改善方法はないの?
>匿名さん
コメントありがとうございます。
他人を変えるということは難しいですからね。
確定的な改善方法があるのだとすれば苦労はしないでしょうね。
それが一番大切ですね。心してやっていきます。
>かずさん
陰ながら応援しています^^
会社の環境はホント大切だと思いますね。ウチの施設は施設長は自己保身しか考えてないし、介護主任は自分の事しか考えてないし、相談員は自分の思いを押し付けて現場の気持ち無視、現場の介護職員守る意思が見られません。これではみんなカリカリして言い方がキツくなるのは当たり前ですね。自分はこの仕事やってて長いですが教えたり教えられたりでいい思い嫌な思いもしてるのでそれを思い出して今は慎重に言葉選んで新人には教えるようにしてます。
しかし、ホントみんなが普通に働ける環境作っていかないと大変ですね。
ウチの施設は上がマトモじゃないから多分無理ですので自分が気を付けるようにしていくしかないですね。
>かずさん
どこも似たり寄ったりの状況があるのかもしれませんが、自分を見失わないようにしていきたいですね。
先日ですがウチの介護副主任が新人の指導に対して注意を受けました。
正直その人キツイけど人を苛めたりする人じゃないです。多少の嫌みはいいますが。いい方はキツイけどポイントを一言ではっきり分かりやすく言ってくれるんでそれで仕事覚えた事も何度もあります。ただキンキン声でいい方がヒステリックに聞こえる時があります。自分でも自覚してるみたいですがつい言い方がそうなってしまうみたいです。で、派遣社員を指導した時教えた事全然守らなくてつい大声出してしまい上司に注意されてしまったそうです。施設長と相談員と介護主任に応接室によばれ3対1で注意されたそうです。施設長もその職員に一人で注意できないから介護主任と相談員を呼んだらしいです。なんか陰険だな、施設長や介護主任はしみじみ一対一で注意できないのかよ、ホント卑怯っていうか無能だなと思いました。
>かずさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
言い方は非常に大切ですが、意識しないと素や思いがけないヒステリックな部分が出てしまうこともありますね。
個人的にはそれは環境がそうさせている部分も大きいと思っています。
一般職員や新人職員、派遣社員を守っていけるような体制も必要だと思いますが、その反面上司や上に立つ人間を育てていく環境や体制も必要不可欠ですね。
あっちを立てればこっちが立たずの環境では何事も上手くいきません。
どんな職員であっても「会社に守られている」と思えなければ良い仕事はできないことでしょう。
そういう体制を作っていくのが会社の使命だと思っています。