介護事業所に勤めていて、「退職したい」と思った場合、まずは直属の上司に伝えます。
その段階で引き留められたり、「他の職員や利用者に迷惑が掛かる」などと意味不明な屁理屈を言われ、最終的に丸め込まれてしまい「退職ができない」というパターンがよくあります。
しかし、それでは憲法上保障されている「職業選択の自由」や「民法627条1項の規定」にも反してしまうことになります。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(民法627条1項)
しかし、万年人員不足の介護事業所では何度も根気よく「退職の意思」を伝え「やっと退職できる」ということが常態化しています。
今回は、「介護職員は辞めたい時に辞められないのか」「介護事業所で常態化している【退職待ち】とはどういう状態なのか」「退職待ちの対処法」について記事を書きたいと思います。
介護事業所で常態化している「退職待ち」とは
何故、介護職員は辞めたい時に辞められないのでしょうか。
また、介護事業所で常態化している「退職待ち」の実態と対処法について書いていきたいと思います。
誰であっても辞めたい時に辞められる
結論から言えば「誰であっても辞めたい時に自由に辞めることが可能」です。
法律上(民法627条1項)では「いつでも解約の申し入れができる」と規定されており「最短で2週間」で退職することが可能ですし、双方(事業所と退職希望者)が合意すれば「即日」での退職も可能です。
要は「双方の合意」があればいつでも辞められますし、事業所側の合意がなくても「2週間後」には退職することができるのです。
極端な話、事業所側の合意がなくても「急に来なくなって辞めた」という人もいるのではないでしょうか。
その行為が社会人としての常識やマナーや倫理的な問題があるにしても、それによって法律で罰せられることはありません。
その極端な例も含めると「誰であっても辞めたい時に自由に辞められる」と言えます。
但し、その行為によって「会社に著しい損害を与えた」「法律に抵触するようなことがあった(会社のお金を横領していた等)」などがあれば、それはまた別の問題になります。
「退職待ち」とは
誰であっても辞めたい時に自由に辞められるはずなのに「すぐには無理」「新しい人が入ってくるまで待って欲しい」などと言われて「全然辞められない」ということが往々にしてあります。
「退職したい」という意思を伝えたのにも関わらず、「自分の希望するタイミングで退職できない」「退職日を先延ばしにされる」という状態のことを「退職待ち」と言います。
また、就業規則や社内規定などで「退職予告は3か月以上前」などと規定してある場合もあります。
事業所側は、それを盾にして「退職待ち」を正当化させているわけですが、一般的には「民法が定める2週間」が優先されると考えられています。
退職待ちへの対処法
退職待ちの状態から脱するためにはどうすればいいのでしょうか。
その対処法をご紹介したいと思います。
①毅然とした態度で臨む
思い起こしてみると過去に退職していった人の中でも「すぐに退職できた人」と「退職待ちをさせられた人」がいるのではないでしょうか。
「すぐに退職できた人」の多くは毅然とした態度で臨んでいます。
退職待ちをさせられる人も真剣に毅然とした態度で臨んでいるでしょうが、「事業所は人によって対応を変え人を見て判断」しています。
つまり、退職待ちをさせられる人は「事業所が舐めて掛かっている」「丸め込める相手だと思っている」ということになります。
そして、それは実際そうなっているわけです。
事業所側も「退職の申し入れ」ではなく「退職の相談」をされている程度にしか思っていない場合もあります。
仮に薄々気づいていたとしても「どうせ引き下がるだろう」ということをわかってやっているのです。
自分自身の性格や既に形成された人間関係があるので、急に人格を変えた対応をすることは難しいでしょうが、「これは相談ではなく退職の申し入れなのだ」ということを意識して毅然とした態度で臨む必要があります。
②転職先が決まっていると伝える
退職待ちをさせられるのは事業所側が「退職理由に急迫性を感じないから」という場合もあります。
この場合、「転職先が決まっていて入社日も決まっている」ということを伝え、「退職待ちをしている場合ではない」ということを理解して貰う必要があります。
しかし、実際は転職先など何も決まっていない場合もあるでしょう。
上司が根掘り葉掘り転職先のことを聞いてくる可能性もあります。
仮に転職先が決まっていなくても退職するための「方便」もありだと思いますし、事業所や上司に対して「転職先も入社日も決まっている」という情報以外のことを伝える必要はありません。
詳しくは下記記事に書いています。
③内容証明郵便を利用する
退職願(又は退職届)を受け取ってもらえない場合は、「内容証明郵便」を利用して提出する方法です。
内容が証明された郵便なわけですから、会社に届いた時点で内容の効力があります。
つまり、「退職願に記載した期日が到来すれば労働契約は終了」します。
④退職代行サービスを利用する
賛否両論あるでしょうが、「退職代行サービス」を利用するのもひとつの方法です。
但し、話がこじれてしまったり法的な問題が発生する可能性もありますから、必ず「弁護士」がやっている退職代行サービスを利用しましょう。
「退職くらい自分で何とかするものだ」という考え方もありますが、これだけ社会情勢も変化し多様化してきている中で「退職したいのに退職させて貰えない」というのは「労働問題であり人権問題」でもあります。
人権問題や「民法が優先だ、社内規定が優先だ」というような法律問題を弁護士に依頼するのは何もおかしなことではありません。
おかしいのは「退職待ちをさせている事業所」なのです。
【退職代行サービスのご紹介】
・会社を辞めたいけど勇気が出ない
・会社がなかなか辞めさせてくれない
・退職することでトラブルが発生してしまった
・会社に行かずに退職したい
・即日退職したい!
そんなあなたに朗報です!
「法律事務所の弁護士」が、あなたの退職を代行してくれます(相談無料)。
しかも「税理士事務所」「社会保険労務士事務所」「行政書士事務所」とも提携しているので、どんな状況でもバックアップが可能な退職代行サービスです。
最後に
今回は、介護事業所で常態化している退職待ちとその対処法について記事を書きました。
「退職待ち」をする前に「何故職員が定着しないのか」「どうすれば職員が定着するのか」を真剣に考える必要があります。
その「一番大切な部分の検討や対策」を怠っておきながら、退職しようとしている職員へ更に圧力や負担や苦労を掛けている姿は滑稽であり本末転倒です。
「多少なりともお世話になった事業所だから穏便に円満に退職したい」という気持ちもわからなくはありませんが、その気持ちに付け込んでくるような上司や事業所を客観的に見ると「どうかしている」としか思えません。
そんな「どうかしている人達」をいつまでも相手にしたり気を遣ったりするよりも、早く自分の人生から切り離して自分にとってプラスになることをしていく方が、どう考えても得策ではないでしょうか。







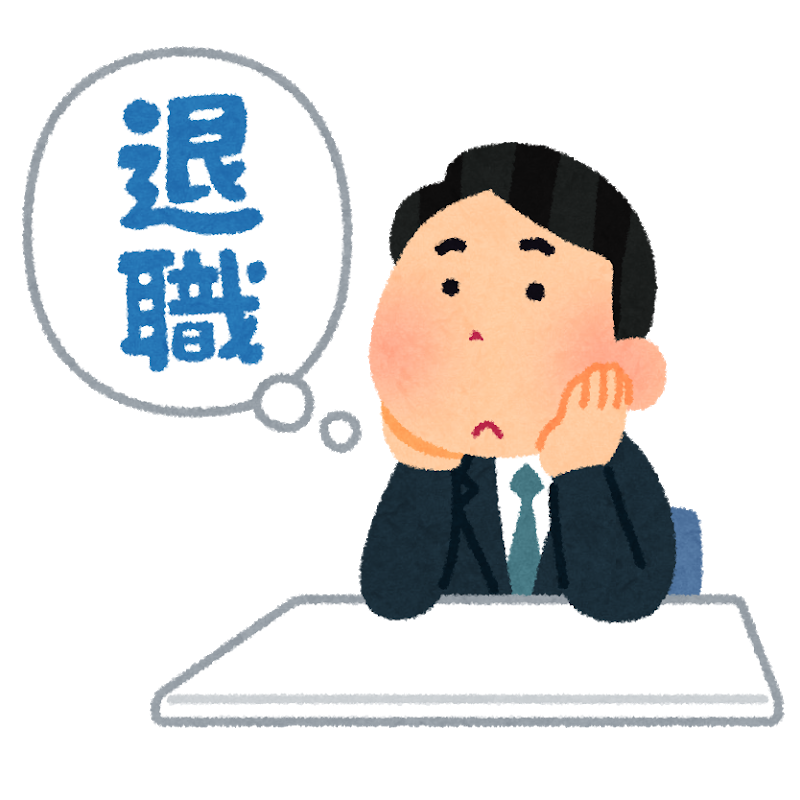

コメント
ありがとうございます。ホント辞める事を伝えたときの相手の出方次第では出るとこ出ます。頑張ります。
確かに告発もアリですね。
ホント職員全員から嫌われてる施設長ですから。こんな人って珍しいですよ。
正直穏便に辞めたいですが無理かなと思ってます。
>かずさん
穏便に済めばそれが一番良いのでしょうが、そのために泣き寝入りをしなければならないとすれば本末転倒ですよね。
私も泣き寝入りは嫌ですね。
ほんの少しの勇気と行動力があればきっと上手くいくでしょう。
そもそもこちらは何も悪いことはしていないのですから。
陰ながら応援しています^^
別のコメントでも書きましたが施設長は介護職を奴隷扱いしてバカにしてますからね。
退職したいって言った職員の話真面目にきかないでバックレかまされたこともありましたし。
就業規則守って筋通して辞める職員をなんで気持ち良く辞めさせてくれないのか理解に苦しみます。ホントクズ施設長ですよ。労基に先日相談したら退職の際はまた遠慮なしに相談してくださいって言われました。その時は施設長の悪行ばらすつもりです。
>かずさん
人を見下したり奴隷扱いするような人が福祉や介護に携わっていて、ましてや施設長だなんてちゃんちゃらおかしいですよね。
とは言え、そういう人って結構いるような気がしますね。
介護保険法や介護保険制度に違反している場合は市町村などの行政にリークするのもありだと思います。
ウチの施設で何年も前から退職希望出して今年の3月いっぱいで晴れて退職決まった職員さんがいました、が、今月の勤務表に名前が乗ってました、週2回の半日勤務なんですが、施設長に遺留されて断り切れなかったみたいです。なんか加算の関係もあるみたいで…。
あと、他から聞いた話ですが施設長がその職員さんの事を諦めきれないって言ってたそうです。いったいどういう意味なんだか…変な勘ぐりした職員もいました。確かにその職員さん性格も穏やかで仕事も丁寧で杉山愛を綺麗にした感じの人なんですが(でもいい年です)
余談ですがウチの職場年度末期末手当出ますが今年は出ませんでした。理由の説明もなしで施設長しらばっくれようとしてました。理由があるならきちんと説明してほしいです。だから辞めたいって人多いんですよね、ウチの施設。
>かずさん
コメントありがとうございます^^
辞めたいのに半ば強引に引き止められて辞めるに辞められないというパターンは本当によく見掛けますね。
期末手当やボーナスを出すも出さぬも法人の自由だという理論でいけば、会社を辞めるも辞めぬも本人の自由だと思うのですが、その辺が全くもって片手落ちというか図々しさを感じますね><