一般的に「愚痴は言わない方が良いもの」「愚痴からは何も生まれない」と言われています。
ですから、愚痴に対して否定的批判的な意見もあるでしょうが、介護現場で働いているとストレスが溜まるのも事実です。
別の方法でストレスを解消したり、愚痴を建設的な意見に変えていくことが大切なのですが、一番手っ取り早いストレス発散方法が愚痴だったりします。
また、意見を言っているつもりなのに愚痴と捉えられてしまうなど八方塞がりの現実があったりもします。
そもそも、「愚痴を言うな」と門前払いをしてしまう風潮に新たなストレスを感じてしまいかねません。
もちろん、愚痴を言われている方に迷惑が掛かったり不快な思いをさせてしまっては本末転倒ですが、愚痴を全く吐き出せないという状況にも不健全さを感じてしまいます。
今回は、介護職員の愚痴から生まれる3つのメリットをご紹介したいと思います。
介護職員の愚痴から生まれる3つのメリット
何事も過ぎたるは及ばざるが如しで、過剰だったり一方に極端に偏ってしまうことは良くありません。
ですから、「愚痴ばかり言う」ことは良くないのと同時に、「一切愚痴を言わない」若しくは「一切の愚痴を禁じられる」ということも良くないということになります。
どんなことにも、丁度良さやバランスが必要なのです。
ちなみに、ポジティブ思考は良いものとされていますが、ポジティブ一辺倒になってしまうことにもデメリットがあることは過去記事でご紹介しました(下記記事参照)。
どんなことでもメリットとデメリットがあるわけですが、では、介護職員の愚痴も一辺倒にさえならなければメリットが存在するのでしょうか。
以下で愚痴の3つのメリットをご紹介していきます。
①気持ちがスッキリする
愚痴の最大のメリットが「愚痴を言うことで心や気持ちがスッキリする」というストレス解消効果です。
ただ聞いてもらうだけでいいのです。
問題の根本的な解決にはなりませんが、即効性があります。
もし介護現場でイライラした場合、アンガーマネジメントを駆使して怒りやイライラのコントロールをすることが推奨されていますが、これは「怒りやイライラを抑え込む方法」ではありません。
アンガーマネジメントでは、怒りをコントロールすることを目的として「正しく怒ることも必要」とされていることに鑑みれば、「正しく愚痴を言う」ということも必要ではないでしょうか。
つまり、時と所と場合(TPO)を間違えないように愚痴を吐くことで介護現場でのイライラや怒りがコントロールできるのだとすれば、アンガーマネジメントの目的に適っていると言えます。
この場合のTPOとは、大前提として利用者に直接言わないということです。
TPOを弁えた愚痴によって、少しでも言った本人の気が晴れて引き続き健全な介護業務ができるのだとすれば、「愚痴様様」です。
言う相手や言う場所や言う内容さえ間違えなければ愚痴にもメリットがあるのではないでしょうか。
②頭の中を整理することができる
愚痴を建設的な意見に昇華させたり、ポジティブに転換させていくことも確かに大切なことですが、いつでもそう上手くいくものでもありません。
何故なら、愚痴を言いたいことが1つではなく複数ある場合もありますし、自分の思考を整理して言葉にすることが苦手な人もいるからです。
特に介護現場では、次から次へとやらなければならない業務は尽きませんし、「何が何だかわからないうちに鬱々とした気分のまま1日が終わった」ということだってあります。
そんな状況で、愚痴さえ言えなければ鬱々としたストレスを溜め込み、言い知れぬ不快感を抱きながら働き続けることになり、知らず知らずのうちに心が削られていき、最悪の場合は心がポッキリ折れてしまいかねません。
ですから、仮にそれが「ただの愚痴」だったとしてもアウトプットをすることで、ストレスが解消できるばかりか自分の脳内の思考を整理させることになり、やがて建設的な意見を言えるようにもなるでしょうし、そもそも、少しくらい愚痴を漏らす方が人間らしいと言えます。
愚痴を言う相手も、
- 上司や同僚
- 親友
- 家族
などの「人」である場合もあるでしょうし、人ではなくても、
- 匿名性を持たせた上でTwitterなどのSNSに投稿する
- 日記やメモ帳に思うがままに書き出してみる
などの方法でもありでしょう。
そうすることで、「あ、自分はこういう考え方をしていてこういう出来事に不快感を抱いていたんだな」ということを再認識することができます。
再認識して頭の中を整理させることで段々と建設的な意見が言えるようになったり、他者から有効なアドバイスを貰うことも可能になるのではないでしょうか。
もちろん、TPOに応じて愚痴を吐いていく必要がありますが、「ただの愚痴からは何も生まれない」というスピーチロックに惑わされないようにすることが大切です。
③問題点を表面化させる
愚痴は何か問題があるから出てくるものです。
もちろん、その問題は愚痴を言っている人だけのものである場合もありますが、職場全体の問題である場合もあり得ます。
言葉がまとまらず上手く言えずに「ただの愚痴」のように捉えられてしまう場合がありますが、少なからず「何かの問題」があるのです。
但し、「常時愚痴ばかり言っている人」「当たり屋のように愚痴を言っている人」の場合は、その本人の人間性や性格に問題があるという可能性も否定できないのは「何事も一辺倒は良くない」と前述した通りです。
愚痴が生まれやすい状況は以下の7つのパターンがあると言われています(参考文献(楽天Kobo):グチの教科書【電子書籍】[ 原 祐美子 ])。
- 日常のイライラ(イレギュラーなことが起こってイライラしてしまうなど)
- 疑い・不安(上司への不信感や将来の不安など)
- 到達不能(無理難題や理不尽なことを言われて「自分にはできない」と感じてしまうなど)
- コンプレックス(容姿、体型、学歴、資格など)
- 愛情からの心配(「あの人はこのままで大丈夫なのか心配」と感じてしまうなど)
- コミュニケーションミス(上司の言う通りに動いたのに怒られてしまうなど)
- 期待外れ(処遇改善手当やボーナスがもっと沢山貰えると思っていたのに雀の涙ほどだったなど)
上記に照らし合わせてみると、いずれも介護現場であり得そうなパターンではないでしょうか(もちろん、上記に当てはまらないパターンもあるでしょうが)。
そして愚痴の正体は「その問題点を指摘している」と言えます。
つまり、「愚痴は問題を表面化させるというメリットがある」のです。
問題が発見できれば、解決したり改善する糸口にもなります。
もし、愚痴によって問題が露出し解決に至るのだとすれば「愚痴を言うことで最終的に根本的な解決に至ることも可能」という結論を導き出すことができます。
ですから、「ただの愚痴からは何も生まれない」と言い切ってしまう人こそ、「臭い物には蓋をしたい無責任で隠蔽体質な楽観主義者」と言えるのではないでしょうか。
最後に
今回は、介護職員の愚痴から生まれる3つのメリットについて記事を書きました。
もちろん、愚痴を聞く側がウンザリしたり不快な気持ちになるというデメリットがあるものの、TPOを弁えることで少なからずメリットも存在するため「絶対に愚痴を漏らしてはいけない」ということも適切ではないという結論になります。
そもそも、介護職員はロボットではなく人間なのですから、ストレスも溜まりますし愚痴も言いたくなります。
「守秘義務」「職業倫理」「個人情報保護義務」「専門職としての自覚」などなどが存在し愚痴などを漏らしにくい職業であることは重々承知をしておりますが、今本当に必要なのは「一切愚痴を言うな」という冷たい北風ではなく「(TOPに応じて)愚痴を言っても良いんだよ」という暖かい太陽なのではないでしょうか。



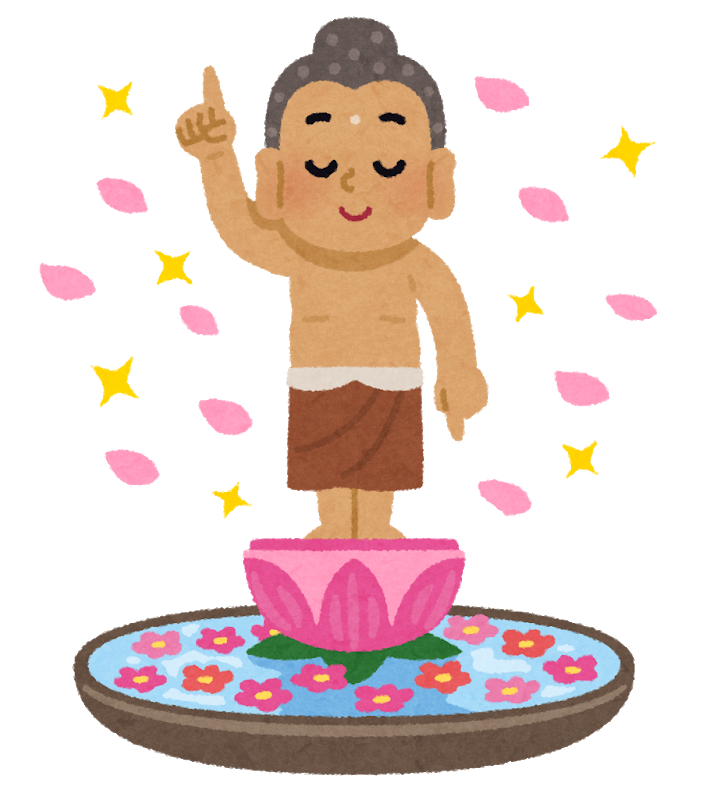
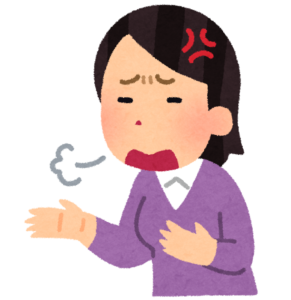






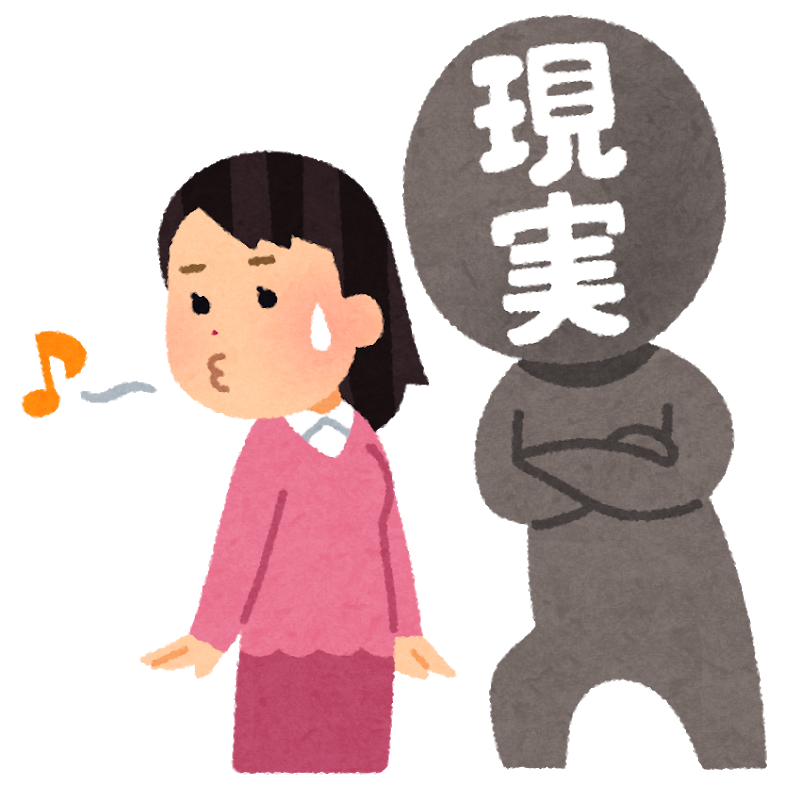

コメント
そもそもなんで人間は愚痴を言うのかっていうと、「昔あった自分にとって嫌なことを愚痴を言うことで忘れないようにして、二度と同じ目にあわないようにするため」だそうですよ。
特に女の人は、かなり昔のことを思い出してはよく文句を言ってますけど、これも理由があるそうです。
そもそも動物のメスは巣にいて子供など群れを守らないといけないので、「こういうことがあって危なかった」というのを覚えとかないと、同じ危険なことが起きたら群れが全滅しちゃう。
逆にオスは、危険をかえりみず狩りに行かなきゃいけないので、昔あった危険なことを忘れるようになってるそうですよ。遺伝的に。
もちろん、個人で差があるし、「ライオンなんてメスが狩りするじゃん」とかいう指摘もありますけど、「愚痴=自分に昔あった不都合なことを忘れないように反芻してる」っていうのはなるほどと思いました。
だってただ嫌なこと思い出すだけなら、何のメリットもないもんね。心理学的にはマゾとか意味付けはされるかもしれんけど。
で、大事なのは「昔あった嫌なことをどうやって回避するか」だと思うんですよね。
愚痴を言うだけでは生産性も発展性もなく、単に嫌な思いを繰り返しするだけなので。
嫌なことを回避するのはもはや動物としての危機回避能力と言えるでしょう。
私の場合は、とにかくスルーする。責任をかかえこまない。仕事はするけど、私がしますとは積極的には言わない。やろうと思えばできるけど。で、他人にさせる。だって何も仕事しない人たくさんいますからね。何も仕事しない人って仕事できないので、させようとするとできないんですよ。で結局、「できないからいっか」「もうやらないでいっか」となるわけ。
その結果、サービスの質が落ちて売り上げダダ下がりなんだけど、まあすぐには会社が倒産しないでしょ。
今よりもっと売り上げ下がったらその時は・・わからないけども。ww
>デイちゃんさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
なるほど、愚痴は危険予知や同じ危険を回避するための動物的な本能なのですね。
確かに、問題は「それ」を活かしてどう回避していくかですね。
全ての愚痴を否定的なものとして捉えたり言わせないようにする人達は、愚痴を言う人に「学習して貰ったら困る」「問題点を露呈されたら困る」という心理も働いているのかもしれませんね。
「理不尽なことも文句言わないでやりなさい」みたいに言うけど、おかしいことはおかしいから。
あとは、理不尽なことをうまく回避する方法を身につけたいですね。
理不尽なことをおしつけられてさせられてるのは、カモになってるだけですからね。
そうそう、今日衝撃の事実が。(いや別に衝撃ではないけども)
余命わずかで看取り期の方がいたのですが、その方が先日亡くなられて、管理者が葬式に行ったそうなんです。
したら家族の人に、「母が〇〇さん(私)によくしてもらったっていつも言ってた」って言われたんだって!!。
マジか。いや確かにそれなりに丁寧にはしましたよ。できる限りのことを精いっぱいはしましたよ。
他のカスタッフはその重度の利用者さんは完全スルーでしたよ。
私だけ毎回入浴オムツ交換して、口からもうものが食べれないというけど少しずつジュース飲ましたりとか、スポンジブラシで口腔ケアしたりとか、唇にワセリンぬったりとかしましたよ。
でもそんな末期で意識ももうろうとしてたのに、私の名前出してよくしてもらったって言うか~!?!?と、その話聞いたとき「マジか!」と思わず言いましたよ。
胸がちょっと痛いと言うか、不思議な感覚がしましたよ。
私は別に評価されたいとか、ほめられたいとか、な~んにも思ってないんですよ。ただ自分の良心に従って仕事してるだけなんですよ。他のカスタッフがサボりまくってるのを横目に。
でもやっぱり良心に従ってサボらずまじめに仕事した方がいいよね~と思ったのでした。
>デイちゃんさん
こんばんは~
返信ありがとうございます^^
理不尽なことを本気で回避しようとすると、事を荒立てることになったり、上司から睨まれるなどの「居心地の悪さ」が発生してしまいますからね。
要は、足元を見られたり高をくくられているんでしょうね。
そういう利用者(家族)からの言葉って嬉しいですよね。
別に期待しているわけでもないし、感謝をして欲しいわけでもないですが、見てくれている人はちゃんと見てくれているんだなぁという気持ちになりますね。
色々な意味で介護って奥深いですね。