早いもので今日から6月です。
既にご存知の人もいらっしゃるでしょうが、本日(2020年6月1日)より、パワハラ防止法(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(略称:労働施策総合推進法))が施行されます。
これは以前からある法律ですが、2019年5月に改正された際に「パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置(第30条の2)」が義務付けられたことで、通称「パワハラ防止法」と呼ばれています。
この法律の施行により、企業側に「職場内のいじめやパワハラの防止」や「適切に対応するために必要な体制の整備」が義務付けられることになります。
ということは、介護現場も含め職場内でのいじめやパワハラが無くなるのでしょうか。
もしそうなれば、働いている側としては大変ありがたい話です。
今回は、このパワハラ防止法の実態やその効果について、介護福祉士である私の意見を書いていきたいと思います。
※当ブログでは、介護に特化した内容でありながら度々法律問題にも触れておりますが、当方は学士(法学)課程を修了しておりますので、学問のひとつとしての個人的見解(ひとりごと)の側面も有しております。
【実態と効果】パワハラ防止法の施行で介護現場のパワハラは無くなるのか?
2020年6月1日よりパワハラ防止法が施行されることになり、職場内でいじめやパワハラに悩んでいる人にとっては朗報のように聞こえます。
しかし、手放しで喜んでしまうのは時期尚早かもしれませんので、その内容や実態を詳しく解説していきたいと思います。
今回義務化されたのは大企業のみ
まず注意しておかなければならないのは、「本日6月1日からパワハラ防止法によってその内容が義務化されるのは大企業のみ」という点です。
つまり、「しばらくは中小企業は努力義務であり義務ではない」ということになります。
中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されることになっているため、それまでは努力義務でしかないのです。
では、「大企業」と「中小企業」の定義や線引きはどうなっているのかと言うと、表にまとめると以下になります(参考資料:都道府県労働局 雇用環境・均等部(室))。
中小事業主とは、以下の①又は②のいずれかを満たすものを指す。
|
つまり、上記に該当しない又は上記よりも大規模である場合が「大企業」ということになります。
となると、今日から施行されたパワハラ防止法が未だ努力義務でしかない介護事業所も多いのではないでしょうか。
もちろん、努力義務ではあっても、適正に遵守できるように可能な限り努力していく倫理観やコンプライアンスが求められるのは間違いありませんが、2022年4月1日までは「あくまで努力義務」であるということは、労働者としても自分に関係してくる場合があるので知っておく必要があります。
パワハラに該当する6類型とは?
次に、どのような事案や内容であればパワハラに該当するのか、はたまたしないのか、という線引きが必要になってきます。
何故なら、パワハラ防止法が施行されたからと言って、何でもかんでもパワハラ認定されてしまうことになると、上司から部下への指導や注意さえしにくくなり正常な組織運営を妨げる要因になってしまうからです。
これについては、厚生労働省が「職場におけるハラスメント関係指針(PDF)」において、パワハラに該当する6類型を示していますので以下に表にまとめておきます。
| パワハラの6類型 | パワハラに該当する | パワハラに該当しない |
| ①身体的攻撃 | 物を投げつける | 誤ってぶつかる |
| ②暴言 | 人格を否定するような言動 | 遅刻など社会的ルールを欠いた言動を再三注意して、それでも改善されない場合に更に厳しく注意を行う |
| ③人間関係からの切り離し | 集団で無視をしたり、職場内で孤立させる | 新人育成のため、別室で短期集中研修を実施 |
| ④過大な要求 | 業務とは無関係の私的な雑用の処理を要求 | 繁忙期や育成のために通常より多い又は高い内容の業務を要求 |
| ⑤過小な要求 | 嫌がらせで仕事を与えない、管理職を辞めさせる目的で誰でもできる業務をさせる | 能力に応じて一定程度の業務量を軽減する |
| ⑥個の侵害 | 本人の了承を得ずに性癖や性的指向を暴露する | 本人の了承を得た上で個人情報を人事部門などに伝える |
つまり、何でもかんでもパワハラに該当するものではないとしつつも、現状で「パワハラに該当することをやっている介護事業所もある」のではないでしょうか。
例えば、「集団で挨拶を無視する」「派閥を作って特定の職員を吊るし上げたり孤立させる」というようなことがある場合はパワハラに該当する可能性が高くなります。
今までの介護事業所内の常識や風潮そのものが、実は非常識であったりパワハラそのものである場合もあるのではないでしょうか。
今一度、職場内の環境や風潮を再確認してみることが重要です。
残念ながら罰則がない
どちらにしても、「確実にパワハラに該当するものは法律違反となる」「労働者に追い風が吹いている」と手放しで喜びたいところですが、現実はそう簡単にはいきません。
何故ならば、残念ながら「パワハラ防止法には罰則がないから」です。
罰則が無いということは、「違反しても処罰されることはない」ということですので、結局は「パワハラが野放し状態になる」という懸念が残ります。
もっと言えば、「パワハラ防止法そのものが無意味」という懸念です。
この事実を知った時に、一気に期待感が急落しテンションもダウンしてしまうことでしょう。
この点に関しては、「パワハラ防止措置を怠っている企業は厚生労働省から行政指導が行われたり、ペナルティとして企業名の公表がなされる」ということになっています。
しかし、本当の問題は「労働者の訴えがそこまで行き着くことが非常に困難」ということです。
つまり、事業所側はパワハラ防止措置としての窓口を設置し、一見防止措置を講じているように見える場合でも、
- 相談窓口の責任者そのものがパワハラの権化
- 窓口に相談しても取り合ってもらえない(パワハラではないという判断をされる)
- 話し合いの末に丸く収めるよう半強制された(新たなパワハラ)
ということが往々にしてあり得るからです。
つまり、「防止措置(義務は全う)はしているけれど実際のパワハラは無くならない」という懸念が残ってしまうことになります。
パワハラ認定は誰がするのか
パワハラの訴えを起こした場合に、その認定は一体誰がするのでしょうか。
事業所の相談窓口の責任者でしょうか、それとも労働基準監督署でしょうか、はたまた厚生労働省でしょうか。
答えは、「最終的にパワハラ認定をするのは裁判所」です。
但し、段階があって、最初に判断するのは「事業所の相談窓口でありその後の事業所内での調査の結果」になります。
しかし、前述したように、事業所内でパワハラがはびこって野放し状態だったり、双方の意見が衝突し解決しなかったり、そもそも窓口の責任者そのものがパワハラの権化である場合には最終的には裁判に持ち込むことになります(労基署や厚労省では個別の事案の判断ができません)。
つまり、パワハラ認定をするための手順は、「事業所の相談窓口」→「裁判」という流れになるのです。
この流れは、「パワハラ防止法があっても無くてもほぼ同じ流れ」になります。
パワハラ防止法の存在意義としては、「裁判に行くまでに事業所側が防止措置を講じていたか否か」という抑止力の効果となるのではないでしょうか。
パワハラを刑法や民法などで対応していく
パワハラ防止法には罰則がなく、最終的には裁判でパワハラ認定を争っていくしかないことを前述しましたが、実際にはパワハラを刑法や民法に当てはめて対応していくことも必要になってきます。
パワハラそのものではなく、刑法違反や民法違反としてその罰則や損害賠償を争っていく方法です。
では、パワハラに関連した刑法と民法にはどのような規定があるのでしょうか。
以下でご紹介していきます。
刑法
- 第三者を前にして被害者の名誉を傷つけたとき:「名誉毀損罪(刑法第230条、公訴時効3年)」
- 差別的な発言・相手をけなす発言をしたとき:「侮辱罪(刑法第231条、公訴時効1年)」
- 暴行したとき:「暴行罪(刑法第208条、公訴時効3年)」
- 相手に傷害を負わせたとき:「傷害罪(刑法第204条、公訴時効10年)」
- 脅迫したとき:「脅迫罪(刑法第222条、公訴時効3年)」
- 暴行や脅迫などを行うことで義務のないことをさせたとき:「強要罪(刑法第223条、公訴時効3年)」
【引用元】https://www.dodadsj.com/content/190526_harassment/
民法
- 加害者の故意または過失によって被害者の権利や利益が侵害された場合:「不法行為責任(民法第709条、時効3年、除斥期間20年)(※)」
- 従業員が業務の執行について第三者に損害を与えた場合:会社(使用者)が損害賠償の責任を負うとされる「使用者責任(民法第715条、時効3年)」
- 使用者が従業員に対して生命・身体の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとされる「安全配慮義務」を怠り損害を与えた場合の損害賠償義務。「債務不履行責任(民法第415条、時効10年)」
- その他、使用者が従業員に対して生命・身体の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとされる「安全配慮義務」を怠った場合:安全配慮義務(労契法5条)
(※)改正民法適用後は人の生命又は身体を害する不法行為の時効は5年(724条の2)
【引用元】https://www.dodadsj.com/content/190526_harassment/
介護現場のパワハラは無くなるのか
ここまでパワハラ防止法の実態を書いてきましたが、結局この法律の施行によって、介護現場のパワハラは無くなるのでしょうか。
結論としては、「抑止力としての一定の効果はあるものの、パワハラは無くならない」というのが私の答えです。
もちろん、相談窓口の設置などの表面上の体裁は整えられてはいくでしょうが、それが実効性があるかはまた別の話です(前述した通り)。
但し、中には、「パワハラ防止法という法律が施行されたのでパワハラをしないように気をつけなければならない」という善良な事業所も増えてくることを期待すれば、一定の抑止力としての効果はあると思われます。
とは言え、事業所や経営者も海千山千でしょうから、罰則のない法律をかいくぐることには長けていらっしゃる人が多いのではないでしょうか。
となると、労働者側としては最後の頼みの綱は「裁判所」です。
しかし、それでは今までと何ら変わりませんし、そこまで行き着ける労働者が少ないのはご周知の通りでしょう。
ですから、パワハラ被害を受けてしまった場合、まずは労基署に相談をしたり、裁判までする覚悟があるなら弁護士に相談をするということには変わりがありません(裁判をしないために弁護士に相談をするという手段もあります)。
その場合、重要になってくるのは「証拠」です。
現在は、スマホでも音声録音可能ですし、ボイスレコーダーなどを利用して、「言った言っていない」の水掛け論になって話が平行線になったり自分が不利にならないように証拠を残しておくことをおすすめします。
ひょっとしたら、パワハラ防止法の施行によって、裁判までしなくてもこちらの本気度を見せつけることで事業所側が歩み寄ってくる可能性も無きにしも非ずです。
法律は「権利の上に眠る者を保護しない」というスタンスですので、泣き寝入りをする前に「自分で自分の権利を放棄してしまっていないか」ということを頭の片隅に置きながら自分を守っていくことが非常に大切です。
最後に
今回は、本日(2020年6月1日)から施行されたパワハラ防止法について、介護現場でパワハラは無くなるのか、ということについて記事を書きました。
残念ながら、この法律には罰則がないため、実効性の期待は低いものの抑止力としての一定の効果はあるのではないかという結論になります。
「今後一切パワハラが無くなる」という効果ではなく「今より多少はマシになる」程度の効果です。
最終的なパワハラ認定は裁判所の判決になりますが、実際問題、なかなか裁判まですることができない人も少なくはないことでしょう。
そして、それを見越して高をくくっている事業所もいるかもしれません。
まずは、「証拠を残す」など、出来る事から始めてみてはいかがでしょうか。




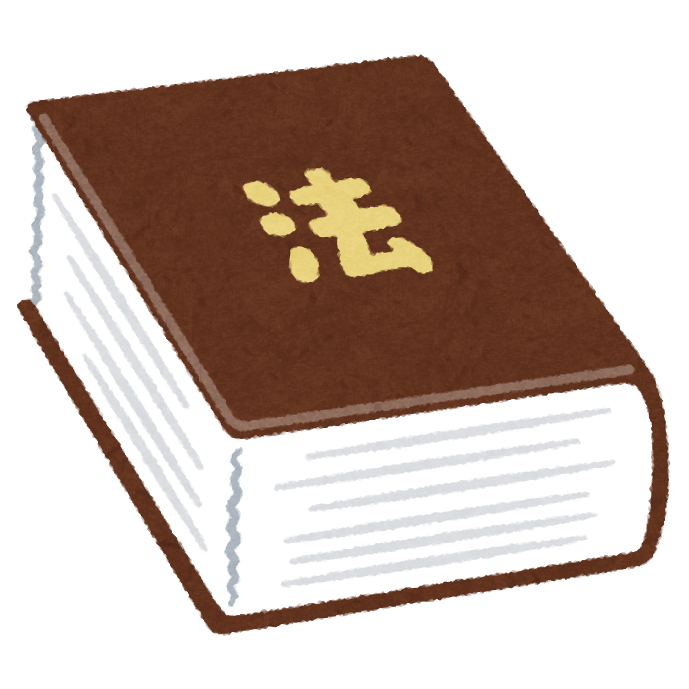


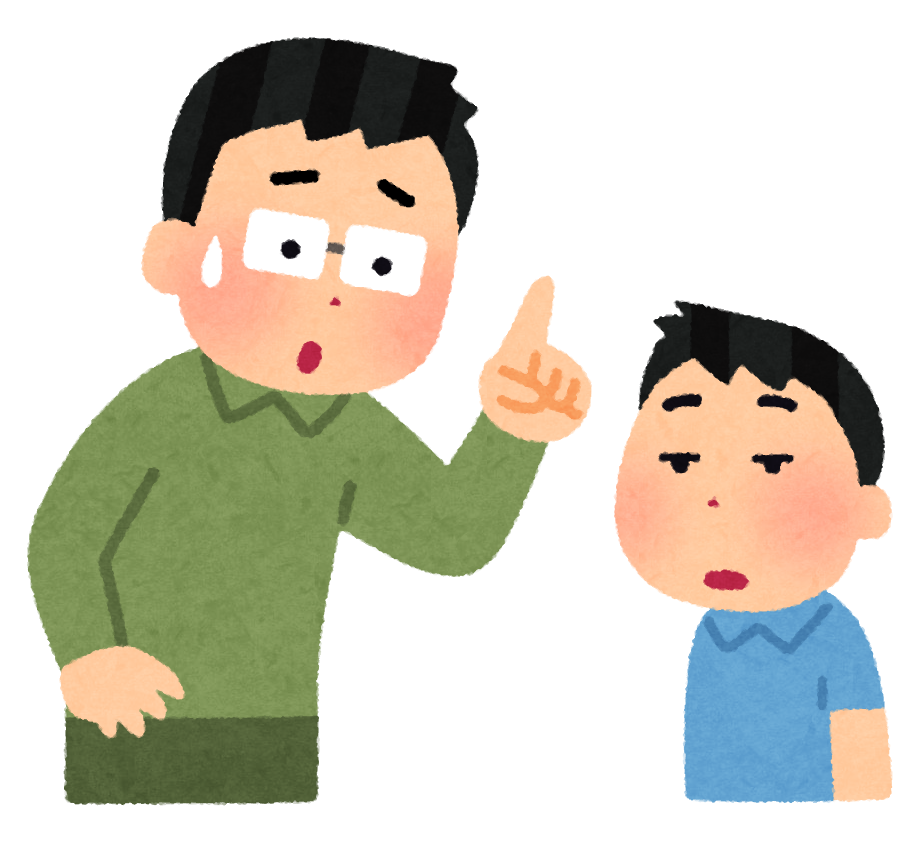





コメント
やっとパワハラというものが認識されてきた感じでしょうか。それまでは言葉はあっても禁止する法律はなかったですもんね。
でも虐待と同じで、禁止はするけど強制力はなくて、結局は他の罪で訴える感じですね。
そうそう、今日、また新しい使徒が送り込まれてきました。利用者さんとスタッフ一人ずつ。
利用者さんは強烈だったけどまあ仕事だから・・って感じなんですけど。でも今でもダメージが残ってる。体とメンタルに。
スタッフは・・・ATフィールド全開、波形パターン青、サードインパクトが起きそうでした。会社の他の事業所で何年も働いてたそうなんですけど、あんな人いったい何の仕事してるんですかね?って感じでした。すごい。とにかくATフィールドがすごかった。
介護の仕事って奥深いですね。(笑)
>デイちゃんさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
罰則が無ければのらりくらりする事業所も出てくるでしょうね。
ただ「防止措置は義務化」されて、義務を怠っていた場合は行政指導や企業名の公表もあるという点で少しは効果があるのかもしれませんね。
何だかまた凄そうなスタッフが来たようですね。
いや本当、介護って奥深いです。。。
どうもです。
虐待も法律ができた後に研修の項目にも入ったので、パワハラも前よりは一般的になるかもしれませんね。
エヴァの新しい映画が公開されるのですが、過去の映画が5月にNHKで放映したのは見てもらえましたか?
あの使徒を見てもらえたら、そのパワーを想像しやすいと思います。
もう使徒スタッフはすごいですよ。ATフィールド全開。波形パターンは青。
利用者のことは何も理解できない、しない。メモもしない。だっていきなり100人くらいの情報を覚えなきゃいけないから、一人ずつ名前と状態を覚えなきゃいけないのに。あなたメモもしないで全部覚えられるわけ?
ぼけ~っと突っ立ってるだけ。「〇〇して~」と言われたら動き出す。そして的外れなことをめちゃ遅くやってる。介助の必要な人は介助しないでスルー、自立してる人は全介助。あなた本当に介護の仕事してるの?オムツかえれるの?要介護度って何?身体介護って何?
コミュニケーションも不能。なんか日本語の発音が不思議な感じ。
まさしく使徒。ATフィールド全開。
管理者が「あんな人よく雇ってるな。しかもあれで6年もいるらしいわ。夜勤とかどうしてんだろ?」って言ってたわ。たぶん夜勤で何人か死んでるね。
あんな風に何も仕事しないでぼけ~っといるだけなら楽だわ。仕事量0で給料もらえたら、すごいラッキー。だからやめないんだね。納得。
いやいや、今デイはサボりまくりのカスタッフばかりだから、それを見越して異動させたんだろうか。そこまで考えてたとしたら支店長はすごいな。でも実際は何も考えてなくて、今いる入居施設が赤字になってとりあえず人件費削らなきゃってデイに異動させただけだとは思うけど。
長くなりました。あまりにも今日は精神的にも肉体的にも追い込まれた。使徒おそるべし。
>デイちゃんさん
返信ありがとうございます^^
せっかくおすすめして頂いておきながら…時間がなかなか取れずにまだ観ておりません(すいません><)。
ただ何となくですが、その凄さは想像がつきます(笑)
確かにどんな人材でも1人は1人ですから、人員配置基準には組み込めますからね。。。
いやはや、おつかれさまでした。
で、さっそく管理者がパワハラしてたんですけど、使徒はATフィールド全開だから全く通じず。
パワハラしても何も感じない人っているんですね。
まあ使徒は常勤じゃないので、だんだん勤務時間減らされそう。
昔いた使えないスタッフ、月の勤務時間が10時間に減らされて、自主退職に追い込まれてました。これもパワハラ??
>デイちゃんさん
返信ありがとうございます^^
なるほど、そういうパターンもあるのですね。
勤務時間を減らされて自己退職に追い込まれるのは本人がパワハラだと思って訴えを起こせば調査はされるでしょうが、管理者側も正当性を主張(他の職員に迷惑が掛かる、利用者に危険が及ぶ可能性、再三注意しても改善されないためやむを得ず、本人の能力に応じた勤務時間にするために減らした等)をするでしょうから、最終的には双方の言い分によって裁判所の判断になるのでしょうね。