介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格があれば、自分一人で独立開業し「居宅介護支援事業所」を立ち上げることができます。
居宅介護支援事業所の人員基準は「管理者」と「介護支援専門員」だけでいいので、自分一人で兼務できるからです。
しかし、現段階で厚生労働省が2021年4月からその管理者を「主任介護支援専門員に限定」する方針を固めているため、主任ケアマネではないケアマネが一人親方として独立開業できるのは2021年3月までになります(現在は経過措置中)。
仮に2021年3月までに開業できたとしても、翌月の4月には主任ケアマネを管理者に据えなければ人員基準を満たさないことになってしまいます。
主任ケアマネになるためには、ケアマネジャーとしての実務経験が5年(60ヶ月)以上あり、長期間の主任ケアマネ研修を修了する必要があるため、厚労省のこの方針によって「主任ケアマネの需要は高まっている」と言えます。
そんな中、2021年4月から逆算して考えてみると「時間的にどう考えても主任ケアマネの取得が間に合わない」という管理者や事業所もあります(あと2年弱しかないですからね)。
ですから、ケアマネ協会が「現在の経過措置期間を延長して欲しい」と要望しているようです。
さて、前置きが長くなってしまいましたが、以上が最近の居宅介護支援事業所事情になるわけですが、自分1人で独立開業した場合どうなるのでしょうか。
居宅介護支援事業所を開業するとどうなるのか
ケアマネ資格は国家資格ではなく、あくまで都道府県が認定する公的資格になります。
公的資格であるケアマネ資格を持っていて「運営基準や人員及び設備基準」を満たした法人であれば、居宅介護支援事業所を開業することが出来ます。
「運営基準」は法律法令規定に則って適切な運営をする必要があります。
「人員配置基準」は管理者とケアマネは兼務できるので、ケアマネ資格を持っている自分一人で開業可能です。
「設備基準」は定められた広さの事務所と、相談スペースを用意できればクリアできます。
資金面から見ても意外と開業のハードルが低いので、ケアマネ資格さえ持っていれば誰でも気軽に独立開業出来るのですが、居宅介護支援事業所として独立するケアマネは少ないのが現状です。
その理由は結論から言ってしまうと「儲からない上に過酷」だからです。
「儲け過ぎてはいけない」という理念
介護保険制度は介護保険料と税金によって利用料が賄われており、また、そもそも「福祉というものは儲け過ぎてはいけないもの」という理念が根底にあります。
それはどの介護保険サービスでも言えることなのですが、居宅介護支援事業所は特にその傾向が顕著になります。
その証拠として、介護施設や病院などに併設された居宅介護事業所では「法人内で一番利益を生まない部署(事業所)」と揶揄されることがあります。
「利益が少なくても介護保険制度上、必要な事業所」であり、そもそも「儲ける前提の事業所ではない」ということになります。
頑張れば頑張るほど報酬が下がる
売上を上げていくためには、顧客の獲得が必要です。
新規で独立型の居宅介護支援事業所を立ち上げたばかりの時は、まずは他の法人や事業所へ挨拶を兼ねて営業が必要になります。
トントン拍子に進んで顧客となってくれる利用者が増えたとしても、居宅ケアマネには「取り扱い件数の縛り」があります。
「35人推奨、39人までは減算なし、40人以上は減算あり」という縛りです。
| 【居宅介護支援費】 | 要介護1・2 | 要介護3・4・5 | 取扱件数 |
| 居宅介護支援費Ⅰ | 1053単位/月 | 1368単位/月 | 39件以下 |
| 居宅介護支援費Ⅱ | 527単位/月 | 684単位/月 | 40件以上59件以下 |
| 居宅介護支援費Ⅲ | 316単位/月 | 410単位/月 | 60件以上 |
(2018年度介護報酬改定より)
利用者39人までは減算はありませんが、40人以上になると報酬が半額に減算され、60人以上になると更に減算されます。
つまり「顧客が多ければ多いほど儲かる」のではなく、「顧客が多ければ多いほど儲かりにくい」報酬システムになっているのです。
減算とは言っても、損失が発生するわけではありませんが、あまりに過剰な人数だと、行政から「業務の質や運営基準に準拠しているか」を疑いの目で見られてしまう「やぶ蛇」になってしまうリスクさえあります。
ケアマネ業務だけではない
1人で独立して居宅介護支援事業所を運営するわけですから、「ケアマネ業務だけしていればいい」というわけにはいきません。
ケアマネ業務の他に、経理や事務もしなければなりませんし、経営者として経営もしなければなりません。
最近、「とある社協のケアマネが利用者の印鑑を無断で作成し不正に使用していた」という報道もありましたが、いくら忙しかろうと印鑑を貰い忘れようと、そんな人間性を疑われるようなことはやってはいけません。
ケアマネ業務以外にもやることが沢山あるのですから、1日の労働時間は必然的に長くなるでしょう。
売上は良くて50万円
利用者を40人以上持つと減算されるのと、そもそも余程のスーパーマンでもない限り、1人で経理も経営もしながらそう多くの利用者を適切にケアマネジメントができないでしょうから、1ヶ月の売り上げは良くて50万円前後でしょう。
「50万円」と聞くと多いように感じるかもしれませんが、「良くて50万円」です。
また、あくまで売上ですから、純利益ではありません。
その50万円の中から必要な固定費や経費を支払っていかなければなりません。
例えば
|
などになります。
上手くやりくりが出来れば、雇われていた頃と同じか、少しは多い給料を手にすることができるかもしれません。
但し、単純計算してもケアマネ1人で売り上げ100万円を達成することが不可能であることは明らかですし、多くの場合は50万円を確保することも難しいと言えます。
名も無き事業所は困難事例を回される
新規で立ち上げた名も無き独立型事業所のケアマネ(経営者)が、利用者を獲得するためには地域包括支援センターや病院などへ営業に行き、良好な関係を築いておく必要があります。
しかし、そういった所は同じ法人内に居宅介護支援事業所が併設されていることが多く、名も無き事業所には併設事業所が敬遠するような「困難事例の利用者」ばかりがおこぼれのように回されたりします。
断れば利用者も獲得できませんし、仕事を回してくれた先の心象も良くないでしょう。
そもそも、運営基準で「正当な理由なく居宅介護支援の提供を拒否できない」とされています。
引き受ければ実績として認めて貰えるため、今後もどんどん困難事例の利用者を紹介されることになります。
「人に使われるストレス」からは解放される
独立開業すれば自分が経営者になるので「儲からない上に過酷」ではあるものの「人に使われるストレス」からは解放されるでしょう。
それは独立する上での大きなメリットでもあります。
自分のペースで仕事が出来ますし、職場の人間関係にうんざりすることもなくなります。
最後に
今回は、「ケアマネ資格を取って居宅介護支援事業所を開業したらどうなるのか」ということについて解説しました。
利益を増やしていこうとすれば、自分以外のケアマネを新たに従業員として雇い入れて規模を拡大させていくか、複合的に「通所介護事業所(デイサービス)」や「訪問介護事業所(ホームヘルプサービス)」を同列法人で運営してく手段が考えられます。
しかし、デイサービスや訪問介護事業を開業するにはコストが掛かりますし、そもそも人材を確保できなければ運営が出来ません。
また、今後居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネに限定していく国の方針から、「主任ケアマネを確保できない程度の弱小事業所は不要」「事業所数を増やさず大規模な事業所に集約していきたい」という思惑が見え隠れしているのではないでしょうか。




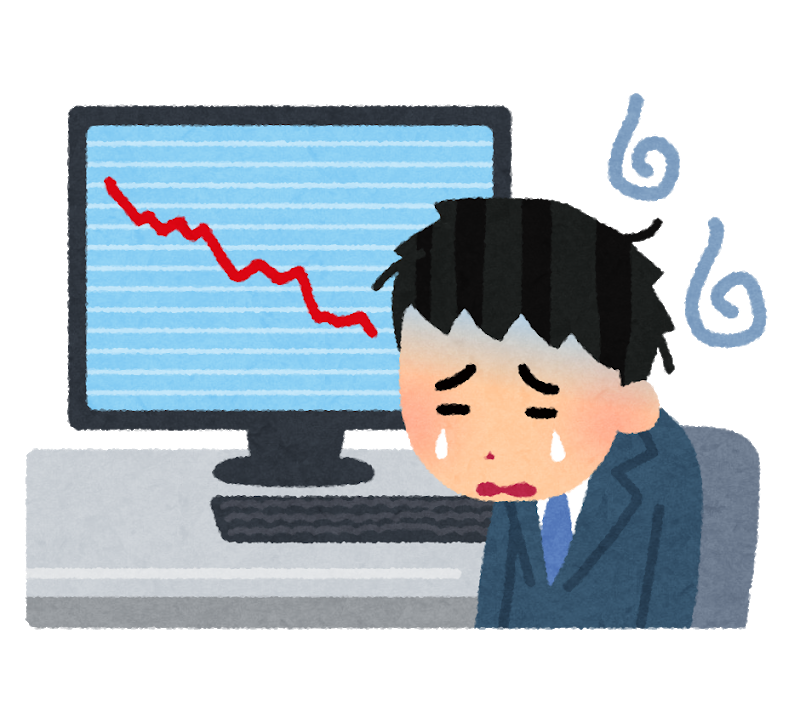


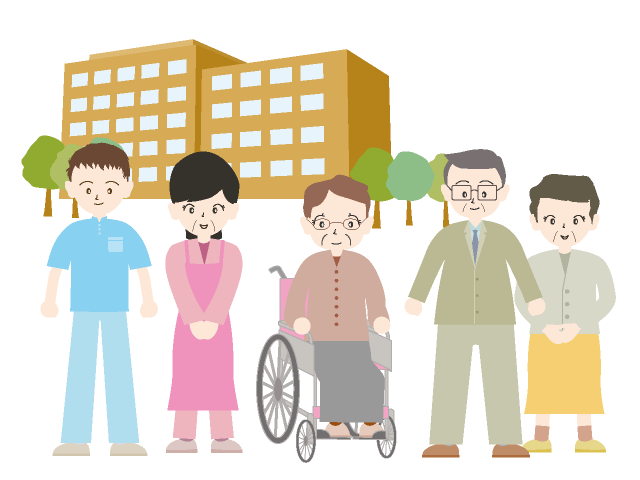

コメント
その人家庭環境色々あったんですよ、両親とも過去色々あって…
で、人に認めてもらいたいって欲求と自分が一番できるという考えでして…実際利用者や家族より自分の評判ばかり気にしているのが見え見えだったんで…。独立するって言った時も生まれそだった地域の為に役にたちたいって言ってましたが格好つけてるの露骨に感じたのでヤバイなとは思ってました。
だから最近は関わらないほうがいいと思って連絡してません。
>かずさん
そうなのですね。
まぁ色々な人がいますからねぇ。。。
何だかキラキラ系の人と被っていますね。
ホントそうですね。その人『もう二度とやりたくない』って言ってました。借金は完済したみたいですが。
そういえば僕の知り合いの別のケアマネが去年独立しようとしてし損ねました。老健でケアマネしててそれから社協でケアマネしてたんですが上手くいかなくて民間の事業所でケアマネしてましたが、実家で独り暮らししてる母親をみながらケアマネしてました。母親けっこう年で要介護状態になったのと、子供達が就職したのをきっかけに以前から独立したい気持ちがあったのと一人でやれば母親の面倒もみやすくなると考え実家の物置小屋を改装して色々手続きして準備も整えてさあ独立!のひと月前兄弟に強く反対されなくなく独立諦めてまた別の事業所でケアマネしてます。独立の為にかなり貯金きりくずしたのでかなり落ち込んだというかやさぐれちゃいました。『今まで自分に母親の面倒みさせておいていきなり口出ししてきて、変な家族だよ!』と吐き捨ててました。でもそのケアマネ人柄がちょっと癖ありで独立しても失敗してたと思います。だから独立しなくて良かったのかなと思ってます。独立前に他の事業所とトラブル起こしてますし、(受け持ってた利用者に今度独立するからまた利用してくださいって言って預けた先の事業所にその事がバレて訴えるって言われました)仲介に入ってくれた地域包括の主任ケアマネに『俺どうすればいいんですか!』ってキレて食ってかかるし…『俺が独立失敗したのいうなよ!俺が何言われるかわからないから!』って僕にキレてくるし、アホかって思いました。
>かずさん
ケアマネ独立の準備までして開業直前で兄弟に反対されて断念というのも変な感じですね。
直前で兄弟に反対されるというのはある意味準備(根回し)不足でもありますし、兄弟さんもやっても失敗するということがわかって口を挟んだのかもしれませんね。
どちらにしても逆ギレをするような人が独立してケアマネをやっていくのは難しいでしょうね。
お久しぶりです。
僕の父方の祖父母を担当してくれたケアマネさんはケアマネになった時の事業所辞めて個人でやってて、人柄も良くて気さくで話しやすい評判の良いケアマネさんでしたが借金がかさみ(300万くらい)このまま続けてたら返せなくなると泣く泣く辞めたそうです。僕も相談員時代にけっこうお世話になりましたが…。
今は看護師で頑張っていますが、ひとりでやるとなると大変だなと改めて思いました。自分の取り分がマイナスの時もあったそうです。
>かずさん
お久しぶりです。
コメントありがとうございます^^
やはり相当キツいでしょうね。
構造上、儲かる仕組みではないのでやりたい人も少ないでしょうし実際やっても苦しいばかり。
そうなってくると資格そのものの魅力も薄れてしまいますね。