2020年7月2日に行われた政府の規制改革推進会議をまとめた答申の中に、「介護職員の業務範囲について医行為との線引きを明確化していく」という議題も含まれていました。
★参照元:内閣府ホームページ「第8回 規制改革推進会議 議事次第」
平成17(2005)年に「医療行為ではないもの」「介護職員が行える業務」について明確にした解釈通知を厚生労働省が出していることで、「介護職員が一包化してある内服薬を服薬介助することは医療行為ではない」ということについては過去記事でもご紹介しました。
ちなみに、平成17(2005)年に発出の通知は以下の10項目になります。
【医療行為ではないもの】
- 水銀体温計・電子体温計による腋下の体温計測、耳式電子体温計による外耳道での体温測定
- 自動血圧測定器により血圧測定
- 新生児以外で入院治療の不要な者へのパルスオキシメータの装着
- 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について専門的な判断や技術を必要としない処置(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)
- 軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
- 湿布の貼付
- 点眼薬の点眼
- 一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)
- 坐薬挿入
- 鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助
【引用元】厚労省解釈通知(医政発第07256005号)「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」
同通知では、更に医師法や歯科医師法、保健師助産師看護師法の規制対象外となる6項目も以下のように明記されています。
【医師法や歯科医師法、保健師助産師看護師法の規制対象外】
- 爪切り、爪ヤスリによるやすりがけ
- 歯ブラシや綿棒、または巻き綿子などによる歯、口腔粘膜、舌に付着した汚れの除去
- 耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
- ストマ装着のパウチにたまった排泄物の廃棄(肌に接着したパウチの取り替えを除く)
- 自己導尿の補助としてのカテーテルの準備、体位の保持
- 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸
【引用元】厚労省解釈通知(医政発第07256005号)「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」
(追記)
また、私の不勉強で知らなかったのですが、平成23(2011)年に日本オストミー協会から以下の照会を厚労省にされており、「条件を満たせば介護職員でもストーマ装備の交換が可能」となっています(Twitterのフォロワーさんに教えて頂きました、本当にありがたいです)。
肌に接着したストーマ装具の交換については、局長通知において、原則として医行為ではないと考えられる行為として明示されていないため、介護現場では医行為に該当するものと考えられているが、肌への接着面に皮膚保護機能を有するストーマ装具については「ストーマ及びその周辺の状態が安定している場合等、専門的な管理が必要とされない時には、その剥離による傷害等のおそれは極めて低いことから、当該ストーマ装具の交換は原則として医行為には該当しないと考えるが如何」
この照会に対する厚労省の回答は、
- 合併症がなくストーマが安定している場合で専門的な管理が必要とされない場合にはストーマ装具の交換は医療行為にはあたらないとの判断
- ストーマ装具交換には教育を受けたものが望ましいとの見解
という内容が示され各都道府県にも通知されました。
ですから、上記により”追加で”「条件を満たせばストーマ交換は医療行為ではないため介護職員が行うことが可能」ということになります。
(追記ここまで)
これらの通知により、かなり医療行為との線引きが明確になりました。
しかし、既に15年経過していることもあり社会情勢や疾病構造やニーズの変化、国民の知識の向上や医学・医療機器の進歩などが生じてきているため、再検討や再整理を行う必要がある時期にきており、介護職員が安心して、尚且つ、円滑に業務が行えることを目的とした提言のようです。
どんな業務に線引きが必要?問題点は?
現状の介護現場で、どんな業務に線引きの必要性があるのでしょうか。
また、線引きをすることで発生する問題点はどういうものがあるのでしょうか。
以下で確認していきたいと思います。
業務範囲に線引きが必要な行為とは?
今回の規制改革推進会議で議題に上がった「介護職員の業務範囲の明確化」ですが、資料を確認すると以下のようになっています
【出典】https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20200702/200702honkaigi01.pdf
この資料によると、
- 酸素マスクのずれを直す行為
- 膀胱留置カテーテルのバッグから尿を破棄する行為
などは医行為になるのかならないのかがハッキリしていないため、介護職員が実施を躊躇してしまうことが多いのでハッキリ明確にさせましょうという内容です。
この文書を読んだ私の率直な感想は、
「あれ、それらの行為は躊躇することなく普通にやっていたけど実は医療行為かもしれないことだったのか」
というものでした。
確かに、酸素マスクもバルンカテーテルも医療的な措置になるので、酸素マスクのずれを直したりバルンパック内の尿を破棄する(もっと言えば尿やカテーテル内の状態確認など)行為も医行為となる余地は十分にあり得ます。
以前、「トイレ誘導を減らせるから入所者の多くに施設側の都合でバルンカテーテルを留置させているという介護施設があるという話を見聞きした」という記事を書きましたが、もしも尿の破棄が医行為だということになれば、その施設は今後介護士よりも看護師を大量に雇わなければならなくなってしまいますね。
他には、現状で医行為となるため介護職員が行えない業務として、
- インスリン注射
- 血糖測定
- 摘便
- 褥瘡の処置
- 点滴の管理
- 手動の水銀血圧計での血圧測定
などがあります。
それらは判断に迷うことも躊躇することもなく「介護職員が行えない」とわかるのですが、他に医行為か判然としない業務が今思い浮かばないので、もし「こんな業務やこんな時に判断に迷うよ」というご意見があれば教えて下さい。
問題点
業務範囲を明確に線引きしていくことはありがたいことですが、
- 酸素マスクのずれを直す業務
- バルンバッグの尿を破棄する業務
が「医療行為である」となった場合は問題が発生します。
何故なら、老健施設などは別として多くの介護施設では「夜間帯に看護師は居ないから」です。
夜間は介護職員だけが常駐し業務を行っており、看護師はオンコール体制になっている場合が殆どではないでしょうか。
そんな人員配置の中で、上記の業務が行えないとすると利用者の生命にもかかわってきます。
となると、「夜間も看護師を1人以上常駐させなければならない」ということになりますが、現実問題として多くの施設が苦慮するのではないでしょうか。
そもそも、政府は「テクノロジーを駆使して介護現場の人員配置を削減していく」という介護現場の実情に沿っていない方針を立てているのですから、それとも矛盾してしまいます。
ですから、恐らく上記の業務は「医療行為ではない」ということになるのではないかと予想しています。
最後に
今回は、政府が規制改革推進会議の中で15年ぶりに介護職員の業務範囲を明確化させようという提言が議題にあがっていることについて記事を書きました。
何でもかんでも政府を批判するつもりはありませんが、最終的な結果は現場職員の働き方や日々の業務に密接に関わってくるため注視していきたいところです。
今回の業務の明確な線引きだけでなく、全てにおいて「介護現場の実情に沿ったもの」になることを願っております。







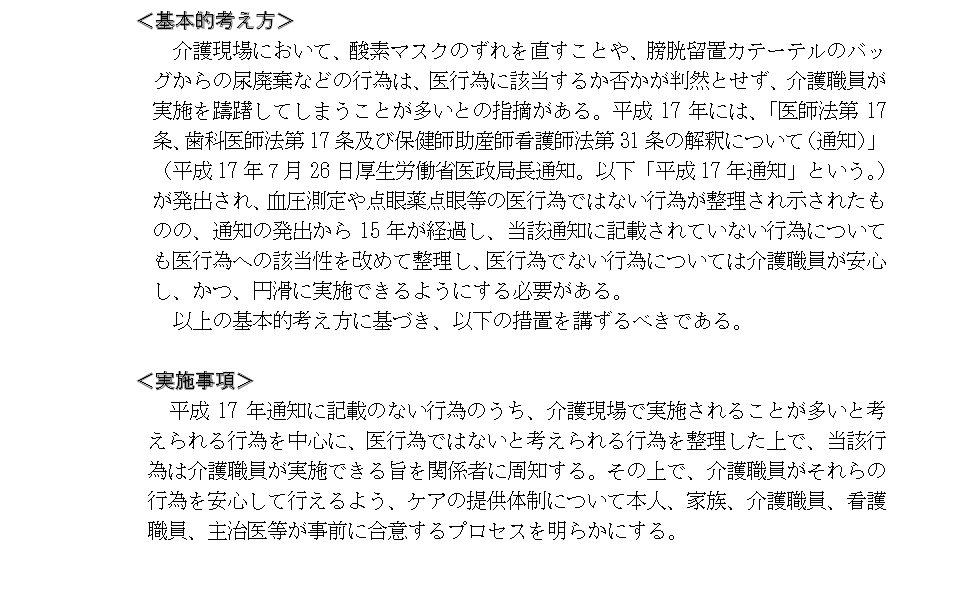






コメント
①決まりは改定できるものですが、ここに来て政府が医療行為を定義しにかかると言うことは…また医療行為の緩和をしようとしているのでしょうかね?なんて勘ぐってしまいます。
詳しくは覚えていませんが、(こちらのブログで)そんな感じの記事を見て、吸引以外にも増えるのかと驚いた記憶がありますが、たぶん勘違いですね。
広義では介護も含まれると思いますが、とある考え方に「(市場に対して)政府の介入は悪影響しか及ぼさない」や余計なことしかしないなんて言及されていますが、まさにその通りだなと感じますね。
ほしい緩和はそこではないのですが、現場の声よりも(特に悪徳)経営者のほうが金や距離感の関係で声が政治に届きやすいから、そりゃ傾きますよね…妄想ですが。
ただしこれは想像の域を出ませんが、この線引きがよくも悪くもただ線引きしただけなのか?(悪用)他意はあるのか?
②管理人さんの施設は点滴がありますか?
有る場合は明言を避けていただいて良いのですが、私はブラック介護施設に勤めた際に驚きました。病院でもないのになんで点滴を指しているのかと。
初めて勤めた施設では全然見たことがなく、あっても1回(数年間で1日(半日))だけあったかどうかでしたのでなおさら。
ちなみにどちらも重度が入所対象でしたが、こうも違うのかと。
もちろんブラックですから、当時調べた上で本記事でも触れられていますが点滴関係って触っちゃいけないはずなんですよね。
法律上は百歩譲ってこのままであってほしいところですとしつつ、明言を避けますが、人体に刺すのも、抜くのもいけないことですよね・・・
当時調べた時点での知恵袋などのサイトもさらに昔のバックナンバーしかありませんでしたが、その場に直面してしまった人、(業務命令で)やってしまった人の問いも少なくなく、なお闇を感じました。
当時の直属の上司含む先輩に少し伺うと、同業他社転職も私なんかよりも多いもののどうやらそのほとんどでやらされてきたと言います。うち1人はそんなこと言ったって(業務命令だから)仕方がない(略)やるしかないのだからとドライでしたが。
結局、どっかのうるさい家族なんかにバレてクレーム入れられて、介護職としての点滴業務はそれなりには縮小しました(違法行為はなくなった)。
ただ、これの嫌なところは過去にも職員側がこれを指摘したことがあるようですが、その利用者家族のクレームがあるまで継続されていたことなんです・・・
③この線引きは悪い緩和のために悪用されるような気がしなくもなく、規制に動く気は薄い気がしますが、個人的に吸引を医療行為に戻してほしいと思います。
資格も経験もないから、介護をやらざるを得なかったとしてもすぐやれとは言われない身の上のつもりですけど、端で見てきてアレ負担大きいですからね。準備から後片付けまで。
生命の選別とかって少し騒がれていますが、吸引と誤嚥性肺炎を少なくとも介護現場から除名してほしいです。それを前提として法的な死亡証明資料の提供の名の下にカメラ監視設置をすればいいと思う。トイレから居室なんて。
医療行為ではないですが、民間企業が勝手にやっている?レクリエーションも廃止にしてほしい。
レクについては対象とする介護度合いによって一概には言えない面もありますが、介護業務から吸引や記事の後半部分などの医療行為ぽいものや違法行為をなくして、レクもなくす。
さらに、ユニットケア(笑)を廃止で従来型に戻せばある程度は人材が集まるとは思うのですがね…雇う気があるならば、と思います。
>めど立てたい人さん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
①について
「明確な線引き」というものが、業務負担を軽くするものではなく逆に緩和して負担が重くなる可能性は十分にあるでしょうし、今までの経緯もあり勘繰ってしまいたくなる気持ちもよくよく理解できます。
現場の実情に沿った緩和や線引きであって欲しいものですね。
②について
過去に家族の希望で点滴を受けていた利用者がいました(点滴をする利用者の頻度はごく稀です)。
もちろん主治医の指示のもと、看護師が点滴をしていましたし、介護職員は一切触ってはいませんでした。
点滴の抜き刺しは完全に医業ですから介護士がすると完全にアウトですし、余程のことがない限りこれからもそれは変わらないことでしょう。
但し、「点滴のセッティングや後始末は介護士でもOK」というような線引きがされる可能性は十分にありますね。
③について
最終的にどうなるかはわかりませんが、とにもかくにも現場の実情に沿った内容であって欲しいですね。
確かに、医療行為以外で線引きをして欲しい点は多々ありますね。
まずは「やるのかやらないのか」で、「やるのならばそれに見合った制度や体制の整備が必須」でしょうし、「やらないのならば現状でも、ある程度は体裁が保てたり負担軽減や効率化が可能」となるでしょうね。
今現在は、どっちつかずのごちゃ混ぜにしてしまっているからおかしくなってしまっているのでしょうね。
徘徊や暴力暴言、自傷行為がある利用者って、ある程度を超えれば医療的な介入が必要だと思うのだけど、そこに言及してほしい。
例えば、利用者の認知症の自立度がMと医師が診断したら、介護職は関与できず(笑)、医療職が対応するとか。(爆笑)
で、同一労働同一賃金がはじまったけど、介護職の仕事量は、看護師よりはずっと多いと思う。なのに看護師資格があるだけで、看護師の給料が介護職より高いのはおかしいと思う。
少人数で大人数の利用者の入浴をしたり、レクや体操をしたり、送迎に出たり・・という業務内容を考えると、どう考えても介護職の方が看護師よりは給料は高くないとおかしいと思う。
もちろん介護職でも仕事しないできない奴もいるし、看護師でも働き者な人もいるので、そこは個々に評価して給料を払わないといけないと思う。
常勤の介護職だからいくら、看護師資格があるから+何万円、という時代ではないと思うのですけど。
>デイちゃんさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
確かに問題行動のある利用者の対応の線引きを明確にして欲しいですね。
介護職の業務範囲は本当に広いですよね。
介護福祉士の給料が看護師の給料に迫りつつあるようですが、介護職の場合は夜勤をして夜勤手当が入ってやっとですからね。
個々の評価にしないとサボった者勝ちになってしまうので同意です。