現在や過去に介護現場で働いている介護職員の皆様であれば既にご存知でしょうから当たり前のことになりますが、
- 世間一般の人
- これから介護職員になろうと考えている人
などにとっては、「利用者の排便量はどうやって確認しているんだろう」と疑問に思われている人もいらっしゃるかもしれません。
確かに、介護現場では「普通便〇〇g」などという記録を行っています。
この「〇〇グラム」は一体どうやって計測しているのでしょうか。
もしかしたら、「その都度、量り(重量計)に乗せて計測しているのか?」と思われるかもしれませんが、結論から言えば「完全なる目分量」です。
今回は、「介護現場では利用者の排便量はどうやって確認しているのか」ということについて記事を書きたいと思います。
介護現場での排便量の確認方法
では早速、介護現場の排便量の確認方法について詳しく解説していきたいと思います。
卵1個分を50gとして換算
介護現場での排便量は「鶏の卵1個が約50gである」ということを基準にして相当量を目視で確認しています。
つまり、利用者の排便を介護職員が目視して、その量が「卵何個分であるか」を基準にして「排便〇〇グラム」という記録を行っています。
卵2個分であれば100g、卵3個分であれば150g、卵4個分であれば200g…という感じです。
ここで大切なのは、「各介護職員の卵1個の大きさの認識に違いがあると排便量の認識も職員ごとに違ってきてしまう」という点です。
今までのライフスタイルの中で、ご家庭でいつも「大きめの卵を使っている場合」「小さめの卵を使っている場合」で50gの認識にズレが生じてしまいます。
ですから、共通認識として「普通サイズの卵を想定して排便量を量ること」が必要です。
※この基準は事業所ごとで違いがある可能性がありますので、あくまで目安としてお考えください。
排便の状態(種類)が変わると益々目分量が必要
介護職員は、排便量だけでなく、排便の状態(種類)や色なども確認・観察を行っています。
排便の状態とは、つまり便状です。
普通の形がしっかりとある便なのか、軟らかい便なのか、下痢便なのかという確認になりますが、この便状が形を留めていなければいないほど排便量の確認も難しくなります。
何故なら、「固形ではない便や水様の便が卵何個分に相当するのかを脳内で換算して排便量に換算する必要があるから」です。
介護の仕事はなかなか想像力が必要な仕事なのです。
トイレで流してしまった場合はどうするのか
介護職員は、利用者の排便をトイレやポータブルトイレやオムツ内で確認をします。
しかし、排便量や排便の有無を確認したくても確認できない場合もあります。
例えば、
- 利用者が流してしまった
- 水洗トイレの自動洗浄機能で自動的に流れてしまった
などの場合です。
その場合は以下の確認を行います。
- 利用者が意思疎通が可能であれば排便の有無や大体の量を尋ねてその旨を記録(利用者の勘違いの場合もありますが、発言の事実をありのままに記録します)
- 流れてしまったトイレ内の便付着の有無や利用者のお尻を拭いた際の便付着の有無で確認
つまり、介護職員が目視で確認できなかった以上、はっきりとした排便量はわからないものの、「排便があったのか無かったのか」というところまで可能な限り迫っていきます。
以上が、介護現場での利用者の排便量(排便の有無)の確認方法になります。
最後に
今回は、「介護現場では利用者の排便量はどうやって確認しているのか」ということについてご紹介しました。
排便量は卵1個分を50gに換算して目分量で確認をしています。
介護現場での排便量の確認方法をご存知ない方のご参考になれば幸いです。




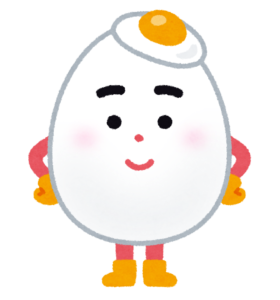
コメント
私は今まで便は、「バナナ一本分・硬さ普通」というように記録してました。
あとは形状によって「にぎりこぶし大・かため」とか。
ナースさんは浣腸とかの後で、茶わん一杯・軟便とか書いてましたね。
便の色も確認はしますが、異常があると、その前にあきらかな体調不良があるような気がします。
鉄剤飲んでると真っ黒になって、はじめは大腸がんだとかあわてた気がします。
量や色は正確にわからなくても、腸の音とか、排便後のおなかのはりで、スムーズに排便できてるか確認してはいますね。
あと、腸の調子が悪くなると、便が滞留して便の成分が再吸収されるからか、なんとなく体から便の臭いがしてくるような・・。
施設だと「この人〇日便出てないわ」とか管理できるけど、デイは毎日利用しないので、排便ができてるかわからないんですよね。
寝たきりの利用者が、腸が便で全部つまって胃まで逆流してた人もいました。
入浴介助時のおしりを洗った時に、便がタオルに付着すると、「この人便は出てるんだな」とはわかるんですけど。
そうそう、1月になりましたが、案の定、特定処遇改善金は支払われていませんでした。
「従来の処遇改善とまとめて払いま~す。でも赤字なのでやっぱり払えませ~ん。」とかになりそうですね。
>デイちゃんさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
やはり事業所(若しくは事業所形態)によって確認方法が異なるのですね~
特定処遇改善加算…一体なんだったのでしょうね。
支払うもののボーナスで調整したり…。
きっと都市伝説のひとつなんでしょうね><
在宅だと、高齢者の食事&水分量のインとアウトが結構適当で、介護5寝たきりの小柄な90歳の女性に息子が家でめちゃご飯食べさせてて、めちゃ太ってたりするんですよ。で、デイを毎日利用してて、息子が「毎日浣腸してください」とか言うんだけど、おかしいでしょ?みたいな。
90歳で寝たきりなら1日の必要摂取カロリーは1000キロカロリーくらいだし、食事も少量でいいはず。少なくともおやつはいらないと思うんだけど。
で、本人はものすごく太ってて、呼吸とかも苦しそう。あんまり太ると内臓脂肪で肺や心臓が圧迫されるから。
ついてる医師も何も言わないみたいで。でも毎日浣腸はおかしいよね~。
会社が訪問の拠点分割をしまくってるんだけど、それは特定処遇改善加算をみこしたものだと思うんですよね。訪問は加算率が高いし。
加算を取ってその金を吸い上げてまた拠点を作る。新しく出した拠点は当然赤字だから、処遇改善は払いませーんみたいな感じ。
で、介護業全体でみると、訪問の赤字のせいで全体も赤字になったんで、処遇改善は払えませーんってからくり。
処遇改善加算を使って新事業所をあけてやろうっていうあさましい考えですね。
>デイちゃんさん
胃瘻の人でも不自然に太っている人いますねぇ。
特定処遇改善加算は事業所の内部留保や処遇改善以外で使ったらアウトのはずですが抜け道もあるのでしょうかね。