前回の記事で、介護現場でのリスク報告書は多い方が良いのか少ない方が良いのかについて解説しました。
まだ読んでいない人は下記記事をチェックしてみて下さい。
結論だけ言うと、「ヒヤリハットなどの気づきは多い方が良くて、アクシデントは少ない方が良い」という内容です。
しかし、そうは言ってもなかなかヒヤリハット報告書や気づきを増やしていくのが難しい状況があるのも事実です。
例えば、
- リスク報告書をネガティブなものとして捉える事業所や職場の雰囲気や環境
- 気づくことで報告書作成や対応などをしなければならず業務負担が増える
などになります。
リスク報告書をネガティブなものとして捉えている事業所は考え方を正していく必要があることは前回の記事で述べた通りですが、では、気づくことで業務負担が増えてしまうという現実はどう解決していけばいいのでしょうか。
今回は、業務負担に焦点を当ててヒヤリハット報告書や気づきを増やしていくための業務改善について記事を書きたいと思います。
ひやり・はっと報告書や気づきを増やしていくための業務改善とは?
ヒヤリハット報告書や気づきは多い方が良いと言うものの、業務負担や精神的な負担が増えてしまうことも事実です。
では、どうすれば増やしていくことができるのでしょうか。
実際に私が働いている職場で実践している方法をご紹介したいと思います。
業務負担や精神的負担とは
そもそも、どのような業務負担や精神的負担が発生するのでしょうか。
一番大きな負担が「報告書の作成そのもの」です。
何故なら、報告書を作成する場合は、
- 発生日時
- 発見者(作成者)名
- リスクの区分
- 発生状況
- 発生後の対応
- 家族への連絡の有無とその内容
- 改善策
などを正確、且つ、具体的、且つ、わかりやすく記入していく必要があるため、時間が掛かってしまう上に精神的な負担も大きくなってしまうからです。
では、報告書を作成する際の負担を軽減するためにはどうすればいいのかを次にご紹介します。
ヒヤリハットを2つに分けて「気づき」にする業務改善
ヒヤリハットを更に2つに分けて、
- ヒヤリハット
- 気づき
という形にします。
1の「ヒヤリハット報告書」は今まで通りですが、2の「気づき報告書」は非常に簡易なものにしています。
また、気づきはヒヤッとハッとしなくても、自分が「これは新たな気づきだな」と感じた内容を箇条書きのようにして記入していきます。
例えば以下のような感じです(※利用者名と職員名は仮名です)。
| 発見日時 | 利用者名 | 内容 | 発見者 |
| 5月18日(月)16時30分 | 田中 次郎 | 歩行時に靴のかかとを踏んで歩いていた。声掛けし靴を履き直してもらう。 | 介護職員A |
| 5月20日(水)23時05分 | 山田 花子 | 訪室するとベッドに端座位になり靴を履こうとしていた。トイレの訴えあり介助を行う。 | 介護職員B |
| 5月21日(木)7時30分 | 笹木 トメ | 朝食の声掛けをするが「まだ眠い」と言われ様子を見る。 | 介護職員C |
|
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
些細なことでも何か気づいたら、「発生日時」「利用者名」「内容」「発見者(対応者)」だけ箇条書きのように記入して書き溜めていきます。
この報告書には、リスク報告書のように「家族連絡」や「改善策」は不要です。
それだけでも業務負担がグッと減り、気づきの件数を増やしていくことが可能なのではないでしょうか。
そして、リスクマネジメントとして「職員間で情報の共有」も格段にしやすくなります。
ヒヤリハットと気づきの判断が難しいという問題
ヒヤリハットとは別に「気づき」という項目で箇条書きのように書き溜めていけば気づきの件数を増やしやすく、尚且つ、職員間で情報共有もしやすいということを前述しましたが、欠点があるとするならば「ヒヤリハットと気づきの判断が難しい」という点です。
両者の決定的な違いは、ヒヤリハットは「ヒヤッとしたりハッとした出来事」であるのに対して、気づきは「ヒヤッとしたりハッとしなかったがひとつの気づきになるような出来事」ということになります。
ですから、職員本人が「ヒヤリとしたか否か」ということを判断基準にするのが良いように思いますが、そうした場合「職員の価値観」「度胸や経験」などによって同じ出来事でも判断が変わってきてしまう可能性が出てきます。
例えば、利用者が1人で歩こうとしているのを発見した場合、職員Aはヒヤっとしたけど職員Bはヒヤっとはしなかったということは往々にしてあり得ます。
では、何を判断基準にすればいいのでしょうか。
判断基準①:リスクマネジメント委員会の判断に委ねる
事業所内にリスクマネジメント委員会があり、最終的な集計や個々のリスクの分析や改善策の検討をしています。
気づきとして提出した内容について、リスクマネジメント委員会で「これは気づきでいいのかヒヤリハットになるのか」という判断を出してもらい、もしも気づきからヒヤリハットに変更する必要があると言われれば修正や訂正や書き直しをする方法です。
修正や書き直しを指示されるた場合、あまり良い気はしませんし手間も掛かってしまいますが、あっても1件か2件でしょうし最初から全てをヒヤリハットとして報告書を作成するよりも業務負担や手間は少ないはずです。
判断基準②:上司やリスク委員などに聞く
気づきかヒヤリハットかの判断に迷った場合、上司やリスクマネジメント委員会の委員になっている人に「どちらになるのか」を尋ねてみるのも良いのではないでしょうか。
「その判断が絶対正しい」とまではいかないまでも、判断の信頼度は高くなりますし「上司やリスク委員などに相談してから作成した」という既成事実も作れます。
大切なことは「気づきを増やしてアクシデントを減らすこと」
気づきとヒヤリハットの判断に迷ったり、修正をしなければならないかもしれないという問題はつきまといますが、気づきを増やすことで最終的に目指しているのは、「アクシデント(事故)を減らすこと」です。
その目的のための過程として、
- 気づきやヒヤリハットの報告件数を増やす
- 職員間で情報を共有する
- 改善策を検討し実行する
- 実行した結果を分析したり評価する
- 改善策の精度を上げていく
という積み重ねをしていくことが大切なのです。
そのためにも多くの気づきが必要なのですから、職場内で気づきも含めたリスク報告書を作成・提出しやすい環境づくりをしていく必要があるのです。
最後に
今回は、業務負担に焦点を当ててヒヤリハット報告書や気づきを増やしていくための業務改善について記事を書きました。
最終的に「アクシデントを減らしていくこと」が目的ですから、まずは「現状の取り扱いがその目的から外れていないか」ということから考えていくことが必要です。
例えば、ベテラン職員にとってはいつものことでも、新人職員にしてみれば「目新しい発見」「大きな気づき」という場合もあり得ます。
個人的にはそういう内容であっても、その職員にとって気づきであったのなら「最終的にアクシデントを減らしていく1つの過程」として気づきであげて貰えればいいと思っています(この辺の判断は事業所や職場で変わってくるでしょうが)。
気づきを増やしていくための業務改善の1つの案としてご参考になれば幸いです。




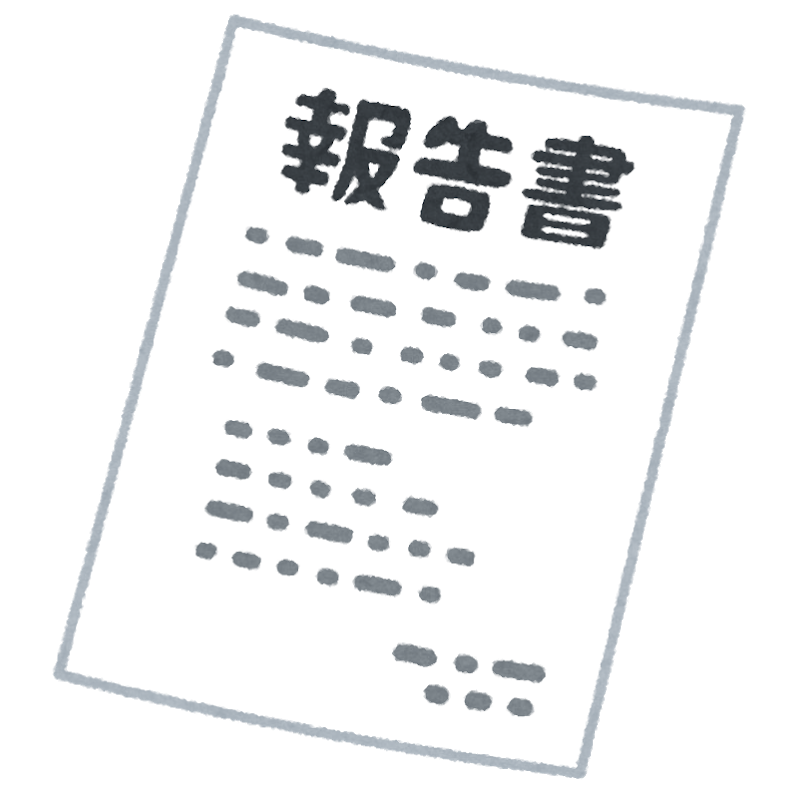






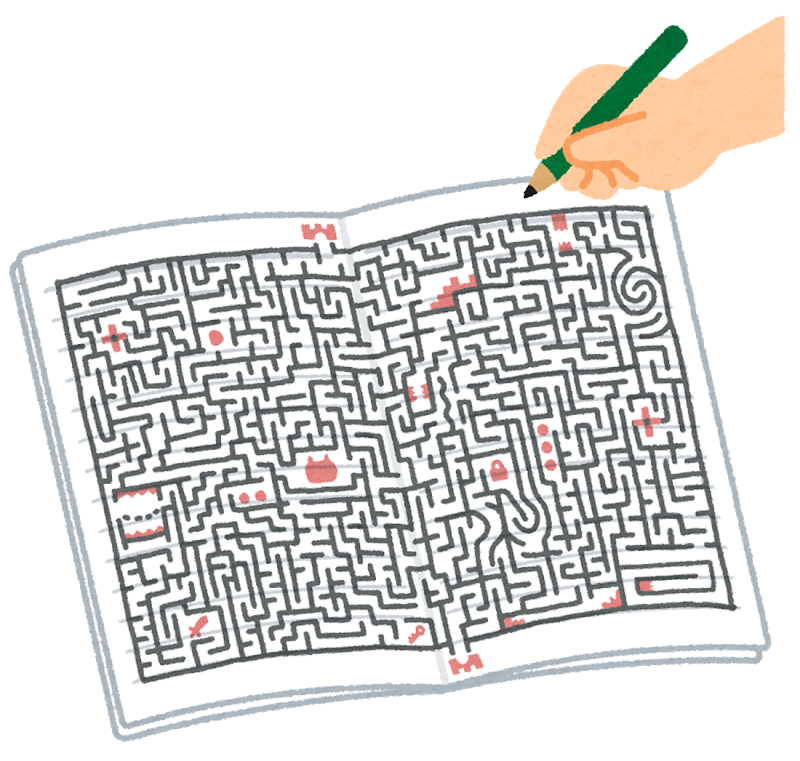

コメント
結局、利用者さんにこまめに関わって、様子を観察し、異変があったらすぐに対応するのが大事なんですよね。で、その対応方法がより適切な方法がないか検討すれば、業務がより改善されるってわけで。
なので、利用者さんにこまめに関わらないかぎりは、気づきがどうのとか業務改善がどうのとか言っても、すべてが机上の空論だと思いますね。
私のデイのカスタッフなんて、基本利用者はスルー&フル無視。とにかく座ってサボってる。中身のない記録を汚い字で書いてる。ww
利用者がむせてゴホゴホ言ってようが、お茶がなかろうが、まわりを見まわしていようが、ボケーっとしていようが、うなだれていようが、しんどそうにしていようが、白目むいてようが、とにかくフル無視。放置。スルー。アウトオブ眼中。ww
もちろん、利用者全員と話してないスタッフばかり。なにしろ、管理者の書いてる目標が「利用者全員と話をしよう」だって。何それ。バカなの?アフォなの?お客様と話しないで何の仕事するの?
もうね、介護の仕事って何なの?って感じですよ。サービス業なのにサービスせず座ってるだけってどんな職業だよ?って感じですよ。
まあ私はとりあえず、自分のできる範囲で自分の分担の仕事のみしようと思っています。実際は他のとこまでしてるけどね。
でも今はスタッフはいつも配置基準以下で、私は一人で15人くらい入浴してるんだけど、よく事故にならないな~って思いますね。ま、事故が起きても人員を配置基準以下にしてる会社のせいだけども。
Q「なぜその事故が起きたのか?」
A「人員配置基準以下の違法なサービス提供体制であり人不足だったため」
Q「その改善方法は?」
A「法律を守ってスタッフを適正数配置し、利用者の状態をこまめに確認する」
もうこのデイ、終わってます。ww
>デイちゃんさん
コメントありがとうございます^^
そういうおかしなスタッフも一応は人員配置の中に繰り込まれているので余計にやっかいですね。
でも、その人たちを入れても基準を満たしていないとすれば違法なサービスになりますね。
自分を守りながら働くしかないですね><
気づき報告書は経過記録と共通するところがありますね。
「入浴拒否が強いが、入浴すると言わずにちょっと来てもらえます?と脱衣室に誘導して、その後服を脱いで下さいと言えば、服を脱いでスムーズに入浴できた」とか、普段の行動や介助方法の工夫などを書いておけば、記録としても十分具体的だし、他のスタッフにとっても役に立つと思います。
また月一のケアマネへの状況報告書も、日々の記録を具体的に書いておけば、それを参考にして利用者の状況や介助方法を具体的に書けるし、ケアマネの信頼も得られると思うのですが。
そのためには、とにかく利用者とこまめに関わらなければダメなわけで。関わって観察して声かけて、介助しなければ、何もわからないし、記録も書けない。
なのにデイのカスタッフ達はず~っと座って意味のない記録を書いてるんですよ。「穏やかにすごされました」とか。もうアフォかと。
で、日々の記録がいい加減なので、当然ケアマネへの状況報告書もいい加減なうすっぺらいものしか作れない。うすっぺらな記録しかないんだからしょうがないよね。
「お変わりありません」「特変ありません」・・って、報告書もらう意味ないじゃない。どういう状態で変わりがないのか?とか具体的に書かないと。
まともに書いてるのは私だけみたいで、気がつくと私だけ状況報告書の担当が10人とかになってる。他のカスタッフは常勤でも3人とかなのに。
他のカスタッフが書いた報告書は「内容がなさすぎる」「誤字脱字がひどい」「不適切な表現がある」「日付すら間違ってる」「担当ケアマネの名前すら間違ってる」「字が汚すぎる」ので書き直しばかりで、ケアマネに渡しても「内容がひどすぎる」「もっと具体的に書いてくれないと」って言われるらしい。当たり前だ。ww
そうやってケアマネの信頼を失っていくから、利用者が減って行くんだよ。当然の帰結。
でも日々利用者とこまめに関わってる働き者のスタッフは、記録物も増えるから、どんどん仕事が増える一方かもしれませんね。
どこかで何かを減らさないと。ww
>デイちゃんさん
返信ありがとうございます^^
そうですね、気づき報告書があればケアマネへの月次報告書などでも情報共有しやすくなりますね。
そして、おっしゃるようにいつもちゃんとしている職員ほど仕事や負担が増えてしまうのも事実ですね。
家族への連絡ノートにも、「入浴は娘さんがそこで入ってきてと言ってたのでと伝えると、すんなり入ってくれた」「脳トレはそろばんが得意だったと言われ、計算問題を熱心にされていた」「絵手紙に取り組まれて、きれいにできたので入口の壁に貼ったら喜んでくれた」「歩行訓練時は左足が出にくくて、ご本人様は気圧のせいかな~と言われていた」「ボールゲームでは思い切りボールをたたいて、ストレス解消できたと喜ばれていた」とか書いて伝えれば、家族も「結構いろいろやってくれてるんだな」「ここを利用してよかったな」と思うと思うんですよね。
でもそうじゃない。
「ご利用ありがとうございます。バイタル落ち着かれて入浴しました。機能訓練もされました。」で終わり。
は?それ今日じゃなくても書けるんじゃない?もう文章コピーしてノートにはれば?みたいな。
もう何の誠意もやる気も感じられない。だから利用者減るんだよ。
でも管理者的は何も分かってなくて、「重度寝たきりの奴を毎日利用させて売り上げ稼がなきゃ~」って言ってたわ。違うよね~。それじゃ永遠に利用者増えないって。
ま、私は毎回入浴になってるので、記録の類は全くしません。記録係じゃないので。
フロアのカスタッフが一日中座ってサボって、内容のない記録を書いてる。
それが諸悪の根源ということに、管理者は首になる前に気づけるかな。ww
>デイちゃんさん
おはようございます。
返信ありがとうございます^^
おっしゃる通りですね。
毎回コピペではあまり意味がありませんよね。
管理者の「気づき」に期待したいですね。