過去の記事で、介護施設での夜勤のタイムスケジュールと仕事内容について解説しましたが、今回は「日中の介護現場業務」について記事を書きたいと思います。
日中は殆どの利用者が活動していますし、夜勤にはない「行事」や「入浴介助」などの業務も加わり介護施設そのものが活気を帯びてきます。
ユニット型の介護施設では、ドア1枚で隣り合った2つのユニットのことを「協力ユニット」と呼び、この協力ユニットの利用者20名に対して共通の介護職員が介護を行います。
ですから、日中には「早番」「日勤」「遅番」の最低3人の介護職員が出勤していないとマトモに1時間の休憩など取れない状態に陥ってしまいます。
そもそも、利用者20人に対して介護職員3人でも業務負担は大きいのです。
では早速、介護施設での1日の流れ「タイムスケジュールと仕事内容」を詳細に解説していきたいと思います。
介護施設の日中の流れ「タイムスケジュールと仕事内容」
施設によって多少の違いがあるかもしれませんが、早番の勤務時間が「7時~16時」、日勤の勤務時間が「9時~18時」、遅番の勤務時間が「11時~20時」という感じの介護施設が多いかと思います。
今回は日勤の勤務時間である「9時~18時」を対象としてタイムスケジュールと仕事内容を解説していきます。
9時00分~9時30分「夜勤から引き継ぎ、情報収集、朝礼」
日勤者の出勤時間は夜勤者の退勤時間と同じである場合が多いです(若しくは30分間の重複時間がある)。
ですから、ほぼ入れ違いとなります。
ここで、夜勤者から引き継ぎ事項を聞いたり、記録などを確認して情報収集を行います。
朝礼も9時から始まるので、早番職員か日勤職員のどちらかが参加することになります。
9時30分~11時30分「排泄介助、入浴介助、行事等、配茶」
この時間帯から忙しくなっていきます。
随時、排泄介助を行いながら入浴介助も始まります。
また、水分摂取をしてもらうためにコップにお茶を入れて配ります。
行事やイベントなどがある場合は利用者を案内したり誘導したりします。
行事なんて、敬老会やクリスマス会など年に数回しかないように思われるかもしれませんが「ほぼ毎日」あります。
友愛訪問、各種ボランティア、リハビリ職による集団体操、活け花などなどがあり、何も無い日の方が珍しいかもしれません(施設によります)。
もちろん参加する利用者もいれば参加しない利用者もいます。
それを判断して振り分けていきます。
11時頃に遅番職員が出勤してくるまで「早番職員と日勤職員の2人」でこれらを行います。
遅番が出勤して「やっと職員3人」が揃います。
行事等があった場合は利用者を送り出して終わりではないので、終わればお迎えに行きます。
11時30分~13時00分「昼食準備・配膳・介助、口腔ケア」
この時間になると厨房から昼食が運ばれてくるので、準備や盛り付けや配膳を行います。
ユニットケアでは「食事をユニットで盛り付けたり準備することこそ家庭的で人間らしい豊かな生活」という良いのか悪いのかよくわからない方針があるので、運ばれてきた食事をユニットで介護職員が盛り付けをして配膳していきます。
遅番が出勤してやっと職員が3人揃ったのですが、そろそろ早番に休憩を取ってもらわないと休憩が取れなくなってしまったり、他の職員に休憩が回せなくなってしまいます。
ですから、早番職員に「11時30分~12時30分まで休憩」を取ってもらいます。
つまり、結局はまた2人の職員で業務を行うことになるのです。
食事を配膳した後は、介助が必要な利用者に介助を行いながら、他の利用者の摂取状況や状態などを見守りしたり声掛けしたり観察したりします。
手が止まっていたり、食事をこぼしてしまっていたり、ムセや喉詰めなどの異常を早期発見するためです。
12時30分頃になると大方昼食が終わるので片づけに入ります。
但し、食事介助が必要な利用者の人数が多い場合はまだまだ昼食は終わりません。
12時30分になると早番職員が休憩を終えて帰ってきますが、次に日勤職員が「12時30分~13時30分まで休憩」に入ります。
そうなると、現場はまた早番と遅番の2人だけで回すことになります。
昼食があらかた片付いたら、順次口腔ケアを行っていきます。
13時00分~13時30分「排泄介助、臥床介助」
昼食と口腔ケアが終わると、随時、排泄介助をしていきます。
午睡(お昼寝)や臥床(ベッドで横になる)が必要な利用者は食後お部屋へ誘導しベッドに寝てもらう介助を行います。
13時30分になると日勤職員が休憩から帰ってくるので、ここでやっと本当に3人の職員が揃います。
13時30分~15時00分「記録の入力、入浴介助、処置、シーツ交換」
この時間までの利用者の生活記録や食事量などを入力していきます。
午後からも入浴介助がある場合は、職員1人が入浴介助に当たります。
他の職員2人は看護師と一緒に処置が必要な利用者への処置のフォローをしたり、共同生活室で過ごしている利用者の見守りや適宜の対応のほか、シーツ交換などを行います。
午後から入浴介助が無い場合は、早番や日勤の休憩時間をこの時間にずらすのもありだと思います(その辺は臨機応変に)。
15時00分~16時00分「おやつ準備・配膳・介助、排泄介助」
15時になると厨房からおやつが運ばれてくるので準備をして配膳します。
またこの時間から遅番職員が「15時~16時の休憩」に入ります(遅番の休憩時間は昼ご飯には遅すぎるし晩ご飯には早すぎる中途半端な時間帯になりがちです)。
つまり、また職員が2人で対応することになります。
「おやつや排泄介助がひと段落してから遅番が休憩に行けばいい」と思われるかもしれませんが、16時になると早番の退勤時間になるため、16時までに遅番が休憩を取らないと「早番が残業をする」か「日勤が遅番の休憩中1人で20人の利用者の対応をする」かのどちらかになってしまいます。
ですから、現場に職員が3人いる間に休憩を取る必要があるのです。
職員2人でおやつの介助等を済ませたあと、随時、排泄介助を行います。
16時00分~17時30分「記録の入力、ゴミ捨て、レク」
16時になれば早番が退勤していくため、日勤と休憩から帰ってきた遅番の2人で業務を行っていきます。
この時間までの記録の入力やユニット内のごみを集めて外にあるごみ捨て場まで持って行きます。
時間に余裕があればレクリエーションや体操なども行います。
そして、17時になれば夜勤者が出勤してきます。
日中の出来事や伝えておく必要があることなどを夜勤者に申し伝え引継ぎをします。
夜勤者のタイムスケジュール等は下記記事をご参照下さい。
17時30分~18時00分「夕食準備・盛り付け…」
17時30分を過ぎた頃に厨房から夕食が運ばれてきます。
準備や盛り付けをして18時頃に利用者に配膳をするのですが、日勤職員の勤務時間はここで終了です。
その後に待ち受けている食事介助や片づけ、口腔ケア、排泄介助、就寝支援は遅番と夜勤者の2人で行っていくことになります。
そして、20時に遅番も退勤すれば「完全なワンオペ夜勤の始まり」です。
本当に介護職員の皆様、お疲れ様でございます!
最後に
今回は、介護施設での1日の流れ「タイムスケジュールと仕事内容」について解説していきました。
記事に書いた内容は、あくまで通常業務の範囲内ですから、この他にも各種会議や委員会、家族や知人の面会、体調や状態の悪化や急変など書ききれないほど色々なことがあります。
通常業務だけでもこうして具体的に見ていくと、「職員が3人いると言っても殆どの時間は職員2人で対応している」ということがお分かり頂けましたでしょうか。
これは、「職員も休憩が必要だから」です。
マトモに1時間の休憩を取ると職員3人の配置ではこのような結果になります。
そして、業務負担が大きく目が回るような忙しさのため、レクにまで手が回らなかったり、ゆっくり利用者の話を聞くということが困難な環境と現実があります。
それを補うように介護職員自らが苦肉の策として「休憩を取らない又は短縮する」「利用者の見守りをしながら休憩を取る」などの劣悪な職場環境があったりもします。
また、休憩が取れるように業務の順番ややり方を見直したり、休憩を取る時間や取り方を工夫したり努力をされている事業所もあることでしょう。
しかし、相手は利用者という人間なのですから全てが計算通りに上手くいくことの方が少ないのです。
介護施設での日中業務を適切で健全に行っていこうとするならば、介護職員のためにも利用者のためにも「最低でも4人の出勤者が必要」です。







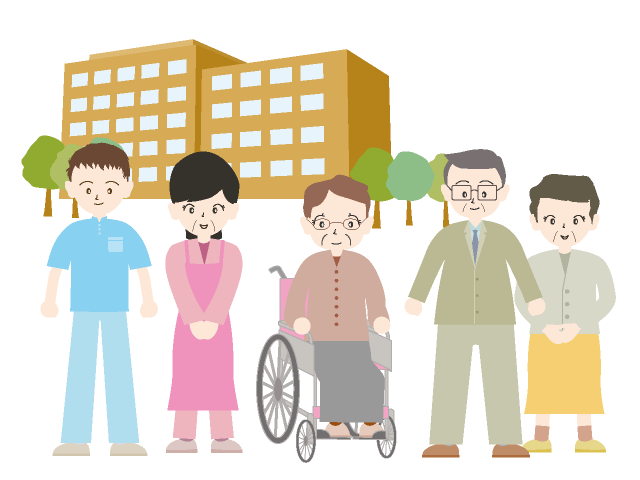

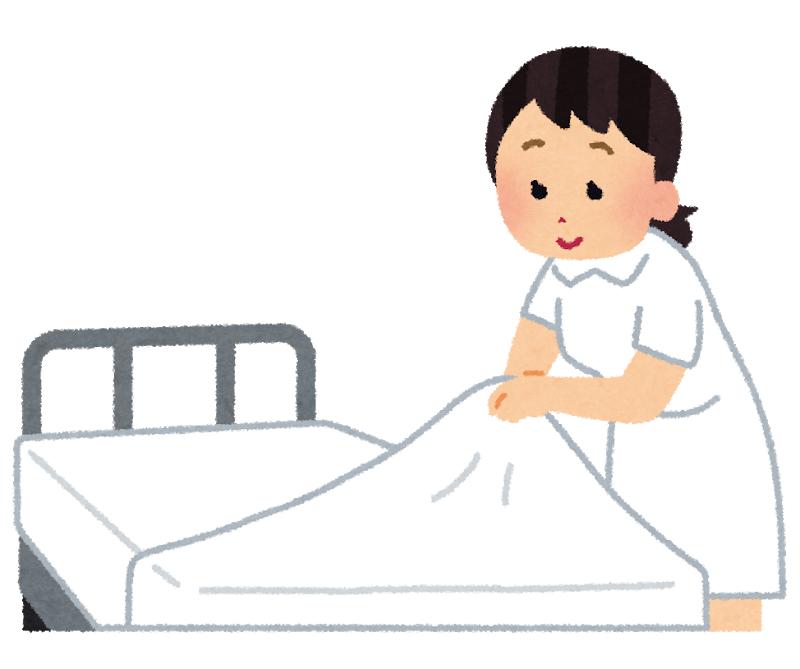





コメント
ユニット特養です。スタッフがいなさ過ぎて泣きたいです。
自分が早番で夜勤者が来るまで一人ってこともあります。
休憩時間は隣のユニットに見守り、排泄介助などをしてもらいます。
最近はそういう状況もなくなってきましたが、今度は妊娠ラッシュで
身体介護が出来ないスタッフがいたり…大変です。
もし何かあったらどうしようと気を遣うばかりです。
>もこもこさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
早番出勤をして日中1人の介護現場はひどすぎますね><
負担と責任ばかり重くなって給料は1人分…では何のために働いているのかわからなくなりますね。
心中お察しいたします><
病院って、入院したら有無を言わさず病衣を着なきゃいけないでしょ。
患者とそうでない人を見分けるためとか、なんかあった時すぐ処置できるようにとか、理由はあるけど。
寝たきりの拘縮してる人に、「ご本人様がなじみのある衣類を」って言って、昔その人が着てたきつ~い服を着させたりとか、意味がわからない。今状態違うじゃんよ。
食介ですが、食事の配膳・食介・下膳の時間帯で、2時間程度働いてもらうシルバーさんとか雇ったらどうかな?と思うんですけど。事故があるかもしれないけど、スタッフが足りない状態でバタバタやるよりはいいですよね?まあ人件費の問題があるからダメか・・。
話は変わりますが、シーツって必要ですかね?
ベッドマットにボックスシーツかぶせて、敷きパッド+部分ラバーでいい気がします。そうすれば、汚染時の交換も楽な気がしますし、定期の交換も瞬殺です。
シーツって結局下に汗とか浸透してますよね?あれ意味ないよな~。ちなみに父親のグループホームはシーツはないですね。
まくらもまくらカバーとかしてますけど、シーツと同じ布なので汗とかまくらに浸透するので意味ないよな~、まくらはラバー地のまくらカバーにしたらいいのにって思ってます。嘔吐した時とかでも大丈夫だし。
>デイちゃんさん
色々本末転倒であったり、砂上の楼閣であったり、支離滅裂な状態ですよね。
シルバーさんに介護補助員として業務に入ってもらえたら助かりますね。
シーツはボックスシーツでいいと思いますよ。
うちも片側だけボックスになっています。
ユニットの勤務は身体的な負担も大きく勤務時間も不規則ですから本当に大変ですよね。僕がデイの相談員をしていた特養では早番が6時半~15時半、日勤が9時半~18時半、遅番が13時~22時、夜勤が22時~7時で明けの日が公休です。だいたい近隣のユニット特養もそんな感じです。夜勤の次の日早番だったら明けの日は寝るだけです。遅番の次の日が早番だったら家に寝に帰るだけです。遅番の連チャンもきついです。
一時期ユニットのシフトに入っていたんですが(相談業務しながら)生活リズムが乱れて身体もきつかったですね。
あと、ユニットリーダー研修にいったいユニットリーダーのなかには研修に行った先の施設の影響をもろ受けちゃう人もいますね。そういう人に限ってキラキラになるんですよね。入所者と一緒に米炊いて料理作るんだとか、でもそのリーダーのユニットはほぼ全介助の入所者でした。そんなわけでそのリーダー顰蹙かってましたね。状況見ろ!あんたなんかリーダーの資格ないなんて言われてました。
>かずさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
16時間夜勤もきついですけど、明けの日が公休にされる9時間拘束8時間夜勤もきついですね><
明けの日なんて寝たら1日が終わってしまいますから。。。
理想ばかりの研修に影響されるリーダーは嫌ですね。
現実が見えないと全員が不幸になります。
今目の前にある現実を見据えて業務を行う事が大切ですからね。そのリーダーは経験があまりなくて上の受けがいいだけでリーダーになった人だから周りが見えてないんですよね。
悪い人ではないんですが…。
ユニットでも従来型でも人手が足りてて余裕持って仕事できて1日が無事に終わるのが一番の理想ですが今の介護業界の現状みたらそれが実現難しいですね。
>かずさん
返信ありがとうございます^^
所詮介護現場のリーダーなんてそういう決め方ですよね。
いや、ほんと安全第一です。
何かあったら責任を負わされるだけでなく裁判沙汰にもなりかねませんからね。
ユニットって悲惨ですよね。
利用者は少ないかもしれないけど、スタッフも少ないから、消耗戦。
常に自分が対応できない状況を作られる。
いつも1人分以上の作業力を求められ、ストレスを与え続けられる。
食事もユニットでご飯を炊いたり、おかずを盛りつけたりとか、意味があるの?
ご飯の炊けるにおいがするのがいいんだって言うけどさ~便臭と消臭剤の臭いしかしないけど?www
入浴も一人のスタッフで一人の利用者を入れ続けるから、常に消耗戦。一人やるのにものすごい時間がかかる。超重度ばかりというのもあるけど。
多対多の介助方法なら、誘導・着脱・洗体に分かれて、誘導が利用者連れてきたら着脱に渡して服を脱がせた後、必要なら移乗を二人でして、洗体が洗う。その間にまた新しい利用者を誘導が連れてきて、着脱が服を脱がして、洗体が浴槽から出してきた利用者と交換。・・みたいな、ある種流れ作業だけど、安全にスピーディーに入浴介助ができるのに。
スタッフも、あと何分で何人とか目標が分かったり、対応が難しい利用者がいても二人で声かけてなんとかなったり、新人にもこうやった方がいいよ?って教育したりできるのに。
ユニットはそういうよさを全部捨ててる。
オムツ交換も、「オムツカートはないです。随時交換で。」って絶対やり忘れるでしょうに。
ユニットは、もう非効率なおかしなことだらけだったけど、やっぱりそういう施設ってスタッフは全然定着せず派遣ばっかり使ってたわ。
スタッフが定着しない時点で、アットホームな介護なんて無理なのに。
もうユニットは失敗だったと認めて、全部多少型にした方がいいでしょうに。
>デイちゃんさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
全くもっておっしゃる通りですね。
人員が確保できない以上(いや、人員配置基準さえおかしい)、ユニットケアは破綻してしまっていると言えますね。
介護職員の自主的(?)なサービス残業と休憩の削減で何とか首の皮一枚つながっている状態です。
ユニットで食事を盛り付けると食事形態のミスも発生しやすくなりますし、良いとこなしですね。
明らかにユニットケアは失敗していますね。
それを認めないところが闇深いです。
食事は厨房で盛りつけてお膳にのせてカートで持ってくれば、作業時間が短縮されてその分食介に時間を使えますよね。
入浴はもうユニットが~とか言わないで、施設全体で入浴担当者出して、入浴しなきゃいけない人全員を流れ作業で入れていく。
特養って今は介護3以上だから、全介助の人ばかりでしょう。ますます誘導着脱洗身とか役割分担して、流れ作業でやらないとダメでしょうね。
とにかくスタッフをユニットに細かくわけず、入居者は全部個室だけどやり方は多床室的な感じで、大勢の利用者を大勢のスタッフで対応するって考え方に変えないと、スタッフは消耗していなくなってしまうでしょうね。
どうしてもユニットと言うなら、グループホームみたいに9名とか利用者を少人数にしないとダメでしょうね。
>デイちゃんさん
返信ありがとうございます^^
そうですね。
特養は協力ユニットとか言って20名の利用者を被せてきてしまうのは負担が大きすぎますね(要介護3以上ですし)。
現状では流れ作業化、全ユニット職員共通化が一番の改善策でしょうね。
高齢者って必要摂取カロリーが少ないでしょ。だから3食食べておやつまで食べる必要あるのかな?っていつも思うんですよね。
デイで寝たきり90歳だけど3食とおやつ食べる人がいて、もう太りすぎててパンパンで呼吸も苦しそう。で毎回浣腸してるとか意味がわからない。明らかにカロリーオーバーだと思う。
10時に軽めのブランチ、17時に夕食の二回でどうかな。おやつは糖尿の人が多いから中止で。ww
衣服もご本人様が今まで着ていたものを・・とかやめて、ダボッとした前あきの服にしたいよね。ルームウエアに。ww
寝たきりの人は、前あきの病衣+肌着+オムツみたいな感じで。ww
あと、入浴介助をなんとかできませんかね?
夏の間はシャワー浴のみにするとか。w
利用者のためにもスタッフのためにもなり、医学的な根拠がある改善・・できるといいんだけど。
>デイちゃんさん
こんばんは~
返信ありがとうございます^^
介護保険内であればどこかでラインは引いて欲しいですね。
医療保険でも保険内で全ての治療ができるわけではないように、介護保険でも線引きをしないと割に合わない感が強くなるだけですね。
正に悪循環です。