介護の仕事はストレスの多い職場だと言われたり、実際問題、人材不足であったりするわけですが、「入職しても退職していってしまう」「入職者がいないのに退職者が順番待ちをしている」などという状況も往々にしてある状態です。
もちろん、そうではない介護事業所も存在するのでしょうが、大半は「悪循環が止まらない事業所ばかり」ではないでしょうか。
この悪循環を阻止するためには、職場環境を改善していったり業務の見直しをしていく必要があります。
しかし、問題が山積みすぎてどこから手をつければ良いのかさえわからず迷走してしまうことも珍しくありません。
ですから、改善をしていく上でのひとつの基準として「介護職員が会社から守られていると感じる環境であること」ということを意識しなければなりません。
ここを失念したりすっ飛ばしたりしてしまうと、一体誰のための職場環境なのかわからなくなってしまいますし、従業員さえ守れない会社には何の魅力も価値もありません。
今回は、介護職員が「会社から守られている」と感じる環境でなければ悪循環は断ち切れない、ということについて記事を書きたいと思います。
現状の悪循環
現状で介護現場にある問題やストレスの元凶として、
- 利用者からのハラスメントや暴力
- 家族からの理不尽なクレーム
- 上司や同僚との人間関係やハラスメント
- 過大な業務負担
- 理想と現実のギャップと温度差
などなど様々です。
そして、「悪循環」が止まりません。
悪循環①「上司が不甲斐ない」
前述したような問題が発生することは仕方がないとしても、それに対して上司や会社が何らかの改善をしていかなければ悪循環は止まりません。
何も改善できないばかりか「我慢しなさい」「不平不満ばかり言うな」「技術や能力が未熟だからだ」などという責任転嫁や丸投げをされると更なるストレスが発生し悪循環が加速していきます。
悪循環②「職場全体のモチベーションが下がる」
上司も含め、会社が何も助けてくれず守られていないことがわかると失望してしまいます。
失望してしまうとモチベーションが下がり良い仕事などできません。
そうなると、ミスを連発してしまったり人間関係が更に悪化する等、どんどん追い詰められていきます。
不平不満を言わずに頑張ってみても、頑張れば頑張るほど納得がいかない気持ちが強くなってしまい心のバランスを崩してしまいかねません。
ここでモチベーションが下がるのは、当人だけではありません。
それを見聞きした周りの介護職員たちも「自分達は会社に守られていない」「結局は使い捨てのボロ雑巾にされて終わりだ」という失望感が伝染していき、職場全体でモチベーションが下がっていくことになります。
そうなると、「職場全体で良い仕事ができなくなる」という悪循環に陥ってしまいます。
悪循環③「自己防衛するか退職するか」
職場全体でモチベーションが下がった状態になると、介護職員たちが考えるのは「自分で自分を守りながら働いていく(自己防衛)」か、「見切りをつけて退職する」かのどちらかになります。
自己防衛をしながら働くにしても、やられたり被害を被ってから防衛しても遅いわけですから、「やられる前に」「被害を被る前に」防衛することになります。
つまり、利用者や家族や上司や同僚に対して「警戒しながら働く」こととなり、伸び伸びと働くことができなくなってしまいます。
しかし、「会社が守ってくれない」以上、仕方がない苦肉の策と言えます。
一方で、ストレスを溜め込みながらそんな窮屈な働き方ができないという判断をした介護職員は「見切りをつけて退職していく」ことになります。
退職者が出れば、益々人員不足となり、職場環境が改善するどころか悪化していきます。
そして、残った介護職員は益々頑なになっていき、上司もその状況に手をこまねくばかりでどうにもできず悪循環が止まりません。
悪循環④「利用者への対応が悪くなる」
退職者が続出し、どんどん人員不足となっていき、残った介護職員も自己防衛で精一杯です。
そんな職場環境では利用者への対応も悪くなっていきます。
- 利用者に接する時間や頻度が減る
- 排泄の訴えなどがあっても長時間待たせることになる
- 手が回らず介護事故が発生する
- 起こってはならないような介護事件が発生する
などの悪循環に陥ってしまうことになります。
大なり小なり全国の介護事業所で似たような状況があるのではないでしょうか。
そして、再びこの状況に耐えかねた誰かが上司に相談したり改善を訴えたりする場合は、「悪循環①」に戻って同じ悪循環が繰り返されることになります。
悪循環を断ち切るために「介護職員を守る」
介護現場の悪循環についてご説明しましたが、では、どうすればこの悪循環を断ち切ることができるのでしょうか。
根本原因は「会社が介護職員を守れていないから」
介護現場で様々な問題が発生してしまうのは当然あり得ることです。
しかし、悪循環が発生してしまう根本的な原因を考えていくと、「最初の段階で上司や会社が有効な解決を図らなかったから」ということがわかります。
つまり、「初動に失敗する頻度や確率が高いために悪循環が発生する」と言えます。
もっと言えば、「会社が介護職員を守れていないから悪循環が発生する」のです。
一度発生してしまった悪循環を断ち切ることはなかなか難しくなり、下手をすればどんどん加速していき手がつけられない状況に陥ってしまいます。
ですから、「初期の段階で」「悪循環が発生する前に」断ち切ることが重要です。
どうやって「介護職員を守る」のか
では、どうすれば「介護職員を守ることができる」のでしょうか。
問題が山積みすぎて個別具体的に挙げていくのは難しいですが、ポイントとしては以下の3つになります。
- 初期の段階で適切な判断を行い手を打つ
- 介護職員の報告や相談を放置したりあしらったりしない
- 介護職員が「会社に守られている」と感じる職場にする
まずは、全スタッフに「無記名」で「会社に守られていると感じるか」というようなアンケートをとってみてはいかがでしょうか。
その結果が、介護事業所の悪循環指数を示していると言えます。
最後に
今回は、介護職員が「会社から守られている」と感じる環境でなければ悪循環は断ち切れない、ということについて記事を書きました。
介護現場では大なり小なり問題は発生するものですから、その問題そのものに対するアプローチとその問題によって発生する悪循環へのアプローチのどちらも非常に大切です。
既に悪循環が加速してしまっている場合は、それを断ち切るためには相当な労力と思い切った改革が必要になってきます。
介護職員を大切にできないのに利用者を大切にできるはずがないのですから、悪循環について「原因と結果」をよくよく検討してみることが大切です。



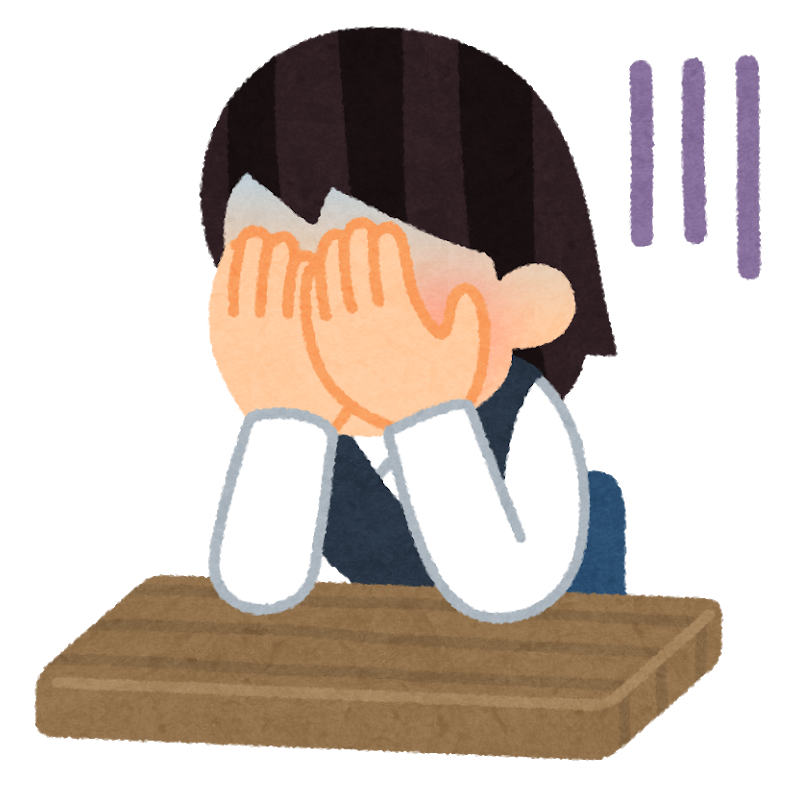


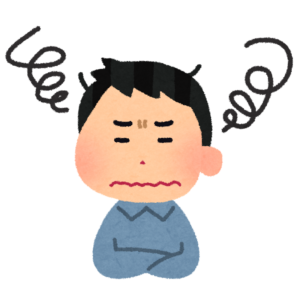


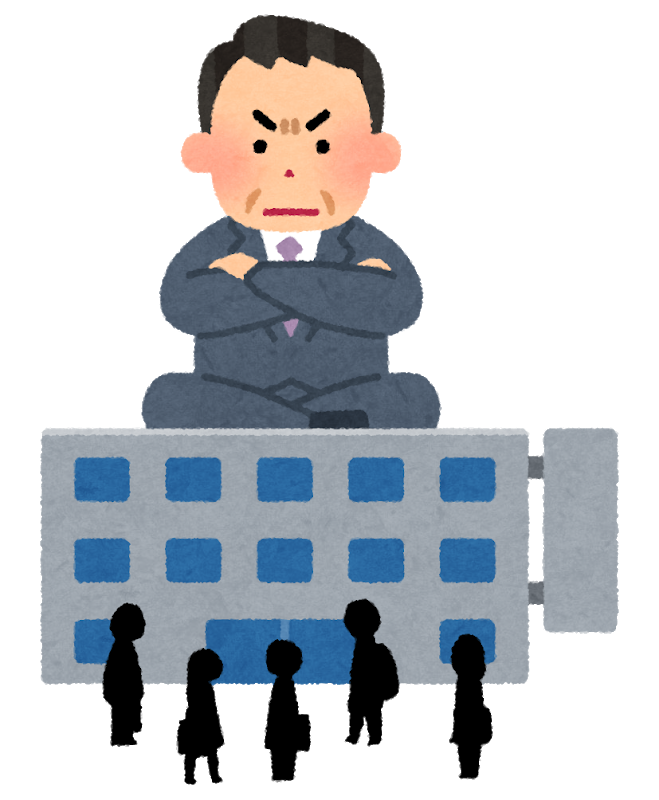



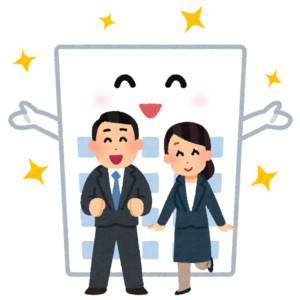
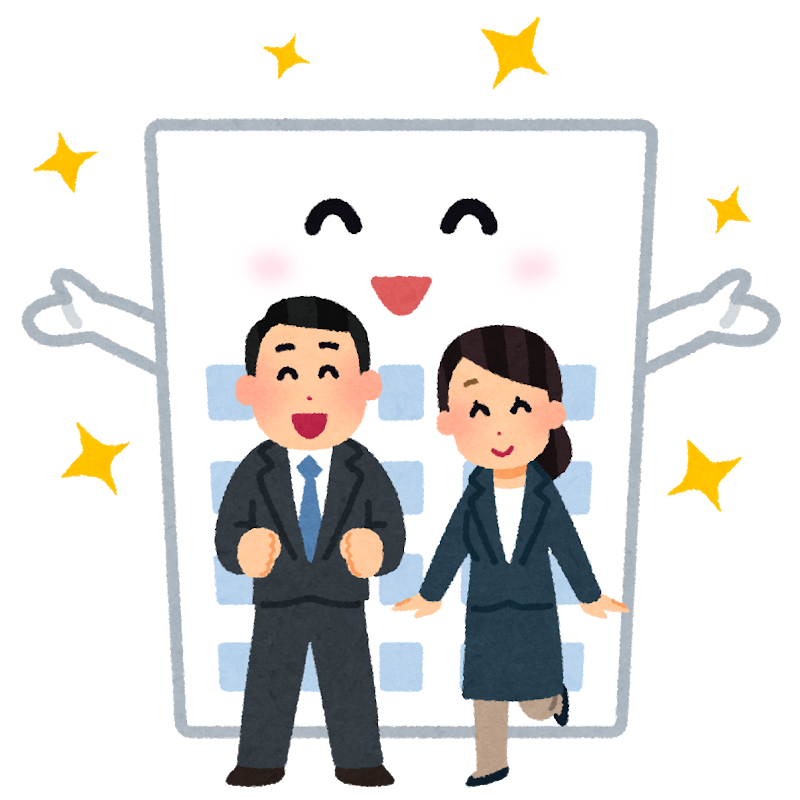

コメント
会社から守られてるって感じることは・・・皆無です。ww
もうね、会社ってヘルパーをこき使うしか考えてないですよ。
できもしないことやらせて、「できないのはお前が悪い」とタイムカード先押し。
検食でスタッフから金をとって、その金で、利用者追加利用させるためのお楽しみ昼食会開催。
利用者が亡くなったら、お香典でヘルパー一人100円ずつ徴収。
あげくの果てには、「休日希望なくして好き勝手にシフト組めるようにしよう」とか言い出した。
そんなことしたら、ヘルパーみんなキレてやめちゃうじゃんよ。って思ったら案の定全員やめて営業不能になりましたとさ。めでたしめでたし。
でも会社って本当にバカだね。失敗してもそこから学習しないもの。
私はいつも、また同じバカなことしてるわ~って、笑いながら見ています。
そのバカなことした結末が、自分に降りかかってくると腹が立つけど、そうじゃなきゃ笑い話で終わるからね。
>デイちゃんさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
会社に守られていると感じることが皆無の事業所が多いという事実が人員不足の原因なのではないかと思っています。
検食とお香典でお金取るのはひどいですね。
タイムカード先押しも完全なるサビ残…。
そうですね、学習能力ないんでしょうね。
そして、介護職員やヘルパーに対して「愚痴や不平不満ばかり」などと上から目線で言うのですから堪りませんね><
おかしな業界です。
昔は検食は金とってなかったんですよ。
前管理者が「あくまでみなさんの自主的な行動ってことで」とか言い出して、検食も金をとるようになったんですよね。
だったらお前が毎日検食して金払えばいいじゃん。冷凍食品のまっずい飯になんで金払わなきゃなんないんだよ。
ちなみに私は、検食は断っています。非常勤なので。www
香典は、利用回数が多い利用者は会社から出るのですが、利用回数が少ない人は出ないんです。
したら「葬式に行くときお香典がいる」とか管理者が言い出して、「〇〇さん亡くなったんで一人100円です」とか言い出した。
あのな、葬式行くならお前が勝手に出せばいいじゃん?
今はとられなくなりましたが。金返せ。ww
あと、ギフトの購入を強制されますね。
前はお中元とお歳暮くらいだったのが、今は毎月ある。父の日のギフトだの敬老のギフトだの。
事業所にノルマがあって、例えばデイは20万とか。
前は「必ず全員一つは購入してください」とか書いてあって、買わない人の名前がホワイトボードにずっと書かれてあったり。
昔の管理者はアフォみたいに強制してたけど、今はあまり言わなくなりましたね。
私は買う時は、やってもいないレク準備などをしたと勤務をつけて、その金で買ってあげてました。ww
ちなみにノルマ達成したら、どんどんノルマを高くされていきます。うちのデイは最終的には100万とかになってました。www
勤務シフトも昔「休日希望をなくす」とか強硬なこと言ってたけど、それはなくなりました。
今はスタッフがいないので、三種保険かけてる人でも「子供が小さいので平日しか無理」「午前中しか無理」「9時から16時しか無理」とか普通に通りますね。
なので私も、曜日指定&時間指定してあげてます。ww
まあ会社と労働者なんて、キツネとタヌキのバカ試合・・じゃなかった、化かしあいみたいなもんですよね。
あまり信用せず、利用できるとこは利用するって感じでしょうか。
>デイちゃんさん
こんにちは~
返信ありがとうございます^^
介護職から更にお金を搾取するやり方は良くないですね~
ギフトのノルマもきつい><
もう介護どころではないですね。。。
ああそうなんですよ。だから介護職って、会社の養分なんですよ。おは養分。ww
漫画のカイジかなんかで、賭博場で金を吸い取られる奴が「俺はこの賭博場の養分だ」って言ってたような。ww
でもあんまり吸い取りすぎると、養分になってるのに気づかれて逃げられたりするから、気づかれないようにそーっと吸わないとね。www
>デイちゃんさん
なるほど、カイジの世界ですか(笑)
気づかれないように吸われるのもイヤですが、気づかなければイヤという感情もないわけですから闇深いですね。