介護現場の多くは人員不足ですが、「人員を確保して欲しい」という労働者側の訴えと「人員を確保したい(又は努力をしている)」という経営者側の利害は一見、一致しているように見えます。
しかし実は、経営者にしてみれば「介護職員が少ない方が儲かる」という考え方があることも事実です。
そりゃそうです。
同じ人数の利用者であれば、入ってくる介護報酬は決まっているわけですから、人件費を削って出て行くお金を減らせば「その分が利益」になるのは経営者でなくても理解ができる算数の問題です。
ですから、「同じ人数の利用者であれば介護職員の人数が少なければ少ないほど儲かる」のです。
しかし、それでは介護職員の業務負担が大きくなってしまいますし、そもそも介護施設は法令で規定されている「人員配置基準」を遵守しなければなりません。
この基準よりも人員配置が少ない場合は、行政処分の対象となり介護報酬が減算されたり、不正に介護報酬を得ていた場合は返還の対象となります。
経営者ですから利益の追求をすることは当然ですし、かと言って法令違反をしてしまうことは自分の首を絞めることになるため、ここで経営手腕が問われてくるわけです。
今回は、リクエストを頂きましたので「介護職員の人員を削って無理な労働を強要する介護施設への対応方法」について記事を書きたいと思います。
介護施設の人員配置基準の闇
介護施設の中でもユニット型特養を例にとって解説していきたいと思います。
ユニット型特養の人員配置基準
よく言われているのは、「利用者:介護職員=3人:1人」という人員配置基準です。
これは、以下の法令に規定されています。
第二章 人員に関する基準
(従業者の員数)
第二条 法第八十八条第一項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二 生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
イ 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、二以上
(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上
(4) 入所者の数が百三十を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上四 栄養士 一以上
五 機能訓練指導員 一以上
六 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
介護保険制度における関係法令は本当に複雑で、介護保険法や老人福祉法や省令、政令、条例、通達、解釈通知、Q&Aなどが「わざとわかりにくくしているのではないか」と勘繰ってしまいたくなるほど複雑に絡み合っています。
そもそも、この「3:1」をそのまま鵜呑みにすると、1ユニット利用者10人に対して常勤換算で介護職員が最低でも3.3人いなければならないことになります(協力ユニットで利用者20人に対して介護職員約6.7人)。
しかし、日中にそんなに介護職員が勢ぞろいしている介護現場を見たことがあるでしょうか。
私は見たことも聞いたこともありません。
簡単に説明すると、この人員配置基準は、「介護職員の総数」つまり「ユニットに所属している介護職員の人数」であり、特定の日に出勤しているかしていないかは関係ないのです。
ですから、極端な話、ユニットに所属している介護職員(及び看護職員)が、4人以上いれば某日の出勤職員が1人でも問題ないのです(もちろん、それでは業務が回りませんので応援を依頼したり書類上辻褄を合わせていく必要はあります)。
大変バカげた基準となっています。
人員配置基準違反となってしまうパターンは、「そもそもユニットに所属している職員の総数が3:1を満たしていなかった」「常勤換算ではなく非常勤も混じっていて基準に満たなかった」という場合です。
また、ユニット型特養であれば「利用者20人に対してワンオペ夜勤」が認められています。
つまり、常勤換算でユニットに所属している介護職員数さえ満たしていれば、法令的には何の問題もないのです。
そして、多くの特養が概ねこの人員配置基準を満たしているからこそ、現状でも大腕を振って運営している状態なのです。
しかし、現場職員にしてみればそれでも人員が足りません。
人員の補充や確保を上司や会社に求めても人員が確保されなかったり、お茶を濁される場合は「実は人員よりも利益を確保するためのダブルスタンダード」である可能性が高いのです。
何故なら、法令上は何の問題もないからです。
介護職員に無理な労働や自己犠牲を強いてでも現状のまま運営していきたいという思惑が見え隠れしているのが「人員配置基準の闇」「介護業界の闇」と言えるのではないでしょうか。
その状態でもこなしてしまう介護職員
仮に人員配置基準を満たしていたとしても、日中1人や2人の介護職員で業務を回すとなると大きな業務負担やストレスを抱え込んでしまうことになります。
そうです、その劣悪な職場環境が人員配置基準を満たしている現状になります。
介護現場ではその劣悪な状態が通常運転になっているため、職場環境が劣悪で常に人員不足の業界だと言われています。
人員配置基準を満たしているからと言って、1人でも辞めてしまうとその基準を満たさなくなってしまうため「生かさず殺さず」「希望もなく絶望もない」状態をキープすることに必死になっているのが介護業界であり介護事業所なのです。
そして、責任感が強い職員ほど頑張って自己犠牲を払い、何とか業務を回そうと努力をします。
少ない人員で業務を回してしまうと、上司や会社は「何だ、やればできるじゃないか」ということになり、法令に違反しない範囲で人員を更に削ろうとさえしてきます。
頑張れば頑張るほど報われない介護現場であれば夢も希望もないことでしょう。
本当に人員不足の介護施設
人員不足、人員不足と言われているのなら、多くの介護施設では人員配置基準さえ満たしていないことになってしまいます。
しかし、多くの介護施設は「人員不足だ」と言いながら、行政処分をされることなく運営しているわけです。
これがどういうことかと言うと、「書類上、事務員などをユニット所属の介護職員にしている」という場合があります。
つまり、実際には介護をしない書類上だけの介護職員が存在するのです。
これで書類上は人員配置基準は満たしていることになりますが、実際の介護現場は人員不足です。
介護職員の業務負担もストレスもマックスの状態です。
そんな状態では、事業所にも問題がありますが、もしそれでまかり通ってしまう状態だとすれば、法令や国や行政にも問題があると言えるのではないでしょうか。
人員を削減して無理な労働を強要する介護施設への対応方法
今まで、介護職員の自己犠牲で成り立ってきたのが介護現場です。
しかし、更に人員を削減して無理な労働を強要するような介護施設へはどういう対応をすればいいのでしょうか。
対応方法①「行政へ通報して辞める」
明らかに人員配置基準を満たしていない場合は、然るべき行政へ通報しましょう。
介護施設の行く末を見守りながらそのまま働き続けてもいいですし、辞めてしまってもいいと思います。
但し、通報する場合は人員配置基準を満たしていないという「具体的な証拠」が必要です。
例えば、ユニットの所属職員全員の氏名と人数や利用者との人数の配置割合を示したり、現場に立っていない事務職員が人員配置に組み込まれている隠蔽工作の事実など「明らかに人員配置基準違反である」という確たる証拠があることを行政に伝えなければ、行政も動きにくいでしょう。
事務員などをユニット所属にしているような確かな証拠がつかめれば一番良いですが、末端の介護職員がなかなかそこまでの資料を手に入れにくいのも事実です。
行政へは匿名でも通報できますし(捨てメアドからでも通報可能です)、通報者の匿名性を(一応は)保護してくれます。
ただ捨てメアドで匿名で通報する以上、具体的な証拠がつかめていないと事業所の書類上の人員配置状況によって「問題なし」という結論になってしまう可能性があります。
そうなると、事業所の正当性を証明してしまう「諸刃の剣」にもなってしまうため注意が必要です。
対応方法②「自己防衛しながら働く」
無理を強いられても知らぬ存ぜぬでマイペースで自己防衛をしながら働く方法です。
もう「無理なものは無理」でしょう。
できないことはできませんし、自分の心身を過度に犠牲にする必要はありません。
利用者の幸せのために自分が不幸せになるなんて不健全すぎます。
利用者の幸せの追求はしていきたいところですが、自分が守れない人は利用者も守れません。
まずは自分と自分の家族の幸せがあってこそ、利用者にも幸せを提供できるのではないでしょうか。
そんな介護施設であれば、自分は自分で守っていかなければなりませんし、最悪の場合は転職も視野に入れていく必要があります。
最後に
今回は、リクエストにお応えして「介護職員の人員を削って無理な労働を強要する介護施設への対応方法」について記事を書きました。
ご希望されていたニアンスや結論から少々ずれてしまった部分もあるかもしれませんが、そもそもの「人員配置基準」がおかしな状態のまま野放しにされているのが介護業界です。
ワンオペ夜勤も未だ認められていますし、それを補うのは介護用品のセンサーという名の介護ロボットのようです。
先日も、介護施設のワンオペ夜勤で入所者に暴行を加えた介護職員の事件もありましたが、介護現場の実情に沿っていない制度である以上、起こるべくして起こったと言えるのではないでしょうか。
「あってはならないこと」が発生するということは、必ず何か原因があるのです。
臭いものに蓋をするだけの表面上のポジティブキャンペーンではなく、蓋を開けて原因を引っ張り出して欲しいものです。




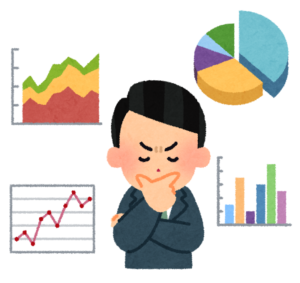




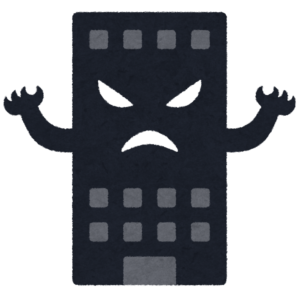
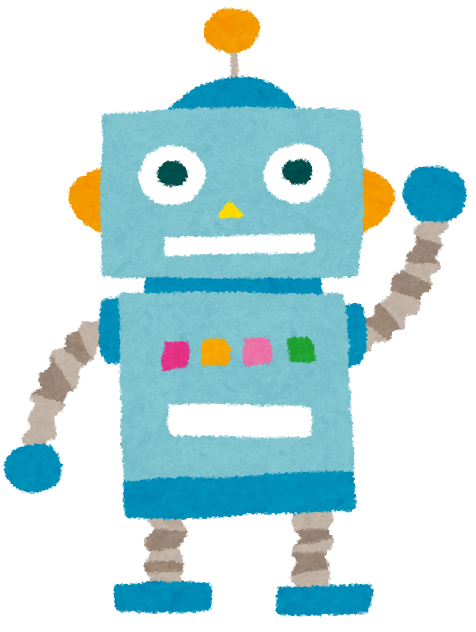

コメント
UP、大変ありがとうございました。(^-^)
対応方法①についてですが・・・。
うちのデイは配置基準は全く守られていません。
勤務シフト表には配置基準が守られているかどうかチェックする欄があるのですが、毎日×ばかり。
なので市の介護保険課に通報したければ、勤務シフト表をコピーして告発文書の証拠として提出すればOKです。ww
なにしろ毎月配置基準は満たされていないので、おそろしい額の報酬返還と指定取り消しが待っていると思いますね。
実際はそうならないように、月末に管理者が、配置基準を満たすように、運転手や事務員が介護職として勤務したように改ざんしているようです。
介護保険課はその説明に納得してくれるんでしょうか。告発してためしてみたいですね。ww
対応方法②についてですが、私は全く無理をしません。
例えば、目離しできない利用者が複数いるのにそれを1人で見なきゃいけない・・となったとして、働き者の人はストレスを感じながら、走り回って何とか対応しようとするでしょう。
でも私はしません。一人の対応をしてる時、別の人が動き出しても放置です。であえて事故になるのを待ちます。そして「私は〇〇さんをしていたので、△△さんはできませんでした。△△さんが動くのが見えて必死で走ったのですが。」などと説明します。△△さんはもしかしたら転倒して骨折し、入院になるかもしれません。でも私が責任を問われることはないでしょうね。問われたら出るとこに出ますし、△△さんはいなくなるので楽になるでしょう。そうやって一人ずつ利用者を減らしていきますね。
利用者さんには申し訳ないけど、できないことはできないし。できないことをスタッフの良心につけこんでやらせようとする会社が悪いんですよ。
実際は骨折事故や死亡事故が続けば行政に報告が必要だし、会社もさすがに連続で事故報告はしたくないでしょうから、スタッフをいれるか、利用者を減らさざるをえないでしょうね。
そう、会社の生殺与奪の権利は、スタッフがにぎっているのです。
>デイちゃんさん
こんばんは~
リクエスト頂きありがとうございました^^
なるほど、証拠があれば強いですね。
とにかく1人の利用者に集中して無理なことはしない方が良いと思います。
介護現場には無理難題が多すぎますね。
本当です。
できもしないことをやらせて、「できないのはお前が悪い」「だからサービス残業して仕事を全部してから帰れ」などと圧力をかけてくるのは、ブラック企業の常套手段。
タイムカードを先押ししてたら、すぐその現場をスマホでとってすぐに労基署に通報。
管理者には、「できないのはお前が悪いからサビ残して仕事を全部して帰れって言ってください。動画とりますので。はい、どうぞ。」とスマホを向ける。たぶん、二度と言わなくなると思います。ww
あと、介護施設だと、「行事やイベントの準備は当然無給」ってとこ多くないですか?
無給なら何もしない。働くなら金をもらう。そこをきっちりしたいですよね。
前にいたパワハラ管理者が、「イベントの準備は勤務をつけてはいけない。」と言ったので、「じゃあ準備しません。」と言ったら、管理者が「とにかくしなさい。」と言うので、「じゃあ金払え!」と言ったら、管理者は何も言わなくなりました。
お前が無給で準備しろ!ww
管理人様は、前と同じところで働いているんですか?
>デイちゃんさん
こんばんは~
返信ありがとうございます^^
いや~本当ありだと思いますよ。
実は私も仕事中は常にICレコーダーを携帯しています。
同じ所で働いていますよ~主導権を握ったらギスギスしていても何とか働けます(謎)
そうなんですか。
まあ今はスマホがありますから、施設内の不都合な真実もすぐに証拠としておさめることができますしね。いい時代になりました。ww
私は、アフォな管理者やカスタッフのせいで何回かやめよっかな~と思ったんですが、「やめるのはお前の方だろ?」と思ってやめてないんですよね。いつやめてもいいんだけど。ww
管理人様が地獄のような施設で主導権を握った方法について記事を書いてみたらどうでしょう。
「地獄のような介護施設でやめない介護職のメンタル」
「地獄のような介護施設を攻略し逆に利用する方法」
とかなんとか。ww
これ、結構みんな知りたいかも。www
>デイちゃんさん
返信ありがとうございます^^
ん~書きたいんですけど身バレすると面倒くさいので(笑)
簡単に言えば、デイちゃんさんのやり方と酷似していますよ。