介護保険サービスの理念を簡単に言えば、利用者の「尊厳の保持」と「自立支援」になります。
介護保険法第1条の「目的」に明文化してある通りです。
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
【引用元】介護保険法
尊厳の保持とは、本人の自己決定が尊重されることです。
もっと言えば、
- プライドを傷つけない
- 人格や人権や権利を虐げない
- 子供扱いしない
- 差別しない
ということにもなろうかと思います。
利用者も(もちろん我々も)人間なのですから、個人として尊重されて当然です。
実は、この「尊厳の保持」は憲法第13条にも規定してあります。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
【引用元】日本国憲法
ですから、尊厳の保持は介護保険法以前に憲法の理念のひとつとしてすべての国民が享受するものなのです。
さて、そこまではいいのですが、問題となるのは介護現場において「利用者の尊厳の保持がフォーカスされ過ぎて逆差別となってしまう実情」があることです。
つまり、「過剰に個人を尊重し差別(被差別)を排除しようとする異常な配慮が逆差別を生んでしまっている」ということになります。
今回は、利用者の尊厳の保持が逆差別になってしまう介護現場の実情について記事を書きたいと思います。
利用者の尊厳の保持が逆差別になってしまう介護現場の実情
逆差別とは、差別を排除しようとする過程の中で差別されてきた側の人達を優遇することで、それ以外の人達の待遇や利益や公平性が損なわれてしまうことです。
つまり、差別を排除するつもりが新たな差別(逆差別)を発生させてしまっている点で不健全な状況であることが理解できるかと思います。
介護現場でも、利用者の尊厳の保持を過剰に意識したり執着をすることで、こういった逆差別が発生している実情があるのです。
以下で詳しく解説していきたいと思います。
実情①:職員が利用者の召使い
「利用者の尊厳の保持をしなければならない」という異常な刷り込みがなされると、職員が利用者の召使い状態になってしまうことがあります。
例えば、
- 利用者の希望や要望全てに対応しなければならない
- ナースコールで呼べばいつでも召喚できる便利な人達
- 職員の人権や権利を犠牲にしてでも利用者の人権や権利を擁護する
などという状況が常態化していれば、逆差別が発生していると言えます。
何故なら、
- 職員も人間であり尊厳の保持をされるべきなのに反故にされている
- 利用者を優遇することによって職員の待遇や公平性が損なわれている
ということになるからです。
もちろん、職員は仕事として介護サービスを提供しているわけですから、より良いサービスを提供していこうとする上で常識の範囲内での一定の犠牲や負担は付きものですが、「常識の範囲を超えてそれらが常態化しているとすれば逆差別状態」と言っても過言ではありません。
そもそも、職員と利用者は対等な存在であり、どちらが上でも下でもないはずです。
利用者の尊厳の保持のために、利用者を過剰に優遇し職員がまるで召使いのようになってしまっている介護現場は、逆差別が横行している不健全な職場であると言えます。
実情②:無法地帯、治外法権
前述したように、職員が召使いのような状況であれば不当な逆差別が常態化していると言えますが、「不当だけではなく違法な状態」が常態化している場合も往々にしてあり得ます。
つまり、介護現場が無法地帯や治外法権のようになってしまっているのです。
例えば、利用者の
- モラルハラスメント(モラハラ)・侮辱・名誉棄損
- セクシャルハラスメント(セクハラ)・強要・(準)強制わいせつ・公然わいせつ
- パワーハラスメント(パワハラ)・暴言・脅迫
- 暴力・暴行・傷害・器物破損
などの法律に抵触するような行為が野放しになっていれば、無法地帯・治外法権の世界だと言っても過言ではありません。
もちろん、認知症の症状であったり精神疾患などの病気の症状である場合も少なくありませんが、問題なのは「そういう利用者の加害行為に耐えながら介護をするのが当たり前」という風潮になってしまうことです。
仮に病気の症状であったとしても、野放しや容認して職員の自己犠牲だけに頼ってしまう状況が常態化しているのだとすれば、それは逆差別を助長していることになり不健全な状態です。
こういった場合、
- 対応方法の検討・共有
- 薬の調整
- 医療機関との連携や橋渡し
- 利用契約の解除や退所
などを行っていくのが本当のプロではないでしょうか。
無法地帯や治外法権が野放し状態の介護現場では、排他的な隠蔽体質になりやすくもなりますし、その先に待っているのは「職員の泣き寝入りや堪忍袋の緒が切れることで発生する虐待や介護事件」だと言っても過言ではありません。
事実、そういう報道が時々流れてきますが、それらはまだまだ氷山の一角でしょう。
介護現場では、利用者の違法行為を野放しにし、黙認や容認をする逆差別によって職員も利用者も不幸になっていく実情があるのです。
実情③:メサイアコンプレックス
「差別はダメだけど逆差別も良くない」ということは、社会通念上の常識で考えれば誰でも理解ができることですが、介護業界にはそれが理解できない人達が存在しているのも事実です。
「自分を犠牲にして他者に尽くすことが気持ちいい」
「逆差別がダメだという常識に捉われてはいけない」
などと、一見良いことを言っている人達の存在です。
しかし、そこに透けて見えるのは、
- 自己陶酔(ナルシズム)
- 自己満足(独りよがり)
- 利己主義(エゴイズム)
- 異常な自分軸・嗜好・性癖
などになります。
つまり、「逆差別を自分の満足感や恍惚感を得るために行うちょっとアレな人達」なのです。
「福祉」という特殊な業界上、こういう人達が少なからず存在しているため、「利用者の尊厳の保持という名の逆差別」が常態化している実情があります。
こういう人達のことを「メサイアコンプレックス(救世主妄想)」と呼びますが、介護現場の逆差別を助長させている権化だと言っても過言ではありません。
メサイアコンプレックスについては、下記記事でも触れていますのでチェックしてみて下さい。
最後に
今回は、利用者の尊厳の保持が逆差別になってしまう介護現場の実情について記事を書きました。
「差別もダメだけど逆差別もダメ」という前提で考えれば、介護現場において、
- 職員が召使い状態
- 無法地帯や治外法権
- メサイアコンプレックス
があってはならないということも理解ができるかと思います。
差別も逆差別もない状態が、本当の意味での「利用者の尊厳の保持」と言えるのではないでしょうか。









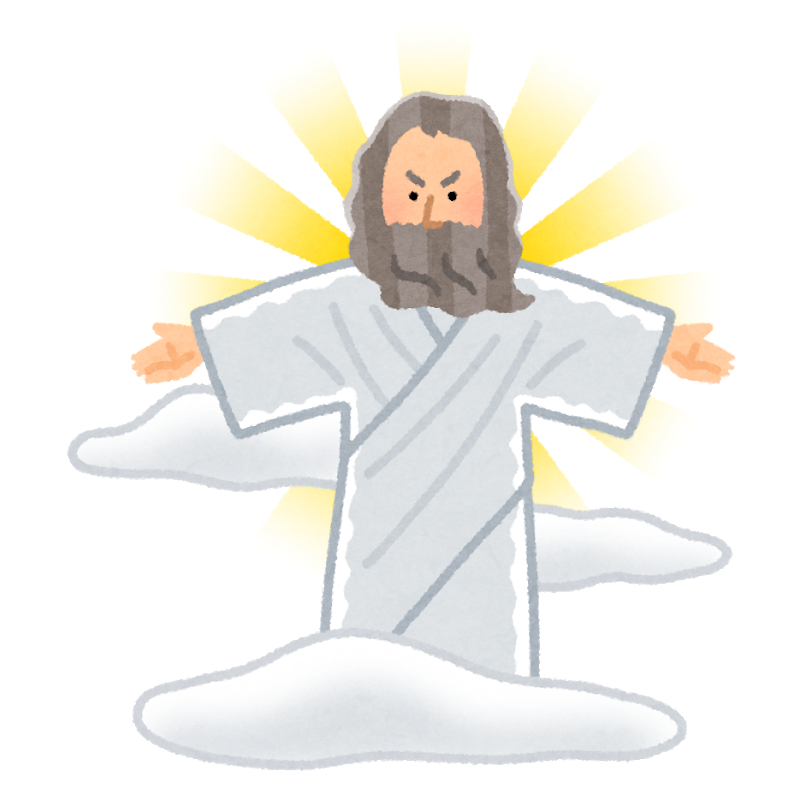



コメント
こんにちは。
私はちょっと勤務時間を増やしてみたんですけど、スタッフ全員から顰蹙を買いまくってる最強徘徊暴力女性利用者と遭遇しました。
その利用者は一見おとなしそうなんだけど、徘徊しまくって、いろんなものをとったり、利用者をたたいたりしてるらしい。
で入浴は何年もしてなくて(拒否&暴力でできなくて)、ヘルパーでリハパン交換だけしてるらしい。今はお高いサ高住に入ってそこの併設のデイを利用してたけど、「ご本人様の意向を大事にして」とやらで、入浴を強制的にはしてなかったんだって。ってそこのデイ、クソバカすぎ。でどんな重度も受け入れるうちに話が来たみたい。(笑)
その女性利用者は、どうも女のスタッフには暴力暴言がすごいみたいで、例の認知症じいさんスタッフの言うことは素直に聞くらしい・・と聞いてたんだけど、その通りで、私が話しかけたら機嫌よく答えて、入浴もちょっと暴れたけど、私が手を握ってもう一人のスタッフが体を洗って・・とすれば苦も無くできましたね。
でも徘徊しまくっていろんなものをとったり・・はその通りで、保管してる薬をいつの間にか盗んでたり、ダンベルを利用者の頭の上にかかげてたり、・・とかなり危険な状態で目離しがいっさいできない。
あげくのはてに、他の利用者のそばをうろついてものを盗ろうとして、その利用者が「私のものにさわるな!」と怒鳴ったら、べしっと頭をたたいちゃったよ。
あら~、たたいた利用者もたたかれた利用者も終了かな~と思ってたら、次の日もどっちも来てたけども。そこは管理者の出番じゃね?
というわけで、最強重度って他の女性スタッフは言うけど、私からしたら普通にやりやすいけど目離しはできない人でした。私はむしろ結構好きかも。
スタッフによって態度を変える利用者は多いですね。
暴力がすごいけど特定のスタッフの言うことは聞く利用者って、スタッフによってその利用者の評価が変わるので、難しいですね。
娘が完全放置のうんこたれ流しの暴力暴言がある女性利用者は、男性スタッフには暴力がすごくて女性スタッフにはそうでもないので、個人的にはそっちの方が、私はやりにくいですけど。
今さらですけど、片時も目離しができない利用者って、
(1)その利用者専用のスタッフを配置する
(2)薬で抑制する
(3)事件事故になるまで放置して、会社が断るようにもっていく(ただし自分がその事件事故の当事者にならないように気をつける)
のどれかだと思うのですが。
(1)は人件費的に会社はしないでしょうね。(2)は家族が薬は嫌とか言い出して、可能性はなさそう。一応家族には伝えてるらしいけど。
というわけで(3)かなあ。断るまでに利用者がさらに減って行きそうですけどね。ww
>デイちゃんさん
こんばんは~
リアルな生の介護現場の情報をありがとうございます。
目が離せない利用者は結局はそういう対応になりますよね。
介護施設でワンオペ夜勤の場合はニッチもサッチもいかなくなるため、現場職員が苦肉の策を講じることで虐待や事件に繋がることもあるでしょうね。
会社も何かあってもトカゲのシッポを切るだけですしね。
スタッフによって態度を変える利用者は確かに多いですね。
屈強な男性スタッフには控えめなのに、女性にはハラスメントが凄い利用者というパターンが多い印象でしたが、その逆パターンもあるのですね。
過去のトラウマや偏見なども関係しているのかもしれませんね。
男尊女卑の時代を経験して、男のヘルパーに対して、「男の方にこんなことさせてしまって」みたいに恐縮する女性の方もいらっしゃいますね。
その一方、男は嫌とか、男スタッフ拒否の女性利用者もいますね。これはどこまで許されるんだろ。
今回たたかれた利用者の方は、嫁いびり大好きな感じの女性の方で、女性スタッフにあれこれ指示して、40分くらい説教したりしてました。
でも男性スタッフに対してはあんまり言わない感じですね。私はわざと嫌味で(笑)、「今日〇〇さんにはじめてほめられた~」と言ったら、その人が「そんなことないでしょ」とちょっとあわてて言ってました。
利用者に対して、スタッフも、あの人はやりやすいけどあの人は苦手ってあると思うんですよね。
大人数の利用者を大人数のスタッフで見るなら、私はあの人できるから私がやるけど、あの人は苦手だからあなたやってくれる?とかお互いに補完できると思うけど。
ユニットみたいに少人数の利用者を一人でみるとなると、できない人が1人いたら困りますからね。
そういう点からもユニットって通常業務に支障をきたしやすいですね。
>デイちゃんさん
そうですね、高齢の人の中にはまだ男尊女卑が根強く残っている場合もありますものね。
同性介護希望の利用者もいますが、極力希望に沿うようにしてみたところでどうしても無理な状況もありますね。
よくよく考えれば、介護保険は公的保険なわけですから「おもてなし」を求めたり求めなければならないような方針や風潮になっていくことに無理があるように感じます。
こんにちは。
娘が完全放置のうんこたれ流しで徘徊暴力暴言がある婆さんが、毎日デイに来てる。
もうすぐロングショートって言ってたのに、とうとうショートにも断られたらしい。暴力がすごすぎる上に、うんこまきちらすからね。
で、毎回私はそのうんこたれ流し婆さんの入浴をしてる。
暴力暴言がすごい。うんこもすごい。オムツからうんこがはみ出して、ズボンまでしみだしてる。洗って清潔にするのに一苦労。やっと個浴につかったと思ったら、中でうんこ。結局出てからまた肛門から出てくる便を洗い流し、全身も洗い流す。
ふと、なぜ私は毎回このうんこ婆さんの処理をしてるのか?と思った。
私は入浴を早く終わらせるために、送迎に出ないで残って9時から入浴を早く始めてるんだけど、だから毎回その婆さんのうんこ処理が当るんだね。
・・・ってことで、私は来月から送迎に出ることにしました。
送迎に出てゆ~っくり帰ってきたら、その婆さんの入浴は、9時から入ってる送迎に出ない他のスタッフがしてるだろうからね。
9時入りスタッフは、もしかしたら何もしないでボケーっとしてるかもしれないけど。だったら私も送迎から帰ってきてからトイレにこもったりして、時間つぶそう。
にしても、8時出勤で送迎に出る人って、前は一応お茶や入浴の準備をちょっとしてたのに、今は全くしてない。9時前に来て全部私がしてる。
だから私は8時出勤で送迎に出る時は、何もしないで送迎に出ようと思う。お湯くらいはわかしといてあげるけど。ww
やっぱりサボるスタッフってずーっとサボってて、働くスタッフってずーっと働いてるね・・と思ったのでした。
そうそう今月から、サボりスタッフは一部訪問に回されてます。そのまま訪問にさようならになればいいんだけど。訪問は一人だからサボれないからね。(それでもサボる人いるけど)
と関係のないことを書いてしまってすいません。
>デイちゃんさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
ショート利用日だけ下剤を服用させて自宅では服用させない利用者家族も経験しましたが、なかなかエグいですね。
排便もエグいのですが、そういうやり方もエグいと感じました。
そのパターンではなく普段から垂れ流し状態の利用者のようですが、それもなかなかエグいですね><
一度でもサボることが黙認・容認されてしまうと、それが当たり前(通常運転)になってしまうきらいはありますね。
だから、最初にサボりを許しちゃいけないんだと思います。
いつもお疲れ様でございます。。。
介護5の重度で家族がネグレクトの利用者を毎日利用させて、40万丸どりするのが元管理者のやり口。
でもデイにいるよりも家にいる時間がはるかに長いから。夕方18時に送って朝9時まで15時間は利用者は放置されてる。
テープ止めオムツにおっきな尿パッドつけて、うんこしっこたれ流し状態。
朝来たら、もううんこがオムツからはみ出てる。
これ、もう虐待ですよね。
そういう状態なら、もう在宅は無理だと思う。
家族が排泄介助するか、できないならショート利用するか入所を検討するかしないと、利用者がかわいそう。
それを売り上げのために、ホイホイ入れて、しかも虐待状態で放置。もう根本的に間違ってる。
自分がオムツつけられてうんこしっこたれ流しって考えたら・・不穏になるよね~。高齢者の人権っていずこに?
排泄はおろそかにしてる一方で、元管理者はせっせとやらなくていいことばかりしてる。
散髪をしたり、利用者の家のそうじをしたり、ごみを捨てたり、通院をしたり、朝食夕食を出したり、ポータブルトイレの掃除をしたり。これ全くの本末転倒。
やらなくてはいけないことをやらず、やらなくていいこと・やってはいけないことをやってる。
そういう間違ったことをしてるから、利用者がダダ減り、売り上げダダ下がりになるんだと思う。
まあ今のまま下がって行ったら、少なくとも元管理者は完全に異動だと思う。まだデイのあたりで未練たらしくウロウロしてるけどね。
もっと売り上げ下がったら、また私の出番って思ってるみたい。
まあ私は一人分のみの仕事をして、少しでも楽をするように心がけて頑張ろうと思います。ww
>デイちゃんさん
返信ありがとうございます^^
それは虐待(ネグレクト)に該当する可能性が高いですね。
その状態を知っていて適切な措置を講じていない担当ケアマネも元管理者も完全に職業倫理に反してしまっていますね。
そういうしわ寄せが現場スタッフに来てしまう所が不健全ですね。
そりゃダメになるわけです、介護業界。。。
どうもです。
よく特養でも、下剤かけてそのまま放置されて、朝オムツあけてみたら、便の海に尻が浮かんでる状態・・ってよくありますけども。
結構気持ち悪いと思うんですよね。私ならずぐに洗い流してほしいわ。
あのオムツで長時間放置するって発想、いい加減やめてほしいわ。
皮膚状態も悪化するし、尿路感染とかのリスクも上がるし、不穏になるし。
そうそう、デイの常勤が二人、今の状況に腹を据えかねて退職届出したんですよ。元管理者への抗議って感じで。
で支店長に説得されて結局やめないらしいけど。やめればいいのに。(笑)
元管理者的には、「あいつら辞める気か!?はむかいやがって!」って感じだろうけども。ww
まあ私は、会社に利益利益言われても、とりあえず自分の良心に従って仕事して、できないことはできないでいいと思うんだけどね。
>デイちゃんさん
確かに気持ち悪いでしょうね。
下剤で放置はさすがに無しですね(もちろん排尿もですが)。
辞める辞める詐欺も使い方次第では効果的だったりしますが、周りからしてみれば色々複雑な気分になったりもしますね。
公序良俗や倫理観や良識や常識や道徳観を見失ったら終わりですね。
人の道から外れないことが、ひいては自分を守ることにも繋がりますものね。