過去記事でも「おむつゼロ運動」について触れましたが、久々にオムツゼロについての話題を目にしましたので、感じた違和感について記事を書きたいと思います。
結論から言えば、その違和感の正体は「本来の目的を見失って、おむつゼロにすることだけが目的になっているのではないか」ということになります。
おむつゼロにすることが目的になっている違和感
おむつゼロの本来の目的は自立支援であり、「水分・食事・排泄・運動」の4つを大きな軸として最終的には利用者が「トイレで排泄できることの喜び」を感じるようにする一種のスローガンです。
しかし、その実情はどうでしょうか。
違和感を感じるものが多く散見されています。
目的を見失った「おむつゼロは素晴らしい」という風潮
批判をするつもりはありませんが、いつからか「おむつゼロ」がひとり歩きし、「利用者のニーズ」や「利用者の尊厳」や「利用者の喜び」をすっ飛ばして「ゼロにすることが素晴らしい」ということになってはいないでしょうか。
つまり、いつの間にか目的がすげ替わってしまっているのです。
利用者のニーズの有無を言わさず兎にも角にも、おむつゼロを達成すると
- 誰かから評価され表彰され賞状をもらえる
- 介護報酬が手厚くなる
- 実績としてホームページやパンフレットや報告書に謳える
という印象を強く受けます。
その証拠に、多くの情報を確認してみると、
「これだけの数の介護施設がおむつゼロを達成した」
「最初はできないと思っていたけど、試行錯誤しながら何とか達成できた」
などと、あたかもおむつゼロ達成がゴールかのように書かれています。
もちろん、ゼロにすることがゴールではなくその後も継続しておられるのでしょうが、そこには
「利用者がどう喜んでいるのか、又は、喜んでいないのか」
「利用者にどういう良い変化、又は、悪い変化があったのか」
「失禁の頻度は減ったのか増えたのか、それとも変わらないのか」
「おむつをして欲しい、と訴える利用者は1人もいないか」
など、利用者に関することがスッポリと抜けてしまっています。
おむつゼロの本来の目的から考えると「そこが肝」のはずです。
肝の部分が抜け落ちてしまっているおむつゼロ運動は、本来の目的を見失ってしまっていると言っても過言ではありません。
闇雲なゼロは善意の押し売り
何事にも言えることですが、闇雲は良くありません。
0か100かのゼロサムゲームのような極端なものも介護現場では適切ではなく、利用者のニーズを前提とした上で丁度良くやっていく必要があります。
そうでなければ主役が誰なのかわからなくなってしまいますし、そもそも理論だけでは通用しないことは介護現場には山ほどあります。
介護職員が主役になってはいけませんが、現状では
- 経営者
- 介護研究者
- 介護コンサルタント
などの現場に立たない・顔さえ出さない人達の方が主役になってしまってはいないでしょうか。
おむつゼロを達成した介護施設があるとするならば、もっと利用者に目を向けた結果報告や統計が欲しいものです。
そうでなければ、「ただの善意の押し売り」と言われてしまっても仕方がないでしょう。
最後に
今回は、「おむつゼロ運動は本来の目的を見失っているのではないか」ということについて記事を書きました。
「おむつゼロを達成した介護施設は素晴らしい」と手放しで称賛する風潮には違和感を覚えてしまいます。
「その陰で泣いている人や、つらい思いをしている人を新たに発生させてしまっているかもしれない」ということにも目を向けていく必要があるのではないでしょうか。



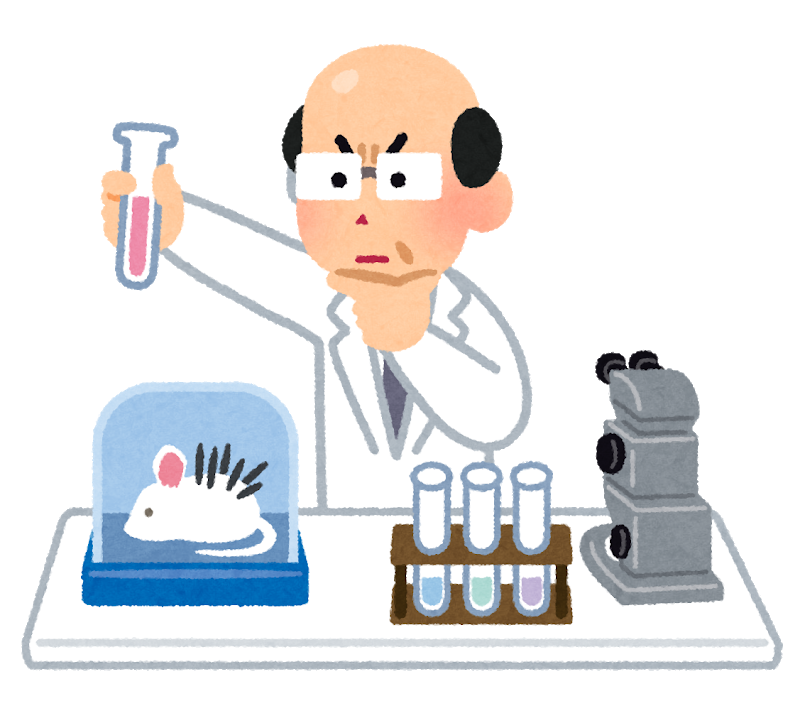





コメント
そもそも施設だからやり玉に挙げられているけど、その老人をどうするの?って話ですよね。
私は特養しか知りませんが、多分ショートの半分は特養相当と考えれば、施設に入れられた老人に行く当てがないって話で。
いかにお涙頂戴の理由があったとして、「家」には戻れない、戻ってほしくはないのが結果にして事実です。
仮にですが、特養の老人でさえ「家」に戻すことを前提として、戻せたとして。なお仮に家族か親戚がその面倒を見るとき、その認知症老人の面倒を見切れるのか?は考えにないのですよね。
赤ちゃんが起源とはいえ、そうした理由を鑑みて、老人利用しているのに、それを一家庭がその排泄失敗の面倒を見れるのか?
家庭の延長のユニットケア(笑)なんてうそぶくのなら、その排泄失敗を無視するのはいかがなものか?
本当にユニットケアなんて害悪。そのくせ、謎理論で少ない配置基準、防水シーツも使うなと言いながら予備のベットもない・・・
>めど立てたい人さん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
そうですよね、結局どうしたいのか迷走もいいところですよね。
家庭の延長とか矛盾もいいところですね。
百歩譲って「個室」は良いにしても、ユニットケアの在り方や弊害をもっと本気で考えていく必要がありますね。
特養や老健て、オムツ代は施設もちですよね。
だから「オムツ減らせたらコストが減るわ~」って思いながらのオムツはずしだと恐ろしいですね。
オムツはずし推進派の施設長は、表では「排泄の自立をうながす」などと言いながら、裏では「これで100万浮いた」とほくそえんでるのかもしれません。
「その分スタッフの仕事量が増えるって?いやいやスタッフはこき使えばいいんですよ。もっと利用者の自立のために働かなきゃ。」みたいなね。
>デイちゃんさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
いや~それは往々にしてあると思いますよ。
目の前にニンジンをぶら下げて馬車馬のようにこき使うことばかり考えている経営者も少なからずいることでしょう。
キラキラ職員やユニットリーダー研修に行った職員なんかは画一的に物事考えて柔軟性なくなって周りと揉めるんですよね。
とにかく利用者が無事に毎日生活できて何事もなければそれが一番だと思います。介護職はそれを援助するだけですから。ホント理想より目の前の利用者です。
>かずさん
返信ありがとうございます^^
ユニットリーダー研修あるあるですね><
映画を観たあとにその主人公になりきったような振る舞いをする姿に似ていますね。
本当、安全第一ですよ。
まずは自分を守りながら働くことが先決ですね。
自分が危険な状態では利用者も守れませんからね。
ホント同感です。
キラキラ職員なんかもオムツゼロにはまっている人多いですね。
オムツ外ししない施設は努力不足だとか。なんか勘違いしてますね。
当たり前の事ですが利用者の状態や気持ちをみて外していくかそうでないかを考え、トイレで排泄できる人をオムツにしない事も考える事が必要だと思います。
僕の知り合いで最初に勤めた特養がオムツ外しを無理矢理推進しようとして上司と喧嘩して辞めました。その時怒りのあまり泣いてオムツ外しなんかはあんたらの都合だ!と怒鳴ったそうです。
>かずさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
そうですよね。
利用者の状態を評価したり処遇を見直していくことは必要ですが、「おむつゼロ」というゴールや目的を決めた上での方針はエゴイズムや善意の押し売りでしかないですよね。
特養であれば寝たきりの人が集中しているユニットやフロアもありますし、あまりにも画一的に考えすぎですね。