特養などの介護施設には施設介護支援専門員(以下、施設ケアマネ)がいます。
人員配置基準で配置が義務づけられているのですが、「介護職員にとって嫌な感じの施設ケアマネ」の存在もたびたび耳にします。
ちなみに、居宅ケアマネの場合は法人や事業所が別(同じ法人内のケアマネでも事業所は別)であるために、事業所単位で考えると外部の人になりますが、施設ケアマネの場合は同じ事業所内で一緒に働いているため内部の人(つまり、同じ職場の人)になります。
ですから、施設ケアマネの場合は「職場環境」に影響する存在になります。
今回は、介護職員を閉口させる「こんな施設ケアマネは嫌だ!5選」をご紹介しようと思います。
こんな施設ケアマネは嫌だ!5選
介護士に「こんな施設ケアマネは嫌だ」と思われている時点で嫌われています。
嫌う方が悪いのか嫌われる方が悪いのかはさて置き、そんな状態では人間関係も職場環境も悪くなりますし、「ケアやケアマネジメントが良い方向に向かってはいない」ということは間違いありません。
どのような施設ケアマネだったら「嫌だ!」と思われてしまうのでしょうか。
①「偉そう」
当然ですが「偉そう」な施設ケアマネは嫌です。
上から目線だったり、知識をひけらかしたり、マウントを取ってくるような施設ケアマネであれば閉口してしまいます。
言い方ひとつで相手に与える印象は全く変わってくるのですが、「言い方にも配慮できない施設ケアマネは偉そうで嫌」です。
介護士には偉そうな発言と態度をしておきながら、その舌の根も乾かぬうちに利用者には猫なで声で接している姿は異様な姿に見えてしまいます。
ケアマネジメント過程において、利用者や家族だけでなく「多職種などとの関係」に対しても基本倫理(職業倫理)が求められているので、偉そうにしている施設ケアマネは「倫理に反している」と言えます。
また、利用者のモニタリングも介護士に行わせている場合が多くありますが、本来モニタリングはケアマネの業務です。
「介護士がやって当たり前」というような顔をしている施設ケアマネは図々しくてとても偉そうです。
②「介護福祉士の上位互換だと勘違いしている」
偉そうな発言や態度の裏には「ケアマネは介護士より偉いんだ」「ケアマネは介護福祉士の上位互換なんだ」という勘違いがあるのではないでしょうか。
これは、実際そうではないということを頭でわかっていても、介護サービスの実施状況を把握してケアプランを作成し、そのケアプランに沿って介護士が業務を実施しているサイクルが繰り返されると、「やはりケアマネの方が介護士より偉いのだ」「ケアマネの手となり足となって働くのが介護士なのだ」という驕りや慢心が出てしまう人もいます。
そんな気持ちを持ってしまった時点で、倫理に反し自分を見失ってしまっています。
自分を見失ってしまった人と一緒に働くのは嫌ですし、そもそもそんな人では適切なケアマネジメントができるはずもありません。
過去記事にも書きましたが、「ケアマネは介護福祉士の上位互換ではない」のです。
③「利用者本位ではなく自分本位」
「自分は特別な存在」だと思っている施設ケアマネは「利用者本位ではなく自分本位になりがち」なので嫌です。
中規模程度までの介護施設であれば、施設ケアマネは1人、多くて2人しかいないでしょう。
そういう配置基準になっているだけで、人数が少ないから「貴重で特別な存在」というわけではありません。
そこを勘違いしてしまうと、だんだんと自分本位なケアマネジメントになっていきます。
利用者のために「こういうケアをして欲しい」「こういう介護サービスを提供したい」という気持ちが強くなり、「質の向上」を建て前にして介護士への圧力も強くなっていきます。
しかし、よくよく考えると「利用者のために」と言いながらも、その内容は結局「自分(施設ケアマネ)の理想とやりたいこと」だったりします。
いつの間にか、介護支援の中心に立っているのは利用者ではなく施設ケアマネになってしまっているのです。
「利用者を満足させたい」のではなく「満足している利用者を自分がどうしても見たい」「利用者を満足させることに成功した自分に酔いたい」という目標にすげ替わってしまっています。
「只の自分本位なケアの押し付け」では上手く連携が取れずお互いが苦労することでしょう。
④「介護士の粗探しばかりしている」
前述したような施設ケアマネにありがちなのが「介護士のアラばかりを探している」ということです。
もちろん、ミスや不完全な業務は無い方が良いのですが、チリひとつ見逃さないような粗探しをされると介護士も息が詰まってしまい嫌になってしまいます。
まるで小姑のような存在です。
介護現場に顔を出したかと思えば「立ち入り検査や監査をする役人」のような顔つきと態度にも閉口してしまいます。
他の職種のアラを探してつるし上げる前に、そうなってしまった原因を考えたりどうすれば上手くいくのかを皆で検討(ケアマネ1人で勝手に決めない)していくことが重要です。
逆に自分のミスを指摘されると、逆ギレしたり責任転嫁をしたりスルーしたりするのが特徴です。
こういう人は「協働と主導」を履き違えてしまっています。
チームケアは多職種協働なのであって、ケアマネ主導ではありません。
⑤「居ない方が平和」
「こんな施設ケアマネは嫌だ!」ということを総括すると「施設ケアマネが居ない方が介護現場は平和」だということになります。
平和ということは「介護士が働きやすい職場」ということになります。
働きやすければ、職員の定着率も上がりますし「より良い介護の提供」にも繋がります。
もちろん、「良くないことは良くない」ので正していく必要はありますが、その役割を担うのは縦の繋がりである介護リーダーや介護主任(又は介護課長等)になります。
直属の上司の能力や資質の問題もありますが、だからと言ってすっ飛ばしていいものでもありません。
あくまで、介護士と施設ケアマネは横の繋がりであり、チームの一員なのです。
どの職種も必要不可欠なものなのですから、「居ない方が平和」などと思われるような人が存在してしまうと「チームケアの破綻」が目前に迫っていると言えるのではないでしょうか。
最後に
今回は、介護職員を閉口させる「こんな施設ケアマネは嫌だ!」というものを5つご紹介しました。
特養などの介護施設では利用者100人に対して施設ケアマネ1人以上の配置のため、自分しか施設ケアマネがおらず相談できる相手(同職種)がいなかったり、施設ケアマネ独特の悩みもあることでしょう。
だからと言って、介護士に偉そうにしたり立場を弁えないような振る舞いをしてしまうのはお門違いです。
利用者を中心とした同じチームの一員として、「お互いが対等な立場で敬いながら利用者を支援をしていくこと」が非常に大切なことではないでしょうか。







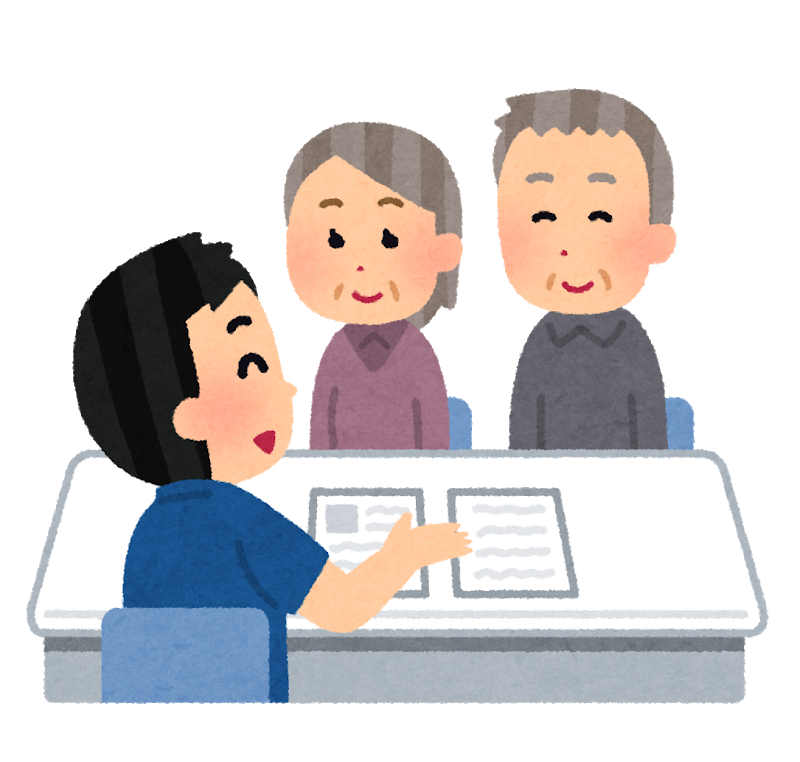

コメント
確かに大変さがクローズアップされてる事が多いですから。僕の知り合いでもケアマネ取って大手の事業所で在宅ケアマネやったらあまりにも大変で『二度とやらねー!』っていってそこ辞めて介護職に戻ってますから。
やっぱりどの職種でもそうですが頑張ろうって環境にしていかないと良い人材が育たないし出てきませんよね。
>かずさん
ケアマネは収入面でもそれほど良いわけではありませんからね~
頑張れる環境作りは大切ですね。
「やりがい」だけでは無理がありますね。
実際仕事しながら覚えて、わからない事は教えるからってケアマネ持ってた相談員から引き継いだ感じで仕事してますね。利用者のことも把握できてない、しようとしないし…たしかに被害者でもありますね、ちゃんとした所なら一からキチンと教えますからね。
しかし周りにはこの人がケアマネやればいいのにって言われてるけどやらない人が多いです。そういう人達って人柄も良くて話しやすくて話もキチンと聞いて返してくれるんですよね。なんかもったいないですね。
>かずさん
返信ありがとうございます^^
ケアマネという職種に魅力やメリットが少ないのでしょうね。
だからケアマネ資格を持っていてもやりたがらない人が多いように思います。
色々もったいない話です。
何故だか返しのコメントで名前が匿名になってました。すいません。
>かずさん
お名前の件、了解しました^^
本当にそう思います。ケアマネだけでなく上司もそういう環境づくりが大切ですね。そういえばケアマネが珍しく食事介助に入った時に身体の大きい利用者だったんですよ。体制直すの頼まれたので嫌な顔しないでやってあげたらけっこうお礼言われて、少し話しました。僕も昔相談員してて慣れなくて余裕ないときは職員にきつくなってしまって…慣れてきたら大丈夫になりましたが、そういう自分の経験踏まえて、ケアマネさん、余裕ないでしょって言ったら『そうなんですよ、もう初めてだから何していいかわからなくて、すいません自分も下手な所あるんで』って言ってました。だからやってればそのうち上手くいきますよ。だから上手くコミニュケーション取ってきましょうといいましたが、どこまで届いたか…。
>かずさん
環境づくりもコミュニケーションも大切ですね。
ひょっとしたらそのケアマネさんも右も左もわからないままケアマネ業務の最前線に放り出された被害者なのかもしれませんね。
お久しぶりです。
ウチのケアマネなんですが、去年入社してきました。ケアマネ業務やるのウチの施設が初めてらしいです。昔現場経験あって受験資格満たしていて、病気で身体壊して介護の仕事やめてまた介護の仕事戻ろうと思いケアマネの資格取ってウチの施設に来ました。身体壊した後遺症で身体介護とかは手伝えませんという条件で。経験がないんだか余裕がないんだか人間性なのかとにかく業務ができないんです。上から目線で、利用者を自分で見に来なくて忙しい時に限って利用者の状態聞いてくるんですよね、だからみんなキレてます。で時によっては答えられない職員に声荒げて逆ギレされてるし、アセスメントしないで職員にアセスメントシート書かせてるし、書いている途中の業務日報を勝手に持っていくし(日報に貼っといたメモを捨ててしまう。)いつも忙しいといって事務所のパソコンとほとんど1日にらめっこ。朝の申し送りのあと忙しいのに担当者会議やるし…書類作ることしか頭にないんですよね。で、施設長はケアマネの行動を容認してるし、ケアマネはどうすれば業務がうまくいくか聞かない勉強しない。現場のの職員はいつかはギャフンといわせてやるって息巻いている人もいます。僕はケアマネに何かあったら報告、連絡まめにして、コミニュケーションとるようにしてますが他の職員はケアマネと話すのもやだって空気になってます。どうなるか怖いです。ケアマネも入って半年間以上たつからもっとかんがえて業務してほしいです。
>かずさん
お久しぶりです。
コメントありがとうございます^^
仕事ができないのに上から目線のケアマネって嫌ですね。
多職種と上手く連携できない時点でケアマネの職業倫理から逸脱しています。
現場職員よりもケアマネの方が偉いと勘違いしている人が少なからず存在するのでしょうね。
ケアマネは多職種協働においてリーダーシップをとっていく必要がありますが、報告や連絡をしてもらいやすい雰囲気や環境づくりが大切ですね。