介護業界に身を置いて介護現場で働いていると意外と多いのが「出戻り就職」です。
つまり、一旦退職した介護職員が再び同じ介護事業所に戻ってきて雇用されるのです(再雇用・復職)。
もし自分だったら、「一回辞めた会社に再雇用や復職は絶対に望まない」と思ってしまうのですが、「別にそうは思わない」と思う人もいるということになります。
また、他の業界よりも介護業界は出戻り就職が多い印象もありますし、実際多いのではないでしょうか。
今回は、リクエストを頂きましたので「介護職員の出戻り就職が多い理由とそれぞれの思惑」について記事を書きたいと思います。
介護職員の出戻り就職が多い理由
介護職員の出戻り就職は何故多いのでしょうか。
理由①「人手不足だから」
介護業界全体で人手不足です。
中には、そうではない事業所もあるでしょうが、それは「特殊な例」と言えるほど人材が足りません。
つまり、人材が喉から手が出るほど欲しいのですから、辞めていった介護職員が「再雇用して欲しい」と希望するのなら事業所側も「是非是非、どうぞどうぞ」となるでしょう。
需要と供給がマッチしているのです。
但し、退職する時に「円満退社」をしていなければ、お互いに軋轢が生じてしまい出戻りへの障壁となってしまう可能性があります。
理由②「お互いをよく知っているから」
出戻りする際は、出戻り職員も事業所もお互いのことがよくわかった上での再雇用となります。
在籍時に勤務態度や仕事ぶりに問題がない職員であれば、事業所側としても雇用しやすいと言えます。
全く知らない人材を1から面接をして職場内の規律や仕事を教えるよりも、ある程度知っている人材を再雇用する方が労力やコスト的にも得策ですし、即戦力となり安心感があります。
出戻り側の介護職員も、職場内の業務や内部事情をある程度知っているため、溶け込みやすく安心感があります。
お互いがお互いをよく知っていて安心感があるため、出戻りしやすいと言えます。
理由③「結局はどこも大差がない」
より良い環境と待遇を求めて転職したものの、結局はどこの事業所も大差がないということは往々にしてあり得ます。
同じ介護業界であれば、介護保険制度の中で似たような運営になることでしょう。
変わってくるとしたら、それは「人間関係」です。
こればっかりは、入職してみるまでわかりません。
口コミや評判を慎重に調べて転職したとしても、実際に自分の相性に合うかどうかは働き始めてみないとわからないのです。
たまたま自分に合う職場が見つかれば御の字ですが、「石を投げればブラックに当たる業界」では、なかなか至難の業です。
「転職をしてみたものの、明らかに前の会社の方がマシだった」という場合は、「出戻りが可能であれば出戻りを選択する人も少なくない」ということになろうかと思います。
介護職員の出戻り就職におけるそれぞれの思惑
出戻り職員が発生すると一瞬職場内がざわつきます。
「退職していった介護職員がまた戻ってくる」のですから、そこには様々な人の様々な思惑が交錯します。
出戻り職員
出戻り職員自体はどういった思惑があるのでしょうか。
- 辞めた職場に出戻りする気恥ずかしさ
- 辞めた職場で再び受け入れてもらえるかの不安
- 辞める前と同じかそれ以上の待遇とポジションを期待
- 全く何も気にしていない
というパターンが考えられます。
もし私だったら、出戻るのは相当勇気が要ります。
だから「絶対にそれはできない」と思うわけですが、中には「生活のため」「家族を養うため」にそんなことは気にしていられないという人もいることでしょう。
また、一回退職したことで自分の価値を上げてそれをアピールできれば、ひょっとしたら以前より良い待遇で迎え入れられている可能性もあります。
これは「辞め方」と「辞めたときの貢献度やポジション」によって変わってくるかと思います。
もし、待遇をアップできているのなら「相当有能」だと言えます。
介護事業所側
出戻り職員を受け入れる介護事業所側は、「嬉しくて嬉しくて仕方がない」のではないでしょうか。
いつまでも引きずっていた別れた恋人(又は配偶者)と再会し、ヨリが戻った気分に近いかもしれません。
「以前勤められていた〇〇さんが〇日から戻って来られます」
と嬉しそうに発表している経営陣や上司の姿を見たことがあります。
「元鞘」「やはり自分(事業所)は他所と比べても選ばれるような存在だった」という自信を与えることになるでしょう。
それが事実か否か、良いか悪いかはさて置き、浮足立っているのは間違いありません。
「復職パスポート」というものを発行して出戻りを支援する試みをしている法人もあるようです。
詳しくは下記記事をご参照下さい。
受け入れる介護職員たち
出戻り職員を受け入れる介護職員たちはどういう思惑があるのでしょうか。
これは、出戻り職員の人格や貢献度や相性によって全く異なる印象を受けることでしょう。
もちろん、中には「1回辞めたくせに出戻ってくるなんて図々しい」と思う人もいるでしょうが、個人的には「出戻り職員の人による」と思っています。
そもそも、「職業選択の自由」は憲法で保障されているわけですし、他人の権利を害したり公共の福祉に反しないのであれば、どの仕事をしようとどの事業所で働こうと自由です。
しかし、出戻り職員が「自分とは相性が良くない職員」「人格に問題がある職員」「業務上問題がある職員」であれば、内心穏やかではありません。
そんな職員であれば「戻ってこなくていいのに」と思ってしまうかもしれません。
そうではなく「相性の良い職員」「普通の職員」「貢献度の高い職員」であれば、人員不足が少しでも解消され業務負担が軽減するというメリットもありますし「また頑張って下さい」と思うことでしょう。
結局は「出戻ってくる職員によって印象が変わってくる」ということになります。
そして、「出戻り就職をする」という自分が持ち合わせていない「勇気」や「判断力」や「行動力」や「人間性」や「価値観」を非常に興味深く感じます。
例えば「他の事業所を経験した上で意図的計画的に出戻ってきた」という場合があるかもしれません。
それは凄い行動力と能力だと思います。
どちらにしても、事業所が許容し判断したことを、いち介護職員がどうすることもできないので、「自分や職場にとってどう影響するか」「自分が得るものがあるか」ということが思惑の判断基準になってくるのではないでしょうか。
最後に
今回は、「介護職員の出戻り就職が多い理由とそれぞれの思惑」について記事を書きました。
万年、人員不足の介護業界であれば、出戻り就職も普通にあり得る話ですし、ひょっとしたら今後益々増えていくことも考えられます(私は出来ませんが)。
「出戻り職員」が登場すると、様々な思惑が交錯しがちですが、「自分や職場に与える影響」がプラスであれば特に問題はないかと思っています。
ただ、自分や職場に悪影響を与える「出戻り」の場合は、悩みの種が増えてしまうことになってしまうため、ネガティブな印象を抱いてしまいます。
幸いにも、今まで経験した「出戻り職員」はネガティブな印象も出来事も無かったために「どちらかと言えば肯定派」と言えます。
自分が出戻りをする勇気も行動力もないため、ただ単純に「凄いなぁ」という思いはあります。





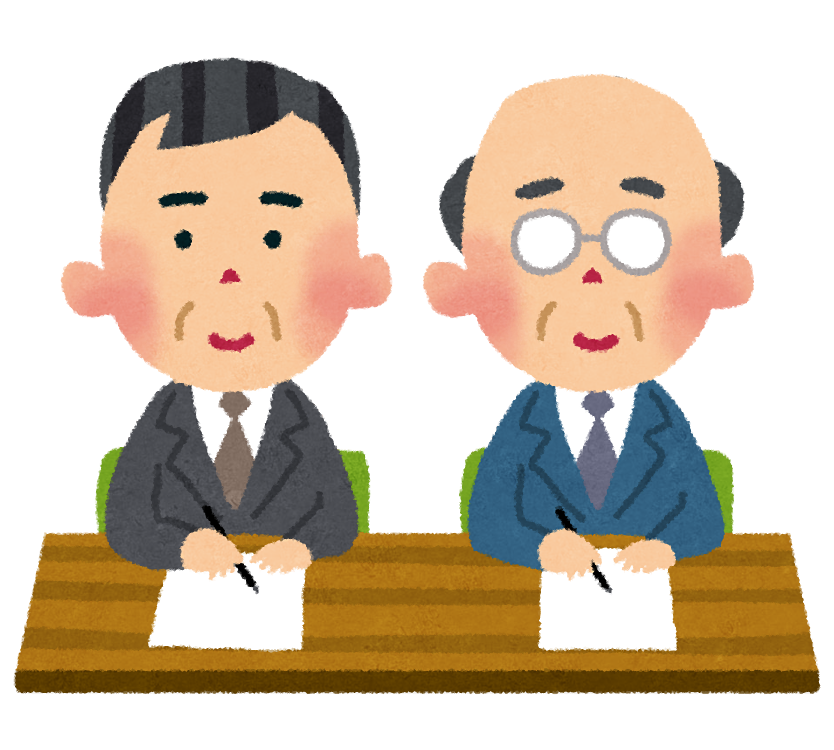






コメント
ありがとうございます。
他人のちょっとした発言でも悪く取って職員どうしの人間関係ぶち壊す人なんで職場での言動には注意してトラブルに巻き込まれないようにしていこうと思います。
自分も今の施設一度辞めた時は態度が悪かったんで出戻る時はそういうレッテルはられてるかなと思い態度には気をつけて周りと上手くやるよう心がけていました。幸い介護主任意外の職員は普通に接してくれていて良かったですが…。
その職員もいい意味で変わっていることは願うしかないです。
>かずさん
本当そうですよね。
良い意味で変わってくれていればいいですが、期待の多くは裏切られることが多いですからどちらに転んでもまずは巻き込まれないようにはしたいものですね。
来月から出戻りで職員が入社します。
2005年に辞めたから16年ぶりです。
はっきり言って『人格的に問題のある職員』です。辞めてくれて良かったなんて言われてたくらいですから。前の在職中は今の介護主任と仲良くて好き勝手にやってました。色々吹き込んで揉め事も起こしていたし…。辞めた理由が新人職員をイジメて当時相談員だった今の施設長に注意されて逆ギレして辞めました。その施設長に人手不足だから戻ってきてくれと連絡うけて戻ってくるそうです。前の職場で調理員やっててその職場が体制変わって辞める事になったので丁度いいって戻ってくるそうです。介護主任除いて職員皆嫌だなって言ってます。
ちなみ今の施設にその人の夫が宿直員を去年の4月から、長女が3年前から働いてます。長女は嫌がってるみたいです。
母親を『問題児』って言ってたくらいですから。ちなみに長女は4月まで育休中です。夫や長女は凄くいい人なんですが…揉め事がおきるのが怖い、そんな人に声かけて施設長は狂ってるって皆言ってました。どうなる事やら…。
>かずさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
初めからレッテルを貼ったり過去の印象や評判で判断しないようフラットな気持ちでいたいのは山々ですが、人間性とか問題がある人というのはそう簡単に変わらない(というかむしろ年々ヒドくなる傾向もあり)でしょうから、人格に問題がある職員が出戻ってくるというのは少々心配ですね。
そういう火種になりかねない人にまで声を掛けなければならないというのは、施設が本当に末期なのでしょうね。
色々お察し致します。。。
1 逆に他業界ってあまり出戻りは聞かないのはなぜでしょう?
本記事の延長上な気もしますが、出戻ってみたいなと思うところもあったりします。
そこには不満はなく、むしろ自分にはもったいないぐらいの会社でした。だからこそ、喧嘩別れではないけれど変な退職だったのでなおさら戻れませんけど。
別業界で知る限り、1件だけ。その昔転職したものの、嘱望され熱意に負けて戻ったと方。言い訳作りだけれども、こうしたポジティブさがないと難しいでしょうかね。
ちなみに、ブラック介護施設の折は、本記事や他の方が触れているようなネガティブな出戻り話はチラホラ聞こえました。
2 他のコメントに触れるのはあれかもしれませんが、食事排泄入浴の基礎だけやっていればいいなんてとてもうらやましいなと思います。
ブログ的にはそぐわない意見と思いますが、介護なんて基礎だけやっていればいい十分です。ただ、それ以外をやる/望むならその分は請求する/されるべきだと思います。
介護もいろいろあるのも問題ですが、少なくとも特養にデイサービス相当を要求されても…とブラック介護施設のときに痛感したしだい。
嫌なヤツも問題でしょうが、ほんとキラキラ職員ってヤツは・・・
3 記事案?または過去記事に当たるかもしれませんが、「介護に直面したときにどう動く(最初に頼る)のか」みたいなこと。
ただ、相談センターって聞いたことがありますし、他にネットにあげている方々もいたりしますが、ネットの欠点は調べ方が悪いと絶対その情報は手に入らないですからね。
正確には、「介護職員が身内で、自身が介護をせざるを得なくなったときの動き方や頼り先を就職先の事業所が教えているのかどうか」です。
私は教わったことがないです。優良と思うとこでもブラックでも。
これって介護に従事るものの当たり前でしょうか?私も介護畑(学校)でではないのでそんな心得もなく入った口ですし。
なんとなく初任者研修資格のおりにチラと触れていたような気がししなくもない程度の記憶ですし。
ボディメカニズムだの口腔ケアだのは正直どうでもいいから、ほんと従業員のためになるようなことってやらないですね。
また、介護職員の介護ってあまり聞かないですよね。よくも悪くも退職理由なんて捏造もできますからね。保育士が産めないはたまに聞きますけど、介護に直面した介護職員なんて想像できそなものですが・・・
>めど立てたい人さん
こんにちは~
コメントありがとうございます^^
>1 逆に他業界ってあまり出戻りは聞かないのはなぜでしょう?
確かに他の業界では出戻りはあまり聞きませんね。
理由としては「それほど人手不足というわけではない」「出戻りを許す風土や風潮がない」ということが考えられます。
そういった理由であれば、仮に「出戻りしたい」と思う人がいたとしても、なかなか打診しづらいために「実際に出戻りを申し出る人もいない(極端に少ない)」ということになるのではないでしょうか。
>2 他のコメントに触れるのはあれかもしれませんが、食事排泄入浴の基礎だけやっていればいいなんてとてもうらやましいなと思います。
今の給料と業務負担が「割に合うか合わないか」を考えれば、財源の乏しい介護保険内であるならば「三大介護だけの提供に留めておけばいい」という考え方は私も持っています。
仮にそうなったとしても、「業務負担を減らしたのだから人員を削減する」ということになれば本末転倒ですし、人間関係などの職場環境も働きやすさに影響してきますので、トータルで考えていく必要はあるでしょうね。
隣の芝は青く見えるものなのかもしれません。
>3 記事案?または過去記事に当たるかもしれませんが、「介護に直面したときにどう動く(最初に頼る)のか」みたいなこと。
「介護職員の介護離職」なんて目も当てられませんよね。
業界としても事業所としても、もっと情報発信やアナウンスがあっても良いと私も思います。
貴重なご意見ありがとうございました^^
介護は基礎だけやっていれば十分、否定はしませんよ。今の特養とか人手不足の現状とか考えたら。
無事に1日利用者が生活できたらそれでいいと考えるようにしています。
色々な考えもありますから意見交換などもしていきたいですね。
必ず出戻り職員はいますよね。
ホント隣の芝生はよく見えるを体現している業界だと思います。
出戻ってもまた辞めちゃう人もいますし。
気持ちに余裕ができて働くのが苦じゃない職場が理想ですがなかなかないですね…。
>かずさん
こんばんは~
返信ありがとうございます^^
誰でも最終的には「自分にとってプラスになるかどうか」ということを考えていますからね。
しかし、介護現場ではその当たり前の感覚さえ失念してしまいそうになることがあります。
どんな形であれ状況であれ、自己防衛は忘れないようにはしたいと思っています。
同感ですね。自己防衛は本当に大切だと思います。
身体もそうですが精神も壊れたら大変ですから。
>かずさん
お互い無理をしないように専守防衛で頑張りましょう^^
おはようございます。リクエストにお答えいただきありがとうございます。
僕は今の職場13年前に退職し昨年出戻りました。退職理由は両親の世話になった人の知り合い(県会議員)が特養つくるので誘われたのでケンカ別れではなかったです。新しい特養でデイで相談員3年10ヶ月、系列のケアハウスで四年1ヶ月勤めました。大変でしたがいい職場でしたが癖のあるオバヘルがいてささいな事でガン無視されたのとそのオバヘルの姉がケアマネしていて色々引っかき回しだしてきたので辞めました。五年前です。それから事業所何ヵ所か変えて昨年今のところに出戻りました。昔はレクや外出行事とか色々やったり実習生の受け入れとう色々やって活気がありやりがいがあったので、職安から応募して再雇用となりました。出戻りの自分が受け入れてもらえるか不安がありましたがその面では大丈夫でしたが現在は慢性的な人手不足で業務ただ食事排泄入浴を繰り返すだけで昔と比べて活気がなくなってました。正直失敗したかなと思ってます。Aさんのブログの記事を見るたび今の職場の問題点と被る記事が色々書かれてるのでホント考えさせられました。またコメントさせていただきます。長くなってすいませんでした。ありがとうございました。
>かずさん
おはようございます。
リクエスト&コメントありがとうございます^^
そうなんですね。
13年前に辞めた所であれば、経営陣はともかく従業員は大幅に顔ぶれが変わっていそうなのでスムーズに溶け込めそうですね。
その代わり活気がなくなり雰囲気や職場環境も変わっていたというのもあり得そうで納得です。
オバヘルや縁故採用等々、人間関係に悩まされるのはどこも似たり寄ったりでしょうね。
またいつでもお越し下さいませ^^