介護業界や介護現場に全く初めて飛び込んだ新人であれば最初のうちは右も左もわからないのは当然ですが、中にはそこそこの勤続年数があるのに一人分の仕事ができない介護スタッフも存在します。
こういう介護スタッフの特徴としては、「わざとそうしている場合」と「能力的な問題でそうなっている場合」及び、「その両方の場合」が考えられます。
もちろん他にも環境的な因子から、「新人の頃にちゃんと教えて貰えなかった」「介護事業所の教育や育成体制に問題があった」という状況も往々にしてあり得ますが、ここで言う「一人前の仕事ができないスタッフ」というのは、
- 世間一般の常識で考えて当たり前のことができない
- 同じようなミスを連発する
- ミスを連発しても反省する意思もない
- 楽をしようとしてわざとサボる
という介護職員等を指しますので、やはり個人的な因子が大きいと言わざるを得ません。
そういった介護スタッフが居た場合、周りのスタッフだけでなく利用者にも迷惑が掛かることになっていまします。
「ではどうすればいいのか?」「その対応方法や解決方法は?」ということについては、過去記事にまとめていますのでチェックしてみて下さい(下記記事参照)。
今回は、「そういう一人前の仕事ができないスタッフを押し付けられる介護現場の闇」についてリクエストを頂きましたので考察していきたいと思います。
一人前の仕事ができない介護スタッフを押し付けられる介護現場の闇
介護現場には様々なスタッフがいます。
職種の違いだけでなく、個々人の性格や人間性や能力など多岐に渡ります。
そういった人達の中には「一人前の仕事ができないスタッフ」もいます。
どんな職場でも少なからず1人くらいはそういうスタッフが存在しているのかもしれませんが、介護現場で一人前の仕事ができないスタッフを押し付けられる(又は押し付け合う)ということが常態化していると「みんな違ってみんないい」などという綺麗ごとでは収まりがつかない闇があったりします。
以下で詳しく見ていきたいと思います。
①人員(頭数)だけが欲しいから押し付け合いになる闇
多くの介護現場はまだまだ人員不足でしょう。
そうなると、人材という名の頭数が喉から手が出るほど欲しいわけです。
しかし、チームプレイで利用者の命を預かっている介護現場に「一人前の仕事があまりにもできないスタッフ」がいると困ってしまいます。
何故なら、周りのスタッフや利用者にも迷惑が掛かってしまうからです。
周りのスタッフは毎回必要以上の業務負担を強いられることになりますし、利用者は一定水準よりも低いケアしか受けられないばかりかスタッフのミスによって怪我などをしてしまう可能性も高くなります。
ですから、本来は一人前の仕事ができないスタッフが居てもらっては困るわけですが、常に人員不足の介護現場では「そんなスタッフでも居てもらわないと人員配置基準を満たすことができない」というジレンマに陥ります。
人員配置基準を満たさないまま運営をしていると行政指導や行政処分の対象となってしまうため、介護事業所としては絶対的に避けなければならないのです。
その結果、「一人前の仕事ができないスタッフも居てもらわなければ困る」という不健全な状況が発生するのですが、現場職員にしてみれば「地雷のようなスタッフには居て欲しくない」というせめぎ合いの中で押し付け合いが始まるのです。
押し付けられるのは大概が「パワーバランスで弱い立場の部署やフロアやユニット」となります。
人員配置基準を満たすために介護現場のレベルが下がり、現場職員の負担が増え、利用者のリスクが増すという本末転倒な状況は闇深いと言えます。
とは言え、人員配置基準を緩和すれば解決するような単純な問題ではなく、もっと根本的な「普通の人が働きやすいと思える環境を整備していくこと」が大切です。
②仕事が出来ても出来なくても給料は同じ闇
多くの場合、「介護現場で仕事が出来ようが出来まいが給料に変わりはない」という待遇になります。
むしろ、勤続年数によっては一人前の仕事ができない介護スタッフの方が給料が高いということさえあり得ます。
これでは周りのスタッフもモチベーションが保てません。
「人のことは気にしないようにしよう」
「自分は自分」
などと自分に言い聞かせてみても、介護現場はチームプレイなのですからそう単純に割り切れるものではありません。
何故なら、一人前の仕事ができないスタッフが居ることで自分の業務負担やリスクが増えるという「実害」があるからです。
一人前の仕事ができないスタッフを押し付けられることによって実害が発生する上に給料に変わりがないとしたら、「みんな違ってみんないい」などという綺麗ごとでは済ませられません。
それを良しとしてしまっている介護事業所が多い現実も闇深いと言えます。
③仕事ができない人が働きやすい闇
前述してきたように、「人員不足のため仕事ができない人も囲い込まざるを得ない」「仕事が出来ても出来なくても給料が同じ」という環境の中で、介護業界は「仕事が出来ない人にとってとても働きやすい業界」になってしまっています。
いやしかし、少なからず現場内では問題や実害があるわけですから、現場サイドで繰り返し注意や指導が行われていることでしょう。
但し、それが行き過ぎてしまうとパワハラやいじめや人権侵害になってしまうという問題も孕んでいます。
ですから、最終的に「現場サイドで押し付け合い」が始まるのです。
こういうことが常態化していると、
- 頑張っている人ばかりに負担と責任が掛かる
- 頑張っている人から先に潰れていく
- 頑張っている人から辞めていく
という悪循環に陥ってしまいます。
また、こういった環境の中では「頑張っても損しかしないのだから自分もサボってやろう」と考える人が出てきても不思議ではありません。
つまり、一人前の仕事ができないスタッフを野放しにすることで、
- 更に人員不足になる
- 更に介護現場のレベルが下がる
- 仕事が出来ない方が負担も責任も少なくて済む(給料は変わらない)
という皮肉な結果が待っているのです。
「仕事が出来ない人ほど働きやすい介護現場」ということになれば闇深いと言えるでしょう。
最後に
今回は、リクエストにお応えして「一人前の仕事ができないスタッフを押し付けられる介護現場の闇」について記事を書きました。
現状の介護現場では、過剰な負担や責任を押し付けられないような働き方をしていくことが必要であると考える一方、自分に与えられた最低限の仕事はこなしていかないと周りに迷惑が掛かりますし、ひいては介護現場の崩壊に繋がりかねません。
介護事業所の「頑張っているスタッフを守っていく姿勢や体制」も必要でしょうし、もっと言えば介護現場に求められている「質と量」及び、与えられている「対価」の関係を辻褄が合うようにしていくことで、闇の中の光明になるのではないでしょうか。











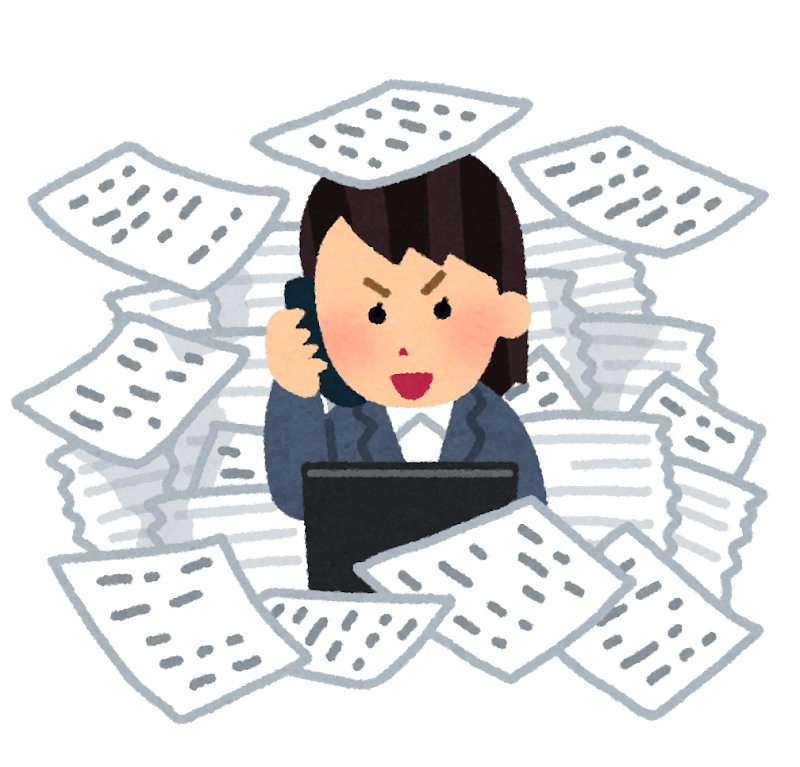



コメント
こんにちは。
新人が8月にデイに入って、何となく仕事が一通りできるようになったかな?となったんですが、案の定訪問のヘルプに出された後、なんと来年1月から訪問のS責になるんだって。
その人、実務者研修は受けてるんだけど、介護の仕事はデイが初めて。
で、ちょっと移乗とかできるようになったかな・・くらいでS責とか大丈夫なのかしら・・って全然大丈夫じゃないと思うわ。多分一か月で終了だわ。
どうしてそういう無茶無理ばかりするんだろうね。
デイに入った新人をデイで教育させて、ちょっとできそうなら、すぐ訪問に取り上げる。
訪問は無理な分割でどこの拠点も常勤がどんどんやめてる。でS責がいなくなったら配置基準違反で営業できなくなるからって、パートを無理やり名ばかりS責にしてる。
いよいよS責にする人がいなくなって、デイから新人取り上げてS責押し付けるなんて、本当にバカだと思う。
S責が重要な説明をしなきゃいけない場面で、「いや~私、介護経験が3か月で何もわからないんで~」じゃ、相手が怒るでしょうに。
ま、この会社は本当にクソなんで、働くのも利用するのも全くおすすめはしませんね。介護事業も赤字だと思うんだけど、どこまで突き進むんでしょうね。(笑)
>デイちゃんさん
こんばんは~
介護の仕事はそういうパターンが結構ありますよね。
良く言えば早く昇格できるのでしょうが、育っていない中間管理職を作り出してしまうことになり、その下で働くスタッフもその昇格したスタッフ自身も、ひいては利用者も不幸になる状況が往々にしてありますね。
私もブログ記事において「無能な上司」と揶揄していますが、実はその上司自身も被害者である場合もあるのかもしれませんね。
連投すいません。
何も仕事ができない奴を現場に押し付けて、他のスタッフから「あの人何も仕事できない」ってクレームになったら、まず管理者が言うのが「だったら仕事できるように他のスタッフが教えてあげなさい」ですね。
「いやいや、教えてもできませんよ」「致命的にスピードが遅いんですよ」「全く覚えませんよ」「指示しないと動かないですよ」・・・などと言っても無駄。「とにかくあなた達でなんとかしなさい」で終了。
あと、良心的なスタッフだと、何も仕事できないスタッフに重度の移乗とかやらせて事故になったらいけないから・・と、重度の対応は仕事できないスタッフにさせず自分ばかりしてしまう。
その結果、まともなスタッフの負担は増えてるけど、事故トラブルはおきないから、「まあなんとかなってるでしょ」ってなるパターン。
で結局、良心的な仕事できるスタッフがしんどくなって、やめていく。
私は仕事できない奴が来た場合は、とにかくそいつに仕事させますね。で事故トラブルになったら、そのスタッフの問題点が表面化するし。
もしそいつのせいで、仕事が終わらなくても、それを補おうとはせず、ずーっとダラダラやって残って残業つける。「あの人がいたら終わりませんよ」って言って。
前はサビ残強要があったけど、今は労働基準法違反を起こして罰金刑になると指定取り消しになるって介護保険法が改正されてるから、サビ残の強要にはならないでしょうし。
あ、そうそう、結構知らない人が多いと思うのですが、平成24年に介護保険法が改正されて、介護事業者がサビ残の強要など労働基準法違反したら保険者が指定取り消しするって変わってるんですよね。
すでに記事にありましたかね。もしなかったら取り上げていただきたいかも・・。
>デイちゃんさん
コメントありがとうございます^^
何だか全てが押しつけですよね><
現場の負担が増すばかり。
自分を守りながら働くしかないですよね。
平成24年の改正ですが、実際は罰金刑になっても罰金をちゃんと払えば指定の取消しにはならないみたいですね。
また記事にまとめたいと思います^^
どうもです。
実際には自分を守りながら働くのは難しい。
なので「ちょっと体を悪くしてしまって・・」「腎機能の数値が・・」などと弱々しく言って、急に一週間くらい休むことをおすすめします。(これ、はじめに就職した会社でよくしてた気がする(笑))
体を壊したとなったら、最近はさすがにブラックな会社でも、過重労働の無理強いはできませんからね。
で、「体が悪くなってしまったので・・」「仕事は続けられないかも・・」「とりあえず退職していったん休みます・・」など、辞めることをにおわす。
辞めるとなると、職場もちょっと大変よね。
いらない人なら「はい、さよーならー」「ごくつぶしがやっとやめてくれた」だけど、いらない人ってたいていは体壊すほど働いてないし。(笑)
働いてる人がいなくなったら、その人の供給してる労働量がなくなるから、がくーんとくるよね。
もし可能なら、「理不尽な状況を抜け出すのに効果的なやめるやめる詐欺のやり方」についてお願いします。
これ、結構需要あると思うのですが・・特にブラック企業にお勤めの方に。(笑)
>デイちゃんさん
返信ありがとうございます^^
私自身があまり辞める辞める詐欺に長けている方ではなく、上司に辞めると伝える時は気持ちが固まった時になるので効果的と言える記事が書けるかはわかりませんが、見聞きした内容も含めて機会があれば書いてみますね。
デイちゃんさんの職場相変わらずすさまじいですね。ウチよりはるかに酷いですね。ウチも頑張っているスタッフを守っていく姿勢や体制は全くないですし、仕事量と対価を辻褄があうようにする事は全くしていません。休日も一部の職員が優遇され、面倒な事は介護職に押し付け、職員もいないのに理事も施設長も三年後には施設建て替える事しか頭になく現状を見ようとしません。挙げ句の果てには意見した職人にお前らは目先の事しか考えてないって…。現実見ろよと思います。アホかとおもいました。というわけで退職決意したしだいです。デイちゃんさんも大変だと思いますがお体に気をつけて頑張ってください。
ありがとうございました。
「頑張っているスタッフを守っていく姿勢や体制」は全くありませんし、「仕事量と対価を辻褄が合うようにする」こともしていないです。
なので、対価に応じて仕事をするようにしていくしかないですね。
一人分の給料しかもらってないので、一人分の仕事をするようにセーブするしかないです。
使徒がいるかぎり仕事は終わらないでしょうけど、それもしょうがない。
入浴が10人残るでしょうけど、しょうがないですね。
>デイちゃんさん
こんばんは~
リクエストありがとうございました^^
そうですよね、「1人分の給料しか貰っていない」ですものね。
介護職員の給料が格別安く感じるのはそういう点でしょうね。