介護事業所で働く人達の中には、今現在与えられている年次有給休暇(以下、有給と呼ぶ)を自由に消化できないという状況や環境があるのではないでしょうか。
2019年4月から、10日以上の有給を持っている労働者には年5日の有給を取得させることが義務化されましたが(労基法第39条7項)、それ以上の有給取得がなかなか難しいままであるのも事実です。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
【引用元】 労働基準法
年5日は法律で義務化されたため取得できますが、それ以上の有給取得がしにくい理由としては、「多くの介護事業所で人員不足であるため職員各々に自由に有給を消化されるとシフトが回らなくなるから」という理由が大きいと考えられます。
となると、使いきれなかった有給は退職する際に消化することになりますが、ナント「退職する時にさえ有給を消化させてくれない介護事業所」が少なからず存在していて、泣き寝入りをする職員を何人も見聞きしてきました。
「有給申請を拒否するのは労働基準法(以下、労基法と呼ぶ)違反なのだから労働基準監督署(以下、労基署と呼ぶ)に相談をすればいいじゃないか」
「事業所には有給の拒否権はないはずだから強行突破で有給消化をすればいいじゃないか」
と思われるかもしれませんが、「大正解」です。
逆に言えば、「そこまでしないと退職時に有給を消化できない」というコンプライアンスの欠片も無い職場が存在していて、「そこまでできない退職者は泣き寝入りしか道が無い」と言えます。
今回は、退職時の有給消化に関する労基法をご紹介しながら「有給消化をさせてくれない介護事業所から有給を勝ち取る3つの方法」について記事を書きたいと思います。
退職する時に有給消化をさせてくれない介護事業所から有給を勝ち取る3つの方法
冒頭でも申し上げた通り、退職時に有給を消化させてくれない介護事業所から有給を勝ち取る方法としては、
- 労基署に相談する
- 強行突破で有給を消化して退職する
のどちらかになります。
上記の方法を更に具体的に3つの方法として以下でご紹介していきたいと思います。
方法①:労基署に相談して口頭助言をして貰う
事業所は労働者からの有給申請を拒否することはできません(労基法第39条1項)。
但し、事業所側には「時季変更権」が認められているため、別の日に差し替えることは可能です(労基法第39条5項)。
また、この労基法第39条に違反した場合は罰則もあります(労基法第119条)。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
【引用元】 労働基準法
とは言え、時季変更権で有給を別の時期に差し替えると言っても、退職する際に消化しようとしている場合は退職日が既に決まっている場合が殆どでしょうから、その日から逆算して全ての有給を消化できないと困りますよね。
ですから、本来であれば差し迫った退職前の有給消化には時季変更権は使えないはずですが、あなたが「有給消化の権利を放棄」したり「話し合いという名の泣き寝入り」をする場合は別です。
つまり、退職時に有給消化できないという状態は労基法違反であるものの、権利放棄や泣き寝入り(泣く泣く有給が使えない状態を認めた形)という客観的事実だけを見れば適法となってしまうのです。
「では、労基署に相談してすぐさま有給拒否の罰則を適用してもらおう!」
と思われるかもしれませんが、事態はそう簡単にはいきません。
何故なら、語弊があるかもしれませんが「労基署は事業所の有給拒否に関してはあまり積極的に関与してくれないから」です。
その理由として考えられるのは、
- 有給拒否に積極関与していると相談件数が多すぎて対応できない
- 事業所側も労働者側も自らの正当性を主張するため終局的な判断は裁判所になる
という点が挙げられます。
本当に労基法が謳う罰則を事業所に適用させようと思ったら、最終的に裁判を起こして違法判決を得る必要があるのです。
裁判となると時間もお金も手間も掛かってしまいますし、「裁判をするくらいなら泣き寝入りする方がマシ」と考えてしまう人が大多数となるのも不思議ではありません。
「それでは労基署も労基法の罰則も無意味ではないか」
と絶望を感じられたかもしれませんが、ここでおすすめするのが「労基署の口頭助言」です。
口頭助言とは、労基署が事業所に電話をして、
「そちらの従業員の〇〇さんから有給の相談があったのですが、有給取得は法律で認められた権利なのでちゃんとした対応をして下さいね」
「有給消化に関して、事業所と〇〇さん双方が納得できるような話し合いの場を設けて今一度検討してみて下さいね」
というような助言をすることです。
但し、これは行政指導でも命令でもなく「あくまで助言」であるため、強制力もなければ従わなかったからといって何かしらのペナルティがあるわけではありません。
ですから、口頭助言で絶対に有給消化ができるとは言えないものの、労基署からの口頭助言によって事業所側はある程度の心理的な圧迫を受けるでしょうから事態が好転する可能性は十分あるでしょう。
この口頭助言をしてもらうための要件は、地域を管轄している労基署に問い合わせて確認をするのが一番確実ですが、最低でも「有給申請を再三にわたり拒否された既成事実」が必要になります。
例えば、
- 有給申請書のコピーやそれが拒否された証拠となる書類
- シフト表や出勤簿やタイムカードのコピー
- 使用者や上司とのやり取りの記録(ICレコーダーで録音、メモに記録等)
などになります。
泣き寝入りをせずに労基署の口頭助言を活用して有給消化を勝ち取りましょう。
方法②:有給申請をした日は一切出勤しない
前述した労基署の口頭助言で事態が好転すればいいですが、助言には強制力がないので悪質な事業所の場合「やっぱり有給が消化できない状態から抜け出せない」ということもあり得ます。
そんな時におすすめするのが、「事業所に有給申請を拒否されたとしても有給申請をした日は一切出勤しない」という方法です。
つまり、実質的な強行突破です。
事業所は本来有給を拒否することはできず、退職日まで差し迫っているのに再三の話し合いも拒否されたり話さえ聞いて貰えないという状況であるならば、「自分の権利を守るために強行突破するしかないからやむを得ず」ということになります。
当然の権利を行使しているだけのことですから、何も後ろめたい気持ちになることはありません。
段階を踏んだ強行突破は適法ですし、事業所相手に裁判を起こすよりもお金も時間も手間も掛かりませんし、気分的にもマシでしょう。
そして、この方法で強行突破する場合も有給申請に係る書類のコピーを取っておき、使用者や上司とのやり取りの記録をしっかり残しておくことが重要です。
ただ、ここで気になるのは、
- 強行突破で有給消化中に会社から何度も電話が掛かってきたらどうしよう
- 強行突破で有給を行使した分の給料が貰えなかったらどうしよう
ということです。
上記2点については、以下で詳しく解説していきます。
会社から何度も電話が掛かってくる場合の対処法
有給消化を強行突破で行使した場合、再三会社から電話が掛かってくる可能性があります。
この場合、「有給申請をした通り現在有給消化中です」という返答をしておけばいいかと思いますが、「有給は認めていない」「早く出勤しろ」などと話が平行線になる事態が想定されます。
事前に労基署に相談をしておき、「労基署の指導のもと有給消化中です」と言うのも効果的でしょうし、それでもダメなら着信無視や着信拒否という対処法で相手にしないようにしましょう。
また、労働を強制したり脅迫する行為は労基法第5条の違反となり、違反した場合は労基法第117条の罰則が適用されます。
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
【引用元】労働基準法
ですから、「労働の強要は労基法第5条に違反し、117条の罰則が適用される可能性がありますので再三の電話で労働の強制をするような違法行為はもうやめて下さい」と言うのもいいでしょう。
要は、「自分は間違ったことはしていないという毅然とした態度」が大切です。
強行突破で有給を消化した分の給料が貰えない場合の対処法
有給消化を強行突破したものの、欠勤扱いにされてその分の給料が貰えなかったり、嫌がらせで本来入金されるはずの給料全額が貰えないという心配も出てきます。
そんなことになれば、せっかく有給消化を強行突破した意味が薄らいでしまいますよね。
給料が入金されるべき日に入金されるはずの金額が入金されていない場合は、まずは事業所に確認をします(嫌かもしれませんがやるべきことを淡々とこなしていく勇気と行動力が大切です)。
その結果、有給の強行突破が理由で賃金が未払いであった場合は速やかに労基署に相談・告発をしましょう。
これも語弊のある言い方かもしれませんが、「労基署は賃金未払い関係には積極的に関与してくれる」のです。
その理由として考えられるのは、
- お金に関する問題は白黒つけやすい(事実関係がハッキリしている)
- 労基法上、賃金未払いの悪質度は高いと判断される
という点が挙げられます。
立入調査に踏み切ってくれる可能性もあるので、各種証拠はしっかり残しておきましょう。
この場合の賃金未払いは、労基法第24条の違反となり、労基法第120条の罰則が適用されます。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
【引用元】労働基準法
また、賃金未払いが認められれば、当然強行突破した有給分と支払いが遅れた分の遅延利息(賃確法第6条)を含めた「正当な給料」が支払われることになるため、結果的に有給消化を勝ち取ることができます(参考:東京労働局「未払い賃金とは」)。
(退職労働者の賃金に係る遅延利息)
第六条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
【引用元】賃金の支払の確保等に関する法律
方法③:退職代行サービスを利用する
退職代行サービスには賛否両論ありますが、退職時に有給を消化させてくれないような悪質な介護事業所に対しては利用するのも有りだと思います。
「退職処理を他人(代理人)にして貰うなんて情けない」というご意見もあるかもしれませんが、これは一種の「労働問題であり法律上の権利義務に関する紛争問題」です。
法律上の紛争の解決を弁護士に依頼し介入して貰うことは何らおかしいことではありません。
しかも、退職代行サービスを利用することで、数万円ほどの依頼料で
- 時間も手間も省ける
- キッチリ有給消化をしてから退職できる
- 話がこじれても弁護士が対応してくれる
- 何より心強い
という多くのメリットがあります。
どうしても自分で強行突破する勇気がない人や事業所が悪質過ぎて手に負えない場合は、退職代行サービスを利用することで有給消化を勝ち取ることができることでしょう。
最後に
今回は、退職時の有給消化に関する労基法をご紹介しながら「有給消化をさせてくれない介護事業所から有給を勝ち取る3つの方法」について記事を書きました。
まとめると、
- 労基署に相談し口頭助言をして貰う
- 有給申請を拒否されてもその日は一切出勤せず強行突破
- 退職代行サービスを利用し弁護士等に対応して貰う
という3つの方法で退職前の有給消化を勝ち取ることになります。
有給消化をしてから辞めたいと思っていても、上司に言い負かされたり半強制的に有給を出勤に変えられるなど泣き寝入りをすることが因習となっている介護事業所も存在することでしょう。
また、
「どうしても勇気が出ない」
「事業所と軋轢が生じるくらいなら泣き寝入りでいい」
「自分が有給消化することで迷惑を掛けたくない」
という人もいらっしゃるでしょうが、当然の権利を行使しようとしているだけであって法律違反をしているのは事業所の方です。
もちろん、最終的にどうするかを決めるのは自分ですから自分が納得する答えが出せればそれが一番いいのですが、時として自分を守るためにやれることは全てやってみることも必要ではないでしょうか。
この記事が、退職する際に有給消化をさせてくれない事業所から有給を勝ち取りたい人のご参考になれば幸いです。











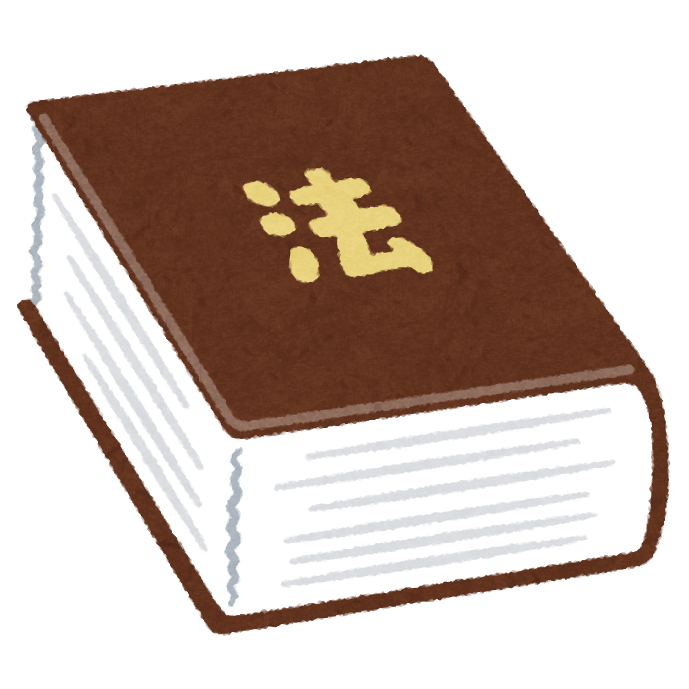

コメント
こんにちは。
私が昔働いていた超ブラックファミレスでは、毎日15時間以上の長時間労働&サービス残業で、下手したら72時間労働とか普通でした。月に1日休みがあるかないか的な。
有休なんてとれるわけがないというね。
で、やめる時にたまってた有休を使って、最終出勤日の2か月後が退職日と思っていたんです。ところがなんと有休が処理されておらず、最終出勤日が退職日になってました。
なのでその会社の人事部に問い合わせたら、当時の上司に問い合わせたところ、有休の処理を怠ったとのこと。
で、もう一回処理し直してもらったのですが、修正にめちゃ時間がかかりましたね。
人事部も全然人がいないみたいで、電話しても毎回同じ人しかいないという。(笑)
まあそのファミレスは今、倒産寸前になってます。おかしなことは続かないですね。(笑)
なので私は、やめる前に有休をまとめて消化するのは危険だと思っています。
有休を申請したのに処理されてなくて、もう一回問い合わせて修正を依頼して・・でも処理に時間がめちゃ時間がかかって・・みたいになるので。
なるべく働いてる間に少しずつ有休を使って、やめる前には有休を全部使ってしまおうと思っています。
そもそも有休自体をとらせない職場もあるかもしれませんが、その時点でブラック確定、転職一直線ですね。(笑)
介護業だと、有休をすべて消化できてる人なんて、ほとんどいないのではないでしょうか?
私のデイでも、有休を使われたら損なので、管理者が意図的にスタッフに有休の申請について教えてないんですよ。なので、私がスタッフ全員に教えてあげましたけど。
したらスタッフ全員が急に有休を使い出して、シフトが組めなくなりましたが。(笑)
でも教えてないのが悪いんですよね。おかしなことは続かないんです。
悪は必ず滅びます。鬼滅の刃みたいに。(笑)
>デイちゃんさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
飲食業界も色々大変だという話はよく聞きますねぇ。
確かに計画的に少しずつ有給を消化していくのも大切ですね。
とは言え、一度くらいは(辞める時くらいは)1か月丸々有給を取りたいという気持ちにもなりますし、そもそも当然の権利ですものね。
結論として、会社の状況的なものと自分の好みや判断で月に2日~3日ずつ有給を消化していくのもありでしょうし、全く有給が取れないという状況だけは避けたいものですね。
全然関係ないですが、管理人様は鬼滅の刃見てますか?
私はYouTubeに違法アップロードされた漫画を見たんですが、もう涙ダラダラでした。
それからも炎を聞きながら、鬼滅の刃関係の動画を見て涙をダラダラ流す毎日を過ごしています。
〇〇〇での日常と言えば、「自分はサボって他の人に仕事させるカスタッフ」「パワハラでスタッフをどんどんやめさせるダメ管理者」「ワガママし放題の嫌われ利用者」「理不尽なクレーマー家族」とか、水の呼吸 壱の型 水面斬りしたい奴らばかり。
やっぱり現実逃避って大事だよね~。
以前はエヴァンゲリオンにはまって、波形パターン青とか言ってたけど、今はうんこたれ流しの利用者を見て、「うんこの呼吸 壱の型 水様便たれ流し」とか心の中で叫ぶ毎日。
でも病院でも子供が注射するときに、看護師さんが全集中って言ったら、子供がじっとするらしい。そういうちゃんとした使い方もあるんだね。
さあ明日も25人の利用者にスタッフ3人とか絶望的な状況だけど、霞の呼吸で乗り切ろう。(状況が悪すぎておかしくなってるww)
もし鬼滅の刃見たことなかったら、超おすすめです。単行本は瞬間蒸発だけど・・。(笑)
>デイちゃんさん
返信ありがとうございます^^
鬼滅の刃はどこでも人気ですね~
ただ残念ながら私は見ておりません><
以前おすすめして頂いたエヴァを見ようと思ったら全話無料公開期間が終わっていたようで、5話くらいまでしか見れず余計に悶々としました(笑)
また時間が許す時に見てみたいと思います。
そうなんですね。
エヴァは用語が意味不明なので、それがわからないと?という感じですね。
人類補完計画?S2機関?LCL?ニアサードインパクト?アンチATフィールド?みたいな。
さあ今日も地獄の始まり。
地獄すぎて心拍数が上がりすぎて、鬼滅の刃みたいに痣が現れそうになったわ。
メンバーに、全く仕事ができない利用者にいじめられて泣いて帰ったバアサンと、スピードが超絶スローな看護師がいる。
思った通り、こいつらは全くの戦力外で、仕事を全くしない。
しかもこいつらに、少しでも仕事させようと作業をふったら、すべての作業が遅くなり逆効果。結局他の3人だけがもくもくと動いてる。(笑)
で、何も仕事を与えないと、バアサンとスローナースは、あろうことか、ダラダラと無駄話してる。
他のスタッフは目をつり上げて走り回ってるのに。
私はとりあえず、バアサンに「一人分の仕事をしてください」と穏やかに何度も教え諭しましたが、もちろん全く改善はありません。
結局、バアサンとスローナースは、全く仕事せず機能せずのまま終了しました。(笑)
そういう仕事しない人仕事できない人は、楽なので、結局やめないんですよ。自分は仕事しないからね。「今日も楽だったな~」って感じ。
まあ私はあと数回で長期休暇に入りますので、私がいなくて仕事が終わるかどうかやってみたらいいでしょ。
今日いた他の2人も年末年始は子供の都合で休むみたいだし。(笑)
今日は、「仕事しない仕事できない奴は、楽なのでなかなかやめない」という真理を再確認しました。
教えてくれてどうもありがとう。
でも会社も、そんな仕事しない奴に給料払うってムダじゃない?と思うんだけど。
人件費削減って言うなら、仕事しない奴をやめさせたらいいのにね。
もしよかったら、「仕事しないスタッフに会社が給料を払い続ける謎」について、記事にしてもらえたらうれしいです。って別に謎じゃないか。ww
>デイちゃんさん
返信ありがとうございます^^
確かに「介護の仕事って楽」とかしたり顔で言いのけてしまう人って一人分の仕事をしていないということがあり得ますね。
仕事をしないスタッフに会社が給料を払い続ける理由は結局はアレでしょうね。
言わずもがなな部分もありますが、また切り口を変えて記事にまとめてみようと思います。