介護業界に限らずですが、職場の人間関係は大切です。
介護職員の退職理由の上位には常に人間関係があるのも事実です。
介護現場での人間関係がこじれてしまう原因としては、
- 事業所の因習や排他性
- 自己顕示欲が強い人や性格がキツい人の存在
- 頑張る職員ほど損な役回りになってしまう構造上の問題
などが考えられるわけですが、それらをそのまま放置してしまうと組織として成り立たなくなったり介護現場が崩壊するキッカケにもなりかねません。
今回は、更に掘り下げて人間関係がギクシャクする介護現場にありがちな7つの失敗パターンについて記事に書きたいと思います。
人間関係がギクシャクする介護現場にありがちな7つの失敗パターン
介護現場の人間関係がギクシャクしてしまう失敗パターンを7つに分類してご紹介していきます。
パターン①:常に介護現場にしわ寄せ
常に介護現場にしわ寄せがいってしまう職場であれば人間関係が良くなりません。
介護はチームで行っているのですから、多職種で連携を取り協働していくことが求められています。
それなのに現場職員だけにしわ寄せがいってしまうとすれば不適切、不健全です。
多職種だけでなく、上司や経営者など「事業所全体で介護現場をフォローしていく」ということが大切です。
もちろん、各々職種ごとや役職ごとに守備範囲が違いますから、「介護職員の手伝いをして欲しい」とか「全員が常に介護現場で働いて欲しい」と言っているわけではありません。
ここで言いたいのは、現場職員だけに責任を押しつけたりしわ寄せをしないことで「こんちきしょう感が格段に減る」ということです。
「こんちくしょう!」
「悔しい」
「悲しい」
「腹立たしい」
という負の感情が芽生えることでストレスが発生し、ひいては職場内の人間関係もギクシャクしてしまうことになります。
現場職員に理不尽なしわ寄せをして「こんちきしょう」と思わせてしまうことがあれば失敗パターンと言えます。
パターン②:現場内の意見の相違
介護現場の中でも、職員ごとや上司との間に意見の相違が発生することはあり得ます。
その意見の相違が未解決のまま介護を続けてしまうと、「各々が好き勝手な介護や対応を行う」ということになり、チームとしての実力も発揮できず統一した介護もできず利用者も混乱したり利用者に迷惑を掛けてしまうことになりかねません。
もちろん、職員個々も「自分のやり方が一番良い(スタンダード)」と思っているため、意に反したやり方に反感を持ってしまうことになります。
現場内の職員間で対立し反感を持ちながら働くことで人間関係がギクシャクしてしまう失敗パターンになります。
パターン③:後ろから刺してくる
「後ろから刺してくる」とは、今まで味方や仲間若しくは自分の賛同者のように振舞っていた人や自分が信用していた人が、急に手のひらを返して裏切ってきたり、「実は最初から敵だった」というような状況を指します。
例えば、普段は自分の意見に賛同してくれていた同僚が他の人や上司の前では自分の悪口や陰口を言ったり、直属の上司に承認を得ていたのに公けの場になると上司が「私はそんなことは言っていません」などと言って梯子をはずしてくるパターンです。
百歩譲って「信用してしまった自分がバカだった」のかもしれませんが、そういう環境があると人間関係がギクシャクしてしまうのは必至でしょう。
狐と狸の化かし合いの場では人間関係が上手くいくわけがありませんし、少なからずそういう人がいて、そういう人が得をする環境があるのであれば失敗パターンだと言えます。
パターン④:現場を無視したワンマン経営
ワンマン経営には、意思決定が早く方向性が明確化できるというメリットがありますが、介護現場をあまり知らない経営者が発する現場を無視した鶴の一声には辟易してしまうことでしょう。
せっかく、現場内や多職種で連携をして決定したことさえも経営者などにいとも容易くちゃぶ台返しをされてしまうと、専門職の存在意義もなくなってしまいますし組織としてもあまりにも不完全で未熟なものになってしまいます。
こういった悪しきワンマン経営は、真面目に職責を全うしようとする職員とイエスマン(後述)との間で人間関係をギクシャクさせてしまう失敗パターンになります。
パターン⑤:イエスマン
経営者などの鶴の一声で職場内の方針や利用者の対応が変わってしまう職場では、イエスマンでなければ働き続けることが難しくなっていきます。
もうそこには、「職業倫理」や「法令遵守(コンプライアンス)」は形だけのハリボテでしかなく、正しく職責を全うする職員や経営者と違う意見を持つ職員は排除されたり、立つ瀬が無くなる環境が待っています。
そんな環境の中では、イエスマンはえこひいきをされ、イエスマンではない職員は最悪の場合、退職を選択するしかなくなってしまうことでしょう。
イエスマン以外を排除してしまう介護現場は多様性を認めているとは言えず、人間関係もギクシャクしてしまう失敗パターンだと言えます。
パターン⑥:お局職員
介護現場に必ずと言っていいほど存在するのが「お局職員」です。
口だけは達者で自己顕示欲が強いのに、自分は大して仕事をしない恐怖政治を行う悪の権化のような存在です。
リーダーや主任といった直属の上司の場合もありますし、勤続年数が長いパート職員の場合もあります。
一言で言うなら「猿山の大将」という感じです。
こういう職員が職場にいると人間関係がギクシャクしてしまう原因となり、それを放置している事業所にも問題がある失敗パターンになります。
パターン⑦:現場職員の反発
「常に現場にしわ寄せ」「後ろから刺してくるような職員」「ワンマン経営」「お局職員」などなど、人間関係がギクシャクしてしまうような様々な原因があれば、現場職員の反発も発生しやすくなります。
反発と言っても、「てめえ、この野郎!」というようなものもあれば、「いやもうさすがに無理です」というようなものもあります。
どちらにしても、「介護職員vs介護職員」「介護職員vs他職種」「現場職員vsお局職員」「現場職員vs上司」「現場職員vs経営陣」というような対立関係が成立してしまうことになります。
反発が起こり対立関係が発生すると、介護現場の人間関係はギクシャクしてしまいます。
ひいては、退職者が後を絶たない職場になってしまう失敗パターンだと言えます。
最後に
今回は、人間関係がギクシャクする介護現場にありがちな7つの失敗パターンについて記事に書きました。
まとめると、
- 常に介護現場にしわ寄せ
- 現場内の意見の相違
- 後ろから刺してくる
- 現場を無視したワンマン経営
- イエスマン
- お局職員
- 現場職員の反発
という7つになります。
どれもこれも共通しているのは「理不尽」ということです。
介護現場に存在する理不尽を減らしていくことで人間関係が良くなっていき、ひいては退職者を減らすことに繋がるのではないでしょうか。











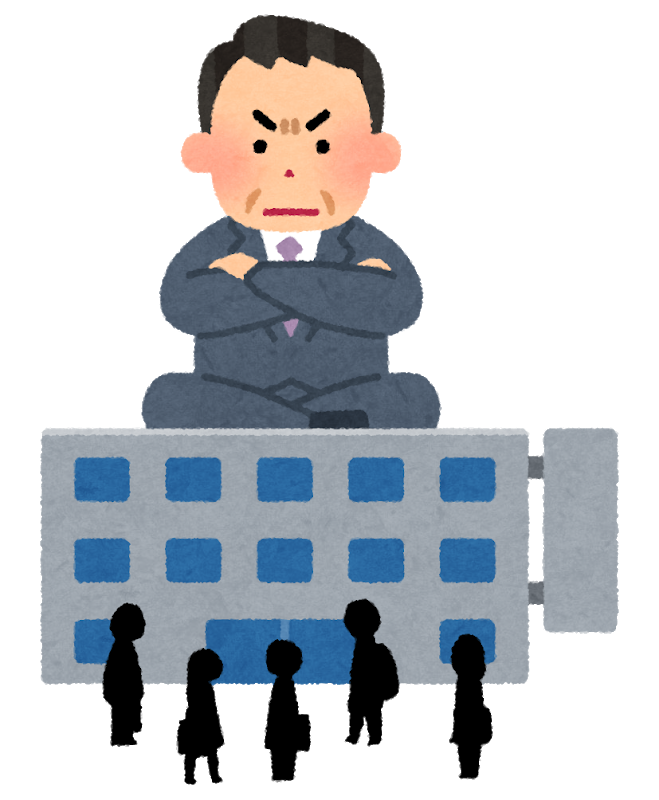









コメント
そうなんですよ。「正義は勝つ、悪は滅びる」状態が維持されれば、組織の平和は保たれますね。
私のデイでは、上記の7つ以外に、
⑧サボりまくってるカスタッフから全体に蔓延するサボり体質
⑨何らかの障害が疑われる異常な人間が場を荒らしまくる
がありますね。
私のデイは、昔は、スタッフは働き者ばかりでそれなりにスキルもちゃんとしてたし、人間関係がよくてスタッフの定着率も高くて、スタッフがた~くさんいたんですよね。
それを見たセンター全体の管理者が、「デイは人がいるから」「デイは回るから」と、デイの仕事のできる人を訪問や福祉用具など他に回し、他の事業所の仕事できないいらない奴らをデイに押し付けた。
それを繰り返してるうちに、デイにはさぼりまくりの仕事できない仕事しないカスタッフばかりに。
ババアナースとババア介護福祉士がサボりのはじまりだったけど、その後グルホのカスタッフが続々と投入され、座ってるだけの中年男、休んでばかりの常勤妊婦、日本語の不自由な生活相談員など、次々とデイを侵食。気がつくと、すべて腐りきってしまったのでした。
そうしてるうちに、登場したのが使徒スタッフ。
中には統合失調症など真性の精神病の人もいましたが、たいていは診断なし。
日本語不自由、仕事は全くできない、事故事件ばかり起こす、注意しても直らない、暴走する、利用者や家族からのクレーム多数、市役所に通報される。
「どうしてこんな人雇ってるの?」状態。
私は昔だったら、怒りまくってたと思うんですよ。
でも今は、とりあえず静観する。静観してるとすぐに事件事故が起きて崩壊するから。で、重度の利用者さんが利用終了になったり。利用者少なくなれば、楽になるしね。
「え?売上減ったら困るんじゃない?」「赤字になったら、あなたもやばくない?」
いえいえ、大丈夫ですよ。私は他の収入源があるので。
もしかしたら事業所がなくなったり、会社自体がなくなるかもしれないけど。むしろ存続してるのがすごいと思う。(笑)
とりあえず自分にできることをゆ~っくりやろうと思っています。
>デイちゃんさん
コメントありがとうございます^^
なるほど、同僚スタッフはいつも一緒に働くことになりますから自分にも直接影響してきますものね。
会社が何も対応をしてくれないと自分で自分を守っていくしか手がありませんね。
理不尽と言えば、一番理不尽なのはカスタッフ達ですね。
とにかく仕事しない。管理者が注意しても直さない。注意されるからミーティングすら出ない。(笑)
管理者が、「スタッフが言うことを聞かない」「スタッフのさぼりが直らない」って言ってたんだけど、サボりは教育でどうにかなることじゃないと思う。
サボるのはスタッフの人格だと思う。
「一生懸命働くのが普通」「サボる=人としてはずかしい」って良識がない人は、「楽をして金をもらうのがいいことだ」「少しでもサボって楽をして金だけもらいたい」と思ってるから、何を言っても無駄だと思う。
怠け者の人格は矯正しようがないと思うし、それは管理者の仕事じゃないと思う。
しかも最近じゃ、ちょっと高圧的に言えばパワハラって言われるし。
いいスタッフがたくさんいれば、仕事しない仕事できないスタッフなんて簡単に首にできるのに。いや最近は簡単に首にできないか。
でもスタッフがさぼってるのを許してるのは会社。普通はそんな怠け者に金払ったりしない。なのに「まあ他の働き者の人がカバーしてくれるでしょ」って甘く考えてる。
甘い甘い。一人サボりだしたら、みんなサボるよ。
だって「あの人はサボってるだけなのに、どうして私だけが働かなきゃならないんですか?」ってなるでしょ?あなたも。
私は、金をガメてる会社にもムカつくけど、どっちかっつーとサボりまくってる怠け者のカスタッフの方がムカつくかも。
ま、ストレスは体に悪いので、自分もスルースキルを高めなきゃ。(笑)
>デイちゃんさん
返信ありがとうございます^^
頑張っている人が損をする、又は、理不尽さを感じてしまう環境は良くないですね。
しかも真面目な職員もサボっている職員も同じ給料だったり、時としてサボっている職員の方が給料が高いなんてこともありますから尚更です。
それではモチベーションが保てませんよね。