新年明けましておめでとうございます。
2021年最初の記事となります。
今回は(も)リクエストを頂戴しましたので、「利用者からの介護職員への暴力やハラスメント」について記事をまとめていきたいと思います。
尚、利用者から職員への暴力やハラスメントについては、過去記事でも何度か触れてきています。
ですから、この記事では総まとめとして過去記事にも触れながら「介護職員が利用者から暴力やハラスメントを受けた場合の対処法」についてご紹介していきます。
【総まとめ】介護職員が利用者から暴力やハラスメントを受けた場合の5つの対処法
ニュース報道などで度々「介護職員による利用者への虐待や暴言暴力」について目にすることがあります。
しかし、実際の介護現場では「利用者による介護職員への暴力やハラスメント」が存在し、その数や頻度は介護職員による利用者への虐待などよりも遥かに多いのです。
そういった問題は報道されないばかりか、職場内で揉み消されたり、酷い場合は「介護職員の対応方法が悪いから利用者から暴力やハラスメントを受けるんだ」などという踏んだり蹴ったりの結果になってしまうことがあるため、なかなか日の目を見ることがありません。
つまり、多くの被害職員は「泣き寝入りをしている」というのが実情なのです。
そんな環境が常態化していれば、お世辞にも職場環境が良いとは言えません。
では、どういう対処法があるのでしょうか。
以下で詳しくご紹介していきます。
対処法①:上司や事業所全体で対策を講じる
一番健全でオーソドックスな対処法が、「上司や事業所全体で対策を講じる」という方法です。
利用者からの暴力やハラスメントの事実はハッキリしているのですから、現場職員に丸投げしたり責任を押し付けて泣き寝入りをさせるだけでは何も解決しません。
本当に解決していこうとするならば、やはり上司や事業所の介入が必要不可欠です。
この一番健全で必要不可欠な対処法が機能してこなかった結果が、現状の「現場職員の泣き寝入り」ではないでしょうか。
次回(2021年)の介護報酬改定の中にも介護職員に対するハラスメントの対策強化が検討されていますし、厚生労働省もYouTubeで「介護現場におけるハラスメントに関する職員研修」という動画をアップしているので、現場職員だけでなく事業所全体で対策を講じていく姿勢が重要です。
また、介護現場が「利用者の尊厳の保持という名の逆差別や治外法権や無法地帯」になってしまわないよう、事業所全体でできる具体的な対策について下記記事でご紹介していますのでチェックしてみて下さい。
対処法②:複数人で対応する
事業所全体での対策が重要であることを前述しましたが、そうは言っても結局は精神論で終わってしまったり、現場職員にしてみれば即効性や実用性が低い対策しかされない可能性もあります。
そんな場合に現場サイドで出来得るベターな対処法は、「暴力行為やハラスメントのある利用者の対応は複数人で行う」という方法です。
二人以上の職員で暴力利用者に対応することで、
- 被害を受けにくくなる
- 複数の目で事実を確認することができる
- 冷静な対応や判断ができる
- 責任や負担が1人に集中しない
- 複数人が証人となる
という効果があります。
人員不足でなかなか複数人で1人の利用者の対応をすることができなかったり、ワンオペ夜勤の場合は複数人で対応できないという懸念も残りますが、そこをクリアできないようではいつまで経っても介護職員を暴力やハラスメントから守ることはできないことでしょう。
暴力利用者に複数人で対応する方法については、下記記事でもご紹介していますのでチェックしてみて下さい。
対処法③:労災を申請する
この対処法は事後対応になりますが、利用者の暴力やハラスメントによって被害を受けてしまった場合は「労働災害保険(以下、労災)を申請」しましょう。
但し、申請は可能ですが労災がおりるかどうかはまた別の話となります。
労災が支給されるためには、診断書が取れるような身体的被害や疾病が存在していて、その被害が業務上発生したという因果関係を証明しなければなりません。
逆に言えば、それらの事実がハッキリしていて診断書や証拠もある場合は労災がおりる可能性が十分ありますので、泣き寝入りをせずに労災申請をしましょう。
労災申請については下記記事でも触れていますのでチェックしてみて下さい。
対処法④:安全配慮義務違反で事業所を訴える
さて、この辺りから対処法が少々穏やかではなくなってきます。
何故なら、「訴える」「裁判」「告訴」などが必要となってくるからです。
逆に言えば、そこまでしなければ泣き寝入りになってしまう可能性が高いという非常に手厳しい環境であると言えます。
まずここでご紹介するのは、事業所には労働契約法第5条と労働安全衛生法第3条1項に定められた「安全配慮義務」があるため、「利用者からの暴力やハラスメントを放置しているのは安全配慮義務違反に当たる」として訴える方法です。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
【引用元】労働契約法
但し、労働契約法は個別の労働問題や紛争の解決を目的とした私法であるため罰則がありません。
私法なのですから労基署もほぼノータッチですし行政指導の対象でもなく、自分で弁護士を雇うなりして民法上の
- 債務不履行(民法415条)
- 不法行為責任(民法709条)
- 使用者責任(民法715条)
などを主張して事業所と戦っていかなければなりません。
(事業者等の責務)
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
【引用元】労働安全衛生法
労働安全衛生法は行政刑罰法規であるため、労基署もタッチしてきますし行政指導等の対象にもなり罰則もあります。
但し、第3条の安全配慮義務には罰則がなく、他の条文や法律に当てはめたり
- 事業者が予測できた可能性があったかどうか(予見可能性)
- 事業者が回避できた可能性があったかどうか(回避可能性)
という視点で裁判で争っていくことになります。
過去の判例では、長時間労働による過労死やうつ病で自殺をしたケース、パワハラによって精神疾患を発症し長期間休職したケースで安全配慮義務違反が認められています。
とは言え、そもそも弁護士を雇うこと自体がハードルが高いため、実際問題裁判までする人は殆ど居ないというのが現状でしょう。
しかし、「事業所には労働契約法5条や労働安全衛生法3条1項で安全配慮義務が定められていて、違反すれば損害賠償請求ができる可能性がある」という情報は知っておいて損はないですし、本気で自分への被害や侵害から身を守るための手段の1つとしての選択肢を増やすことにもなります。
また、弁護士の無料相談や弁護士費用を状況に応じて払いやすいように対応をしてくれる国立の法律案内所として「法テラス」というものがありますので、利用してみるのもいいでしょう。
まだまだ訴訟や裁判はハードルが高いとは言え、泣き寝入りがスタンダードな業界ではどう考えても健全とは言えません。
対処法⑤:警察に通報する
こちらも穏やかではない対処法ですが、あまりにも上司や会社が何もしてくれなかったり、被害が甚大な場合は「警察に通報する」「被害届を出す」「告訴する」という方法も脳裏をよぎります。
要は、暴力やハラスメントを行う利用者本人の責任を追及したり罪を償ってもらう対処法です。
但し、ここで問題となるのは「利用者に刑事上の責任能力があるのか」ということです。
責任能力が無ければ不起訴となりますし、そもそも被害の程度や状況証拠などによっては被害届すら受理してもらえない可能性もあります。
もっと問題なのは、業務上の被害や損害が発生した場合は、まずは上司に報告して判断を仰ぐのが普通ですから、上司や事業所が警察を呼ぶという判断をしなければ自分の判断で警察に通報するという判断がし難いという点です。
とは言え、認知症のある利用者が介護職員をハサミで刺したという事件では、事業所が警察に通報し利用者が現行犯逮捕されたというニュース報道もありました(下記記事参照)。
ですから、暴力やハラスメントのある利用者の対処法として「警察に通報する」という対処法も全くないというわけではありません。
最後に
今回はリクエストにお応えして、「介護職員が利用者から暴力やハラスメントを受けた場合の5つの対処法」について記事にまとめました。
訴訟や裁判や通報など明らかにハードルが高い対処法も含まれていますが、選択肢の1つとして知っておいても損はないでしょう。
本来であれば、事業所が「介護職員等を守るための対策や判断」「安全配慮義務の遵守」をしていけば少しずつでも歯車が合っていき職場環境も健全化していくのでしょうが、利用者の暴力やハラスメントで悩まされている職場では事業所側のそういう姿勢や配慮が欠如していると言っても過言ではありません。
「会社は守ってくれないし、かと言って訴訟や被害届を出すのもなぁ…」と思っている人の多くは泣き寝入りをした上に、最終的には辞めていってしまうことでしょう。
介護現場での働き手が守られる健全な環境であって欲しいものです。






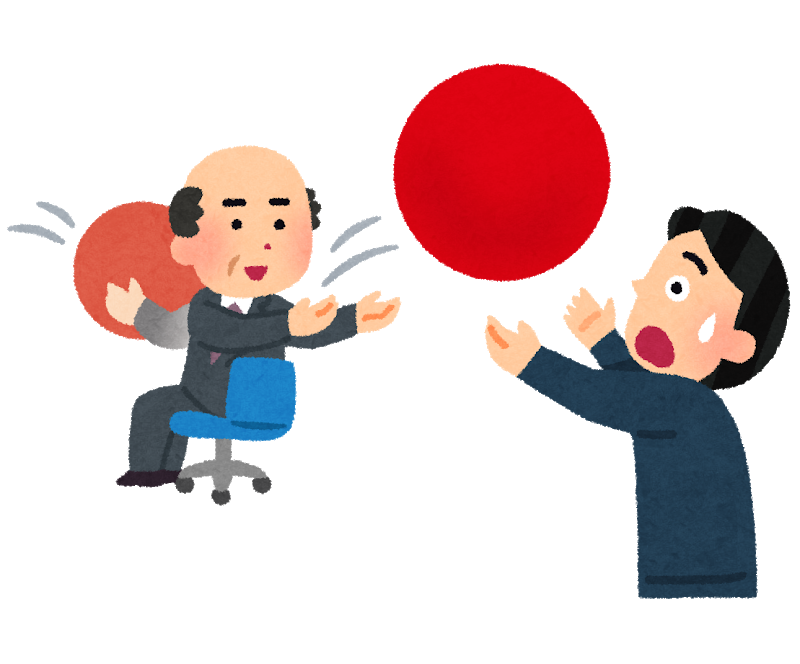

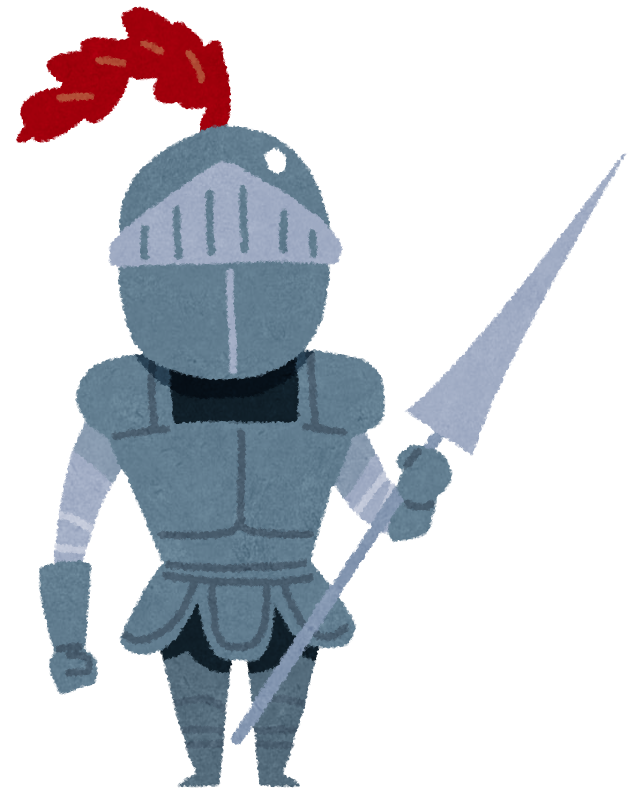





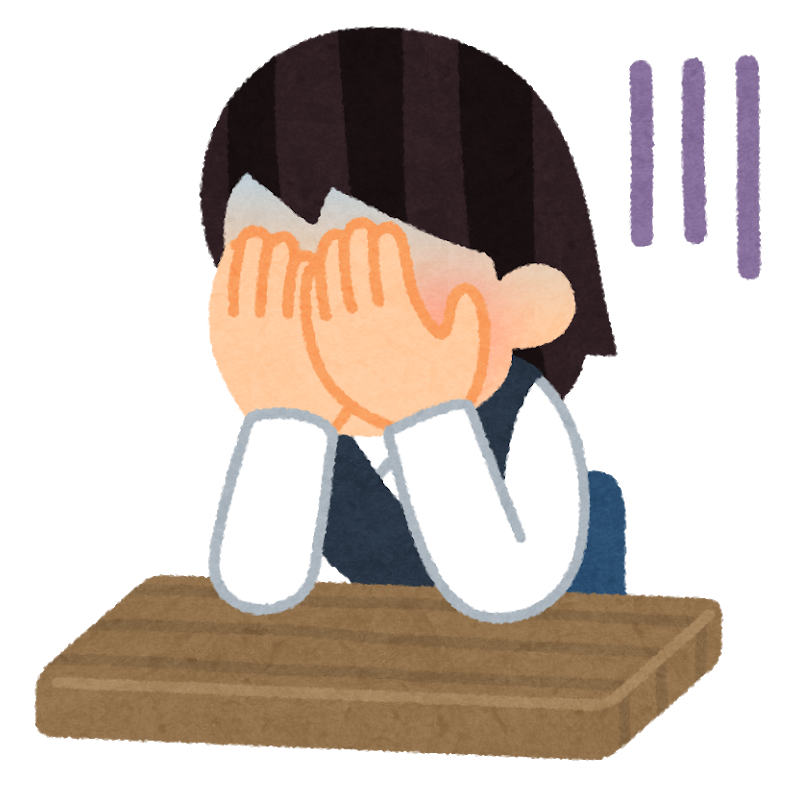

コメント
もう法人としては寿命が近づいてると思います…。亡くなった理事長の亡霊がきえてないので…。
>かずさん
社会福祉法人はなかなか潰れないと言われていますが、亡霊がいればそういうわけにもいかないかもしれませんね><
ウチの職場は施設長や職員も他では勤まらない職員多いですね。若い介護職員でも口の聞き方知らない人多いし。たまたま今の施設で上手くいっているから態度が大きい人何人もいます。前述の若い職員態度デカイくせに他で働く自信ないって言ってますから。ホントある意味ムラ社会です。だから施設長や看護師や相談員やケアマネは介護職をバカにして、介護職員どうしは悪口絶えない、だから信頼関係もないし、もうバラバラですね。
施設長は家族に言うべき事も言えないし職員も守ろうとしないから職員も集まらないんですよね。最近派遣雇いだしたし、終わりの始まりですね、ウチの施設…。亡くなった先代理事長がワンマンで職員をすぐ馘にしてたツケがきてますね…。
>かずさん
返信ありがとうございます^^
職場内には色々な人間性や性格の人がいますが、そこを管理していくのが上司や管理者の責務のひとつでしょうね。
上に立つ人間まで滅茶苦茶だと確かに「終わりの始まり」ですね。
昔は経営者のワンマンですぐに職員をクビにするような経営でもやっていけたのかもしれませんが、もう時代が変わりましたからね。
過去のそういうやり方のツケが回ってくるのも間違いないですね。
ホントそうですね、実は人情なしって人権なしって書こうとしたら間違えたんです。すいません。
アドバイスどおり記録やメモは自己防衛の為に取るようにしてます。
利用者の人権を守ると言ってる施設ほど職員の人権は守られてないですよね。
利用者にパワハラうけてどれだけの職員が辛い思いしてるか…だから虐待もへらないと思います。
>かずさん
返信ありがとうございます^^
そうですね。
職員がいるからこそ利用者に介護を提供できて売上になっているという基本的なことが見えない上司や経営者がまだまだ沢山いるのでしょうね。
ホント災難でした…そのあと腹にパンチと蹴り食らうし…。一緒にいた職員が黙っててやるから一発食らわせなよってマジな顔で言ってました。当然やりませんでしたけど。しかしウチの看護師やケアマネや相談員はその利用者が暴言暴力増えているのに対してなにも考えてないですね。病院の精神科から入所してきてるから状況を家族に報告して受診して薬調整してもらうとか。そういう事全然考えないんですよ。家族にいい顔ばかりするから。あと同室者で徘徊がひどい利用者がいて同室者の枕や布団を取ったり破いたりすごいんですよ、だから僕を引っ掻いた利用者含めもう1人の利用者も不穏になって大声だしてるんですよ。その利用者が原因だね、みんな不穏になるのは。他人や施設のもの破損してるのに家族に何も言えないんだね、ウチのケアマネや相談員は、ホントダメな施設だねって吐き捨てた職員もいました。今回の事は業務日報とケース記録とモニタリングにしっかり書いときましたが。
ホントに今度同じような怪我したらただでは済まさないですけど。ウチの施設の介護職は人権無しですからね、訴えます。あとは油断せずに慎重に介護を行います。自分や利用者の安全の為に。
>かずさん
返信ありがとうございます^^
介護職は人権無し…お気持ちお察し致します><
利用者からの被害や上司とのやりとりを日時とともにメモしておいたり録音しておくことをおすすめします。
もしもの時の証拠になりますから。
そもそも論ですが、介護職が守られていないのに利用者を守ることなんてできないんですよね。
そういう無理ゲー的な環境や風潮をどうにかして欲しいものですね。
遅くなりましたが明けましておめでとうございます。
去年の暮れですが一歩間違えたら右目失明(大げさかな?)しかけました。
認知症が酷く暴言暴力があり最近とみに酷くなってきた利用者(女性)がいまして、浴室に連れていく時も騒ぎまくっていて慎重にトランスで車椅子に移乗したんですが移乗して自分が手を離した瞬間利用者の手が顔に飛んできて右目の下を引っ掛かれました。5センチ位の傷ができて出血もしました。すぐ顔洗って看護師に消毒してもらい家にも抗生物質の軟膏とマキロンあるので帰ってからも消毒して軟膏塗ってました。かなり強い力で引っ掛かかれたんでもし1センチ上だったらもろ眼球だったんでゾッとしました。今は傷は消えましたが。
施設長は大丈夫ですかしかいわないし、
ケアマネは対策たてろというだけだし
看護師は医者に相談するかと言ってました。自分は半分皮肉半分本音で『怪我したのが自分で良かったですよ、利用者が怪我したら大変でしたからね。それ考えたら腹立ちませんでしたよ』って言ったら『エライ、プロですね』って。何がプロだよって思いましたが。怪我させたらわざとじゃなくても滅茶苦茶怒るくせにって思いました。もし目が指に入って大怪我したら警察沙汰にするつもりでしたが。今度同じ目にあったら訴えてやれよ、介護職員を人扱いしてない職場だからやってやれ!って言ってくれた職員もいましたが。安全配慮義務違反ですか、ウチの施設引っ掛かりますね。今度利用者に大怪我させられて大丈夫ですかだけで済まされたら訴えようかなと思います。いい事聞きました。ありがとうございます。まぁ、でも移乗した時点で油断した自分も悪いんですが。いい勉強になりました。長文すいません。
>かずさん
明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。
似たようなケースがうちでもありました。
その時は労災で処理されてましたね。
会社は労災を嫌がりますが業務上の事故は事故ですからね。
とにもかくにも災難でしたね。。。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
大勢の人がこの事実を知れたらいいんですけど。
>デイちゃんさん
こんばんは~
リクエストありがとうございました^^
そうですね、多くの人に知って欲しいですね。